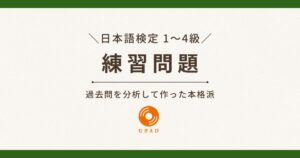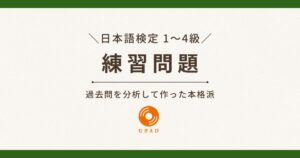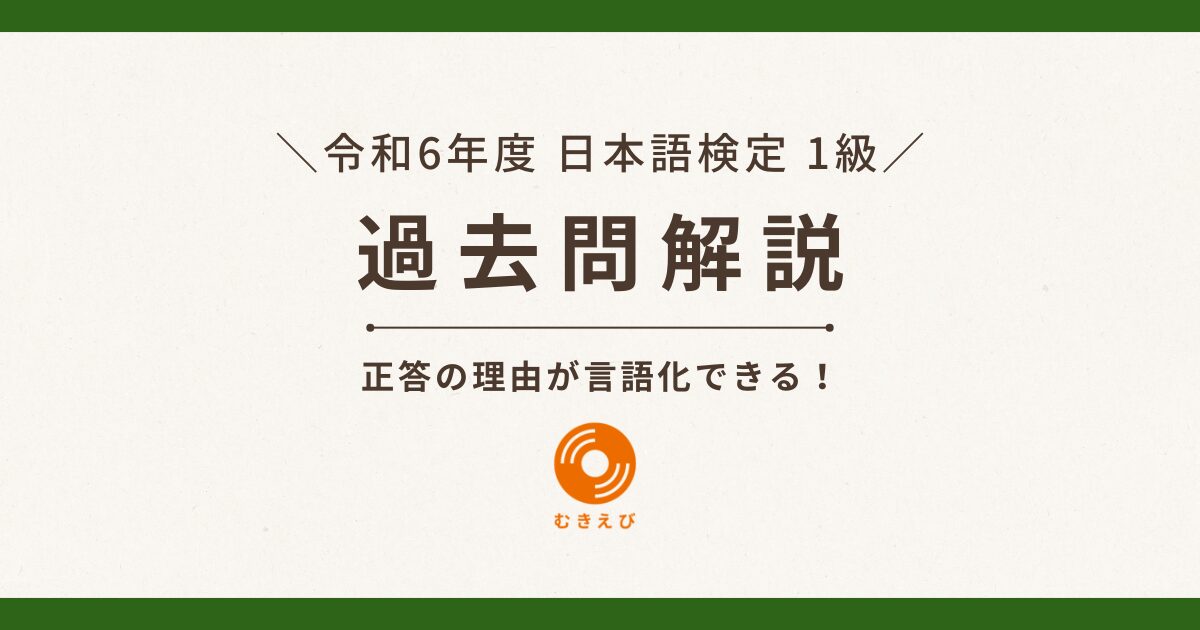著作権の関係上、問題は掲載していません。
以下をご用意の上で、ご確認ください。
前の問題


問11 言葉の意味
ア


( )の前に
のらりくらりの答弁で
とあるので、
はがゆく、もどかしいこと
を表す3が入ります。
解説 馬耳東風
解説 蟷螂の斧
解説 隔靴掻痒
解説 無味乾燥
イ


( )のあとに
~の議論などそもそも期待はしていないがね
とあるので、「実際には~という議論が行われなかった」ということですね。
剛直で言を曲げないこと
を表す1が入ります。
解説 侃々諤々
解説 喧々囂々
解説 是々非々
解説 喋々喃々
ウ


( )の前に
追及される側は、私は関わっていないだの、知るところではないだの~
とあるので、
後日の証拠となる約束の言葉を採られないように
となる2が入ります。
解説 決め手
解説 言質
解説 論破
解説 煙に巻く
エ


( )の前に
「真摯に対応する」という言葉
( )のあとに
掲げる
とあるので、
「真摯に対応する」という言葉を他に対しての自己の行為・主張などを権威づけるためのものとする
となる3が入ります。
解説 大義名分
解説 座右の銘
解説 錦の御旗
解説 懸河の弁
オ


( )の前に
ここをやり過ごせば
とあるので、
ここをやり過ごせば、国民の関心も薄れていく
となる3が入ります。
解説 暑さ寒さも彼岸まで
解説 去る者は日々に疎し
解説 人の噂も七十五日
解説 コップの中の嵐
次の問題


過去問解説の一覧
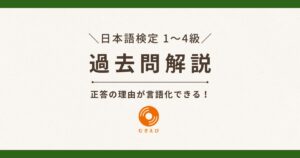
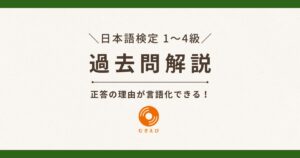
過去問で確認したいこと
特に、
- 敬語
- 文法
の2分野は、「解説を見れば、なんとなくわかるんだけど…」となりやすいのではないかと思います。
過去問を解いたときに、間違えた問題ごとに意識したいのは、
「そもそも知識がなくて解けなかった」
「知ってはいたが、問題になると解けなかった」
のどちらなのかを明確にすることです。
前者であれば、過去問を丁寧に解きながら、1つずつ知識の穴を埋めていきましょう。
- 語彙
- 言葉の意味
- 漢字
のような分野であれば、まとめて暗記していけるのですが、
- 敬語
- 文法
のような分野は、問題の文脈とセットで取り組むのがおススメです。
また、後者であれば、多くの練習問題で知識と問題のギャップをなくしていきましょう。
「わかる→できる」になることで、問題を解くスピードを上げていくことが大切です。
日本語検定は、1級から4級で、
- 語彙・言葉の意味・漢字などの聞かれる範囲が異なる
- 1問1問の難易度が異なる
という違いはあるものの、
- 敬語
- 文法
のような難易度が高い分野で必要な知識に大きな差があるわけではありません。
敬語であれば、
- 尊敬語
- 謙譲語Ⅰ
- 謙譲語Ⅱ
- 丁寧語
- 美化語
の5分類がそれぞれ「どのように定義されているか?」「どのような語が該当するか?」を整理しておきましょう。
その際に、単語を覚えていくのではなく、文章の中で登場人物を確認しながら見ていくのがおススメです。
文法であれば、
- 動詞
- 副詞
- 助詞
などの品詞ごとに、それぞれの語のもつ用法(使い方)を整理しておきましょう。
例えば、
買い物に行くので、8時に駅に集合してください。
には、3つの格助詞「に」がありますが、すべて用法が違います。
買い物に
の格助詞「に」は、「行く」という移動の目的を表しています。
また、
8時に
の格助詞「に」は、時を
駅に
の格助詞「に」は、「集合する」という移動の着点を表していますね。
まとまった参考書・問題集はないので、過去問で出てきた語の用法を1つずつノートなどにまとめていくのがおススメです。
この「日本語検定ナビ」では、分野ごとの練習問題を多数掲載しています。
- 過去問を解いていて、不安が残る分野
- もっと解くスピードを上げたい分野
があれば、ぜひご活用ください。