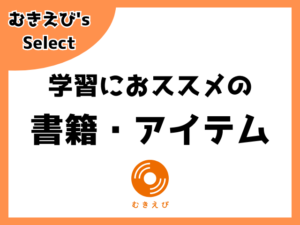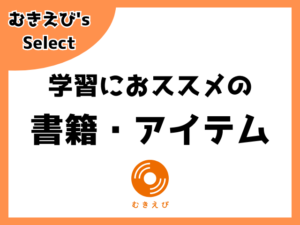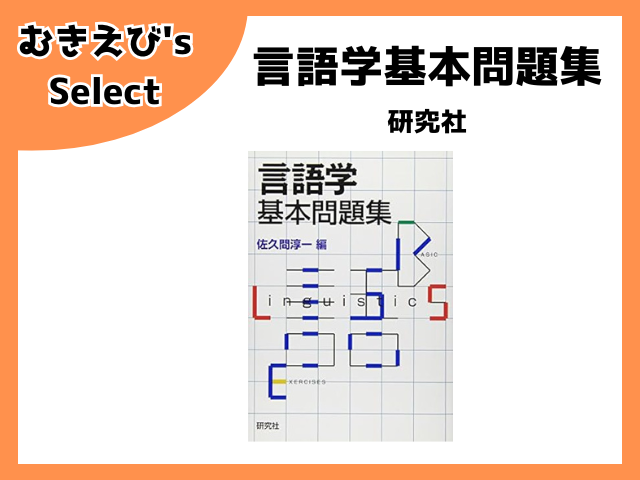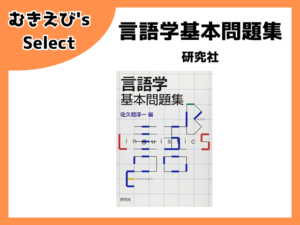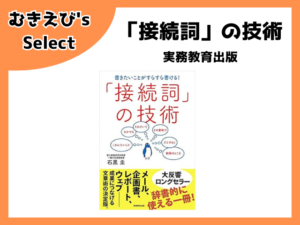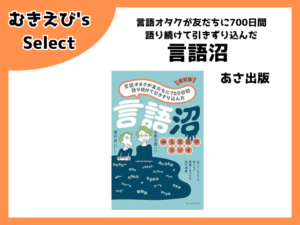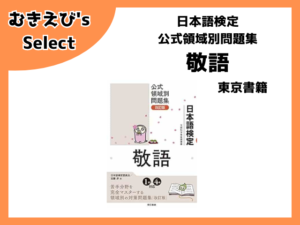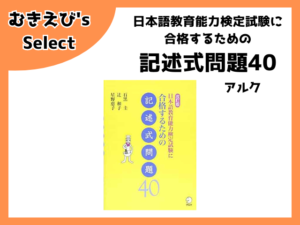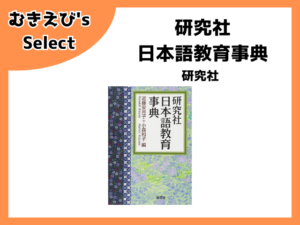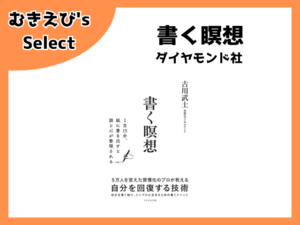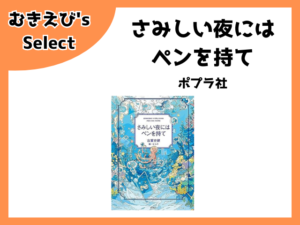今回は、
研究社
『言語学基本問題集』
をご紹介します。
この記事以外にも、おススメの書籍・アイテムについて、記事を作成しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。
おススメの書籍・アイテム
この書籍で学べること
「言語」分野の攻略
日本語教員試験・日本語教育能力検定試験に共通して出題数の多い
- 言語と教育
- 言語
の2分野のうち、「言語」分野の知識を問題形式で確認することができます。
ページの右側に問題があり、左側に解説があるので、ページを行ったり来たりする必要がなく、学習もスムーズです。
| セクション | 出題分野 | 出題数 |
| 1 | 言語の特性・言語学の対象・言語の類型 | 30 |
| 2 | 音声学・音韻論 | 60 |
| 3 | 形態論 | 50 |
| 4 | 統語論 | 50 |
| 5 | 意味論 | 50 |
| 6 | 語用論 | 45 |
| 7 | 言語と社会 | 36 |
| 8 | 言語の変化 | 40 |
| 9 | 文字の体系 | 24 |
と問題集が十分にあるのも、プラスですね。
特に日本語教育能力検定試験でも出題されることが多い
- 音声学・音韻論
- 形態論
- 統語論
- 意味論
- 語用論
に多くのページ数が割かれています。
『言語学入門』とセットで使うのもおススメ
個人的には、日本語学の勉強をこれから始める人向けだと
が1番おススメなのですが、この『言語学基本問題集』と同著者の
も良著です。
『言語学基本問題集』と各項目が対応しているので、2冊セットで使ってみるのも良いですよ (^^)
この1冊で「言語」分野を網羅するのは、厳しい…
「言語」分野の知識を問題形式で確認していくことができますが、この1冊だけで網羅できるわけではありません。
日本語教育能力検定試験向けに日本語学の内容が多めですが、出版年が古いこともあり、この1冊を完璧にしても「言語」分野で満点を取るのは難しそうです。
音声学の部分では、
- 音声記号
- 口腔断面図
などの知識も必要ですし、統語論では
- 格
- 複文
などの各文法分野のより深い知識が必要になってきます。
ただし、だからといって、この『言語学基本問題集』が使えない…というわけではありません。
あくまで「基本問題集」なので、基礎的な部分を固めるにはちょうどよい粒度の問題が並んでいます。
試験対策として使うのであれば、この1冊をなるべく早く終わらせ、日本語教育能力検定試験の過去問などの実際に出題されるレベル感の問題に慣れていくことが必要です。
最後に
この記事以外にも、おススメの書籍・アイテムについて、記事を作成しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。