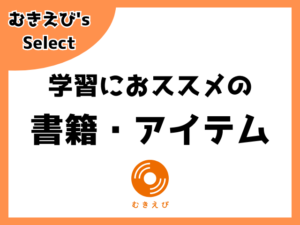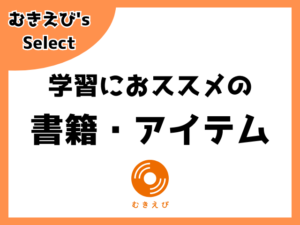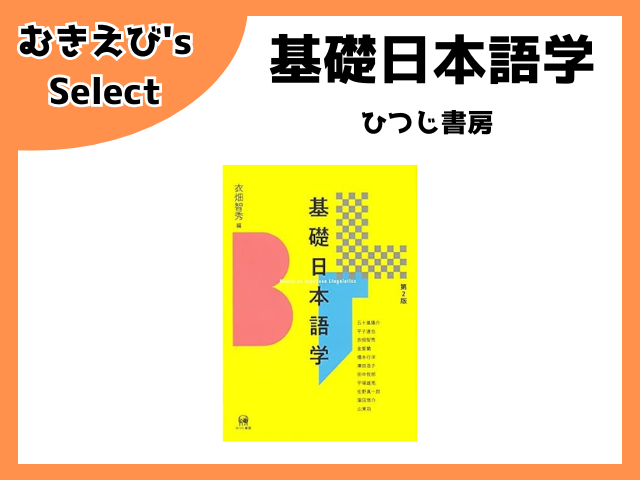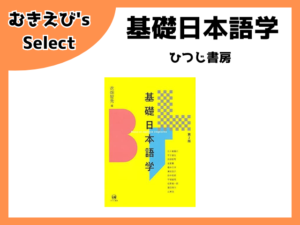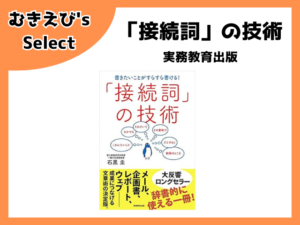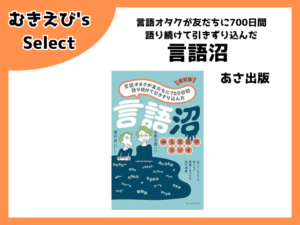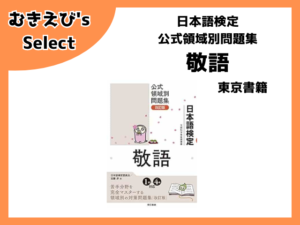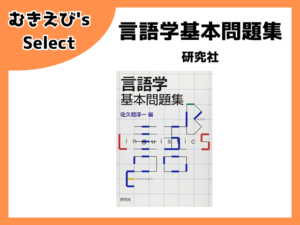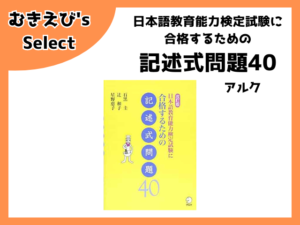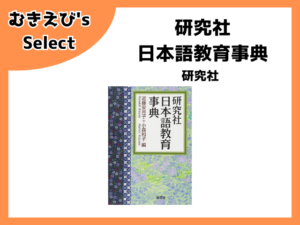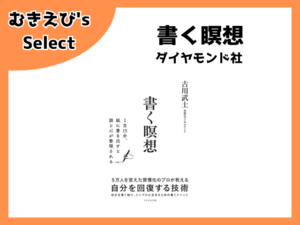今回は、
ひつじ書房
『基礎日本語学』
をご紹介します。
この記事以外にも、おススメの書籍・アイテムについて、記事を作成しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。
おススメの書籍・アイテム
この書籍で学べること
「言語」分野の1冊目におススメ
日本語教員試験・日本語教育能力検定試験に共通した出題範囲である「必須の50項目」を大きく分類したときの
- 地域・文化・社会
- 言語と社会
- 言語と心理
- 言語と教育
- 言語
の中で、学ぶのに時間のかかる「言語」分野の基礎作りにおススメです。
「言語」は、
- 日本語教育能力検定試験において、1番出題数が多い分野
- 日本語教員試験において、「言語と教育」に次いで出題数が多い分野
であり、ココが苦手だと、学習自体が苦痛になりやすい分野だと言えます。
出題範囲も多岐に渡るので、学習初期にしっかりと全体感を掴んでおくことが大切です。
書籍の内容をピックアップ!
『基礎日本語学』の大項目は、以下の通りです。
- 現代日本語の音声と音韻
- 音韻の歴史変化
- 現代日本語の文法
- 文法の歴史変化
- 現代日本語の語彙
- 語と語彙の歴史的変化
- 文章論と談話分析
- 文体差と文体史
- 言葉の変異と諸方言
- コーパスと統計
- 理論的研究とは?
- 日本語学史
特に、
- 日本語教育能力検定試験の試験Ⅱ 問題1~3・6
- 日本語教員試験の応用試験(聴解)
の音声分野は、この『基礎日本語学』の知識だけで十分対応することができます。
章末の「読書案内」が超おススメ
例えば、「文法の歴史変化」の章末では、参考文献とは別の「読書案内」として
の3冊が紹介されています。
試験勉強をしていく中で、
- この分野は、面白いからもっと学びたい!
- 試験勉強としてはこのレベルまでで良いが、もう1歩進んでおくと、将来役に立ちそうだな…
ということもあるかと思います。
そんなときには、各章末で紹介されている「読書案内」の書籍の1冊目にチャレンジしてみるのがおススメです。
近い分野の書籍とは、どう違うの?
同じくらいのレベル感で書かれている書籍に
があります。
私が考えるこの書籍との1番の違いは、日本語教員試験・日本語教育能力検定試験に共通して得点源にしやすい
- 口腔断面図などの調音音声学
- ハ行転呼などの音韻の歴史変化
- 格助詞の接続助詞化
などの分野の解説が充実していることです。
決して『超基礎・日本語教育のための日本語学』がダメ!というわけではありませんが、1冊目として購入するのであれば、ぜひ『基礎日本語学』を検討してみてください。
最後に
この記事以外にも、おススメの書籍・アイテムについて、記事を作成しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。