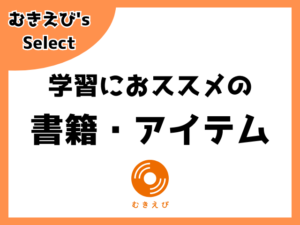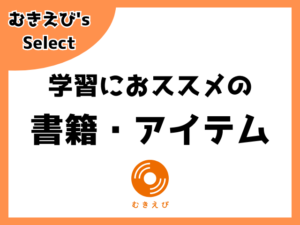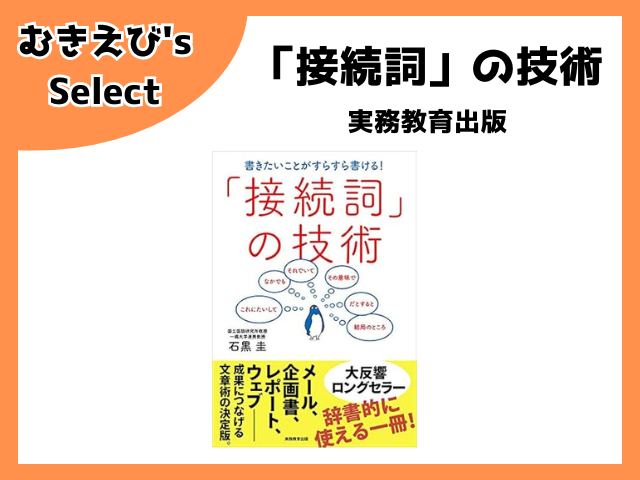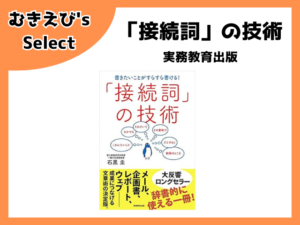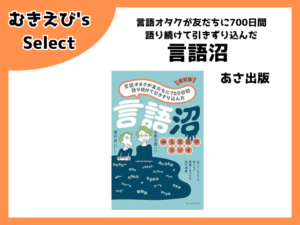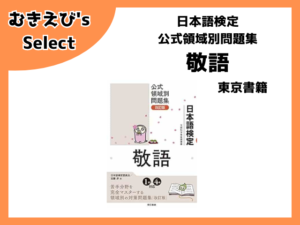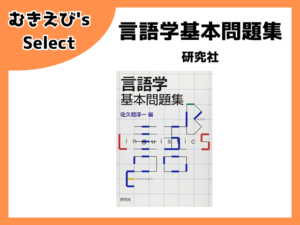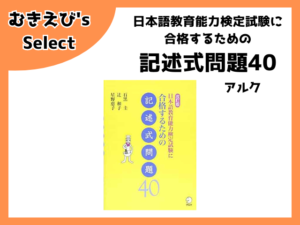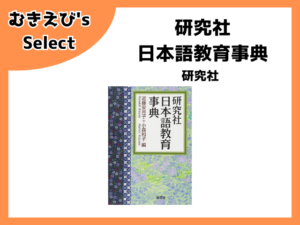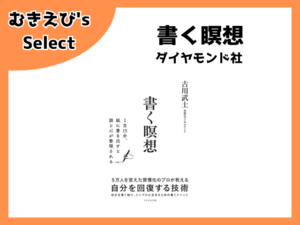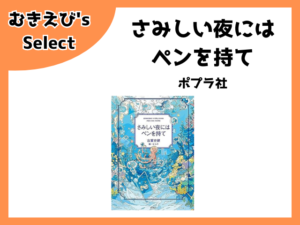今回は、
実務教育出版
『「接続詞」の技術』
をご紹介します。
この記事以外にも、おススメの書籍・アイテムについて、記事を作成しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。
おススメの書籍・アイテム
文章力向上を目指すあなたへ -「接続詞」の技術 を読む
文章を書く際に、
「これにたいして」
「なかでも」
「それでいて」
「その意味で」
「だとすると」
「結局のところ」
といった接続詞は、日々目にしながらもいざ自分で使おうとすると迷ってしまうことがあります。
そうした悩みに応えるのが、石黒圭先生の著書「『接続詞』の技術」です。
「接続詞」は文章の道標
著者は、接続詞が単に言葉をつなぐだけでなく、書き手の発想を広げ、読み手の理解を助ける重要な役割を担っています。
接続詞を適切に使うことで、文章の論理構造が明確になり、伝えたい内容がより正確に、そして効果的に伝わるようになります。
本書では、約340語もの接続詞を取り上げています。
その内容は、接続詞の基本的な役割から始まり、様々な機能を持つ接続詞を分類して解説しています。
具体的には、
予想通りの結果を示す「順接」
予想に反する結果を示す「逆接」
といった論理の接続詞
似たものを並べる「並列」
対照的なものを並べる「対比」
順番に並べる「列挙」
といった整理の接続詞
適切な言葉に言い換える「換言」
例を挙げる「例示」
情報を補う「補足」
といった理解の接続詞
話題を変える「転換」
話をまとめる「結論」
といった展開の接続詞についても詳しく解説されています。
単に接続詞の意味や使い方を解説するだけでなく、文脈との関係性や実践的な活用方法、そして使用上の注意点にも触れています。
例えば、接続詞の「テンプレ」を使ったり、発想を組み合わせたりする方法、さらには自分だけの「オーダーメイドの接続詞」を作る方法まで提案されています。
また、文体レベルへの配慮や、論理の飛躍、牽強付会、不要な接続詞を避けるといった、接続詞を使う上での留意点も解説されています。
企画書や報告書、論文、レポート、ブログ記事など、ビジネスからアカデミック、そして個人の発信まで、幅広い執筆シーンでの活用が想定されていますね。
本書を必要に応じて参照することで、文章力のレベルアップが期待できそうです。
石黒圭先生の著書だと、日本語教育能力検定試験の記述対策における
の本にお世話になった方も多いのではないでしょうか?
文章術の本も多く書かれていて、
なども、新書で読みやすい内容なので、おススメです。
大学生であれば、
は必読書ですし、最近の著書だと
も面白かったですよ (^^)
最後に
この記事以外にも、おススメの書籍・アイテムについて、記事を作成しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。