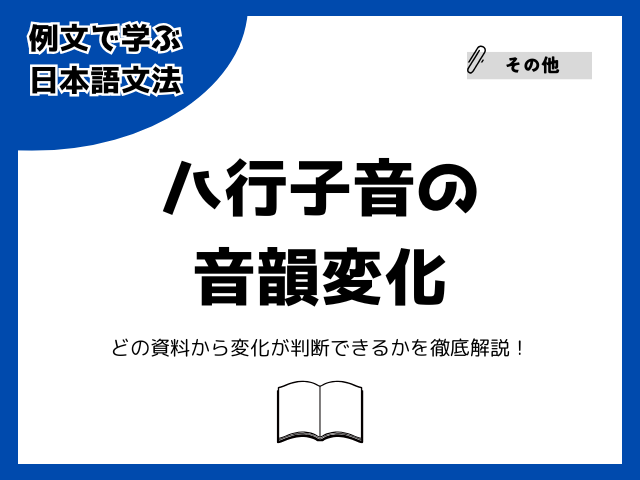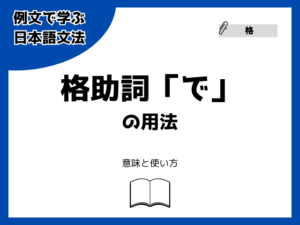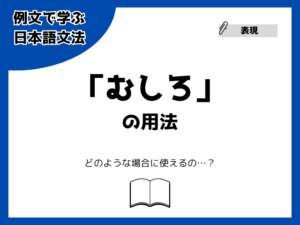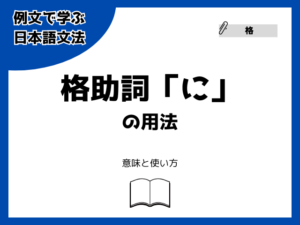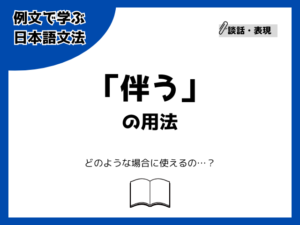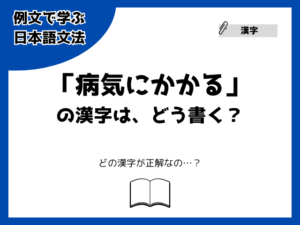今回は、
✅ 現代日本語のハ行子音
✅ ハ行子音の音韻変化
について、一緒に勉強していきましょう。
この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください
例文で学ぶ 日本語文法
現代日本語のハ行子音
現代日本語のハ行子音は、[h][ç][ɸ]
| ハ | ヒ | フ | へ | ホ |
| ha | çi | ɸɯ | he | ho |
カ行の子音の音声記号
[k] 無声軟口蓋破裂音
と声帯振動の有無で対立するのが
ガ行の子音の音声記号
[ɡ] 有声軟口蓋破裂音
であり
タ・テ・トの子音の音声記号
[t] 無声歯茎破裂音
と声帯振動の有無で対立するのが
ダ・デ・ドの子音の音声記号
[d] 有声歯茎破裂音
であるのに、
バ行の子音の音声記号
[b] 有声両唇破裂音
と声帯振動の有無で対立するのが、ハ行ではなく
パ行の子音の音声記号
[p] 無声両唇破裂音
であることに疑問をもったことはありませんか?
これには、ハ行の子音の音韻変化が関係しています。
ハ行の子音の音韻変化
語頭のハ行音の音韻変化
これは、万葉仮名において、ハ行音を表すのに使われている漢字が [p] 無声両唇破裂音 を子音としてもつものばかりだったからです。
現代日本語における「フ」の子音の音と同じですね。
橋本(1950)では、奈良時代にすでにハ行子音が [ɸ] 無声両唇摩擦音 であったとしています。
これは、858年の『在唐記』を根拠としていますが、さまざまな解釈があり、どのタイミングで[p]から[ɸ]に変化したかは、まだ議論の余地があります。
語頭のハ行子音は、鎌倉・室町時代まで [ɸ] 無声両唇摩擦音 であったと考えられています。
これは、1492年の朝鮮板『伊呂波』で当時誕生したばかりのハングルにおいて、ハ行子音に対して両唇摩擦音または、両唇接近音を表すとされる文字が使われているからです。
現代日本語におけるハ行音は、
| ハ | ヒ | フ | へ | ホ |
| ha | çi | ɸɯ | he | ho |
であり、「フ」の音だけ
[ɸ] 無声両唇摩擦音
のように、唇音性が残っていますが
ハ・へ・ホの子音の音声記号
[h] 無声声門摩擦音
ヒの子音の音声記号
[ç] 無声硬口蓋摩擦音
のように、唇音性が失われています。
この唇音性が失われたことがわかるのが、の唇音性が失われたことがわかるのが、1695年の『蜆縮凉鼓集(けんしゅくりょうこしゅう)』です。
「新撰音韻之図」という五十音図が掲載されており、これまでマ行音ともに「唇音」とされてきたハ行音が唇音性を失ったことが示唆されています。
参考書籍
今回は、
✅ 現代日本語のハ行子音
✅ ハ行子音の音韻変化
について、解説してきました。
を主に参考にしています。
さらに詳しく勉強したい方は、ぜひ手に入れてみてください。
また、この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、ブックマークしてご確認ください。