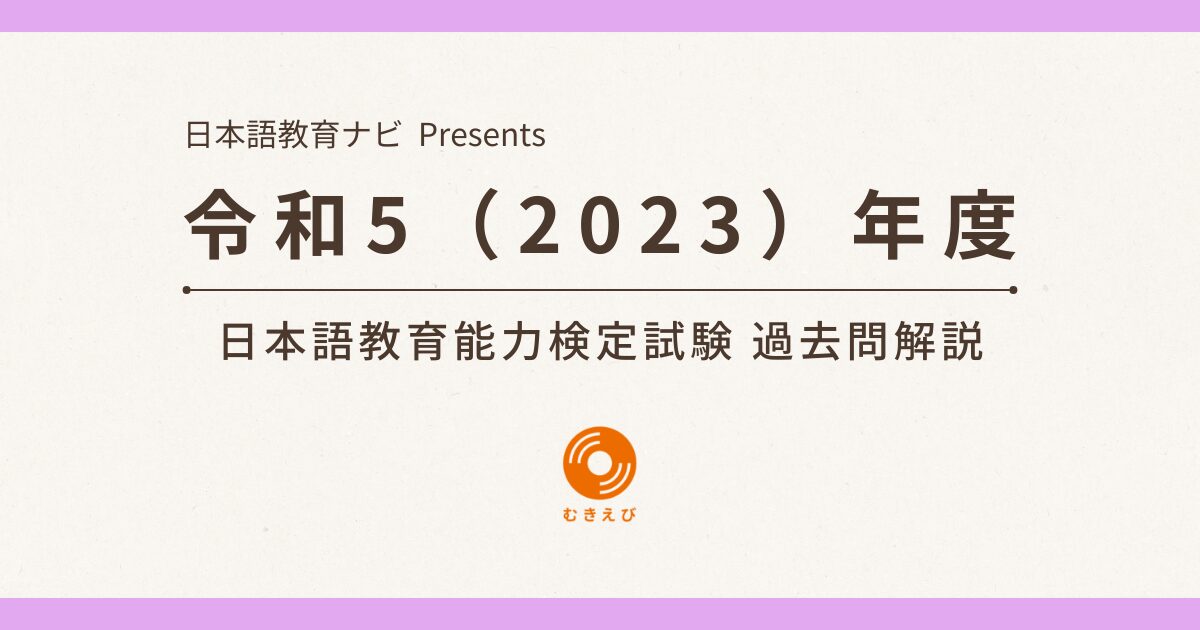令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題7
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 ブレンディッド・ラーニング(Blended Learning)
解説 ブレンディッド・ラーニング(Blended Learning)
「eラーニングで基礎を学んでから、集合研修でアウトプットする」という場面でよく出てきますが、オンライン+オフラインに限った用語ではありません。
「eラーニングで基礎を学んでから、オンラインプラットフォームで会話練習する」のようなオンライン+オンライン・「参考書で独習してから、講座に通う」のようなオフライン+オフラインの場合でも、複数の学習方法を組み合わせたものであれば、「ブレンディッド・ラーニング」です。
eラーニングは、自分のペースで進められるが、質問ができない…
集合研修は、質問はしやすいが、個々の理解は確認しにくい…
といった各学習方法のメリットを活かしつつ、デメリットを他でカバーすることで、学習効果を高めていくことができます。
その答えになる理由


複数の学習方法を組み合わせているものを探してみましょう。
1で使われているのは、オンライン教材のみですね。
これは、ブレンディッド・ラーニングではありません。
2で使われているのは、オンライン授業のみですね。
これは、ブレンディッド・ラーニングではありません。
3で使われているのは、インターネットのみですね。
これは、ブレンディッド・ラーニングではありません。
4で使われているのは、オンライン学習と対面学習の2つですね。
これが、ブレンディッド・ラーニングです。
4が正解です。
問2 非同期型オンライン授業のメリット
その答えになる理由


「同期」とは、作動を時間的に一致させることです。
アカウントをPCとスマートフォンで同期させると、PCで変更した箇所がリアルタイムでスマートフォンでも反映されますね。
教室での講義のようなオフライン授業は、すべて同期型です。
目の前での講師の説明をリアルタイムで聞くことができます。
オンライン授業のメリットの1つが「非同期型」の授業も可能であることです。
教室内で講師の説明を聞くのと同じように「同期型」でリアルタイムの授業を受けることもできれば、録画したあるものを好きな時間で視聴する「非同期型」にすることもできます。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
教師が学習者の活動・思考プロセスの情報を得られるのは、「同期型」の授業のメリットです。
ただし、「同期型」であってもこれらの情報をどれくらい得られるかには形式による制限があります。
「同期型」オフライン授業の場合は、クラスの規模の影響を受けます。
少人数クラスであれば十分可能ですが、対100名の講義だと得られる情報は少なくなりますね。
「同期型」オフライン授業の場合は、情報が双方向かどうかによります。
教師と生徒が双方向にやり取りできるのであれば可能ですが、リアルタイムで授業風景が配信されているだけで生徒の映像が出ていない場合は難しいですね。
「非同期型」オンライン授業のメリットではないので、1は間違いです。
「同期型」オンライン授業の場合は、決まった時間にPCやスマートフォンの前にいなければなりません。
「非同期型」オンライン授業であれば、録画してあるものを視聴する形なので、学習者は好きな時間に開始することも・途中まで見て続きは明日ということも可能です。
「非同期型」オンライン授業では、学習者が時間に縛られない学習環境を確保することができますね。
「非同期型」オンライン授業のメリットなので、2が正解です。
「非同期型」オンライン授業のデメリットは、情報が双方向ではないので、リアルタイムでの質問対応ができないことです。
「非同期型」のメリットである「時間に縛られないこと」の裏返しですね。
「非同期型」オンライン授業のメリットではないので、3は間違いです。
ドリルのような練習問題は、
・ オンライン or オフライン
・ 同期型or非同期型
に関係なく提示可能です。
学習項目が定着しやすい順番にできるかは、授業形式ではなく、授業を組み立てる講師の腕の見せ所ですね。
「非同期型」オンライン授業のメリットではないので、4は間違いです。
問3 ハイフレックス型授業
解説 ハイフレックス型授業
・同期型オフライン授業
13:00~教室で講義を受ける
・同期型オンライン授業
13:00~教室で行われている講義をPCで視聴する
・非同期型オンライン授業
13:00~教室で行われた講義の録画を好きな時間にPCで視聴する
コロナ禍で、学習塾界隈でも増えてきた形態ですね。
運営側は負担が大きいのですが、学習者側にはメリットが多い内容だと思います。
その答えになる理由


3が「ハイフレックス授業」の内容そのままですね。
これが正解です。
問4 適切なメディアを選択する際の留意点
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
アラサーの私が大学生のころでも、PCは持っているがプリンタはないので大学で印刷する…という人はちらほらいました。
最近だと、PCも持っておらずスマートフォンだけ…ということもあるそうですね。
学習者の多くがスマートフォンしか持っていない場合、文字が小さ過ぎたり・改行が少なかったりすると効率的に学習を進めていくことが難しそうです。
メディアが学習者の学習環境に合っているかの精査がないと、ICT化によるデメリットの方が大きくなってしまいます。
1は、「適切なメディアを選択する」際の留意点として適当です。
学習者からの質問内容をストックして共有できるようにしておきたい場合、WEB掲示板のような情報が時系列で流れてしまうものよりも、カテゴリが設定できたり・複数の検索が可能だったりする方が使いやすいですよね。
メディアが教育の目的・学習方法に合っていないと、せっかくシステムを入れたのに使われない…ということにもなりかねません。
2は、「適切なメディアを選択する」際の留意点として適当です。
アニメを授業の題材にする場合、「これ来週までに配信で見てきてね」だと学習者側に金銭的な負担が掛かってしまいますね。
また、どんなに良いシステムであっても、維持コストが膨大であったり・システム管理者をできる人がいない場合は運営側都合で導入が難しい場合もあります。
メディアを使用する際の諸条件がクリアできないと、学習者側・運営側の負担が大きくなってしまいますね。
3は、「適切なメディアを選択する」際の留意点として適当です。
日本だとTwitter(新:X)のシェアが多いのですが、海外で1番使われているSNSはFacebookです。
教育効果も大切ですが、やはり最優先は学習者のニーズですね。
4は、「適切なメディアを選択する」際の留意点として不適当です。
問5 著作権
解説 学校における教育活動と著作権
参考はこちら
大学に限らずですが、学校等の教育機関で著作物を利用する場合で著作権者へ了解(許諾)を得る必要がないのは、以下の4パターンです。
① 学校の授業における複製またはインターネット配信(第35条)
② 試験問題としての複製(第36条)
③ レポート作成などでの「引用」(第32条)
④ 文化祭、部活動などでの上演等(第38条第1項)
その答えになる理由


大学の授業での「著作権の侵害にならない例」なので、
① 学校の授業における複製またはインターネット配信(第35条)
に当てはまるものを探していきましょう。
リンクの4Pに、著作権者への了解(許諾)を得る必要がある例(無許可だと著作権侵害になる例)として
画集から多くの作品をスキャンしてクラウド・サーバにアップロードし、教員間で共有する
令和5年度改訂版 学校における教育活動と著作権
文化庁著作権課
の記載があります。
「授業用に録画したニュース番組」も同じ扱いのため、著作権者の了解(許諾)が必要ですね。
1は、著作権の侵害に当たります。
著作権は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の2つに分かれています。
選択肢1・3・4は「著作権(財産権)」の内容ですが、選択肢2だけ「著作者人格権」の内容ですね。
「著作者人格権」のうちの1つに、「同一性保持権(第20条第1項)」があります。
これは「自分の著作物の内容や題号(タイトル)を自分の意に反して改変されない権利」のことで、ざっくり言うと「勝手に修正されない権利」のことです。
個人ブログからダウンロードした写真やイラストを「そのまま」大学の授業で使うのであれば、著作権者の了解(許諾)は必要ありません。
今回は「一部に修正を加え」とあるので、アウトですね。
2は、著作権の侵害に当たります。
リンクの3Pに、著作権者への了解(許諾)必要がない例(著作権侵害にならない例)として
新聞の記事や写真をコピーした授業用のプレゼン資料を作成し、クラスに配布する。
令和5年度改訂版 学校における教育活動と著作権
文化庁著作権課
の記載があります。
「ウェブ上の教育利用のためのコンテンツ」も同じ扱いのため、著作権者の了解(許諾)は不要ですね。
3は、著作権の侵害に当たりません。
リンクの4Pに、著作権者への了解(許諾)を得る必要がある例(無許可だと著作権侵害になる例)として
算数のドリルを児童生徒に購入させず、コピーして配布する。
令和5年度改訂版 学校における教育活動と著作権
算数のドリルを児童生徒に購入させず、スキャンしてクラウド・サーバにアップロードし利用させる。
文化庁著作権課
の記載があります。
「大学が購入した教科書」も同じ扱いのため、著作権者の了解(許諾)が必要ですね。
4は、著作権の侵害に当たります。
3が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら