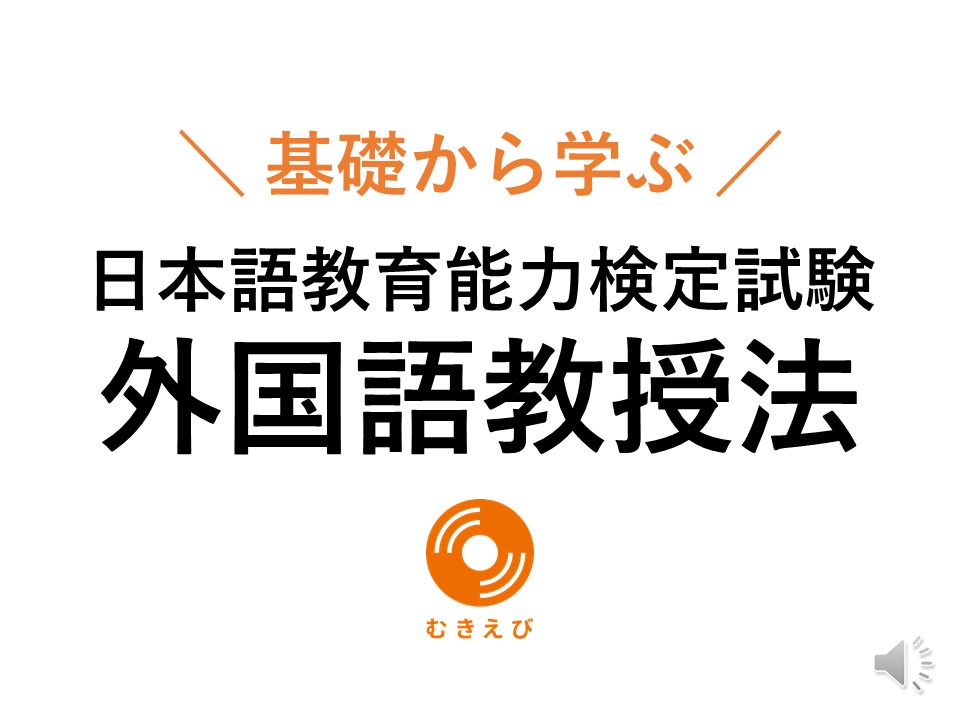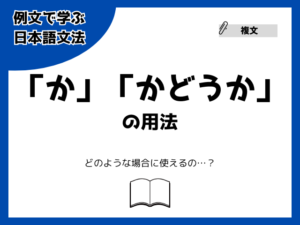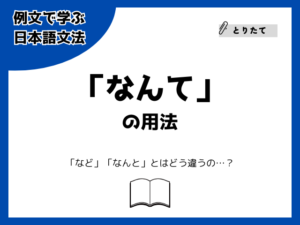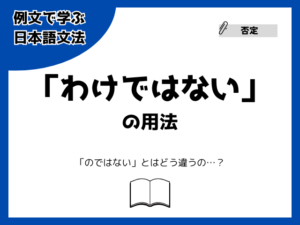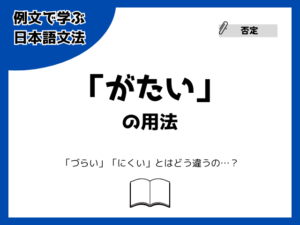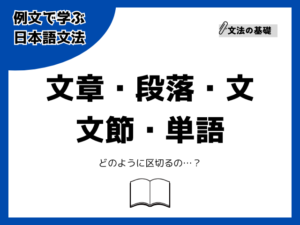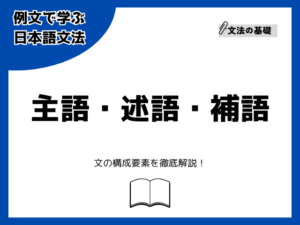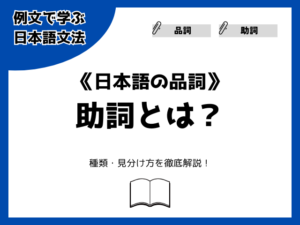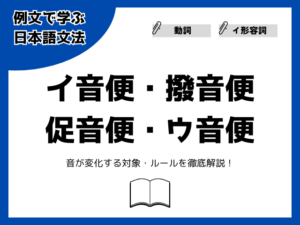流れの全体観を確認してから、内容を見ていきましょう。
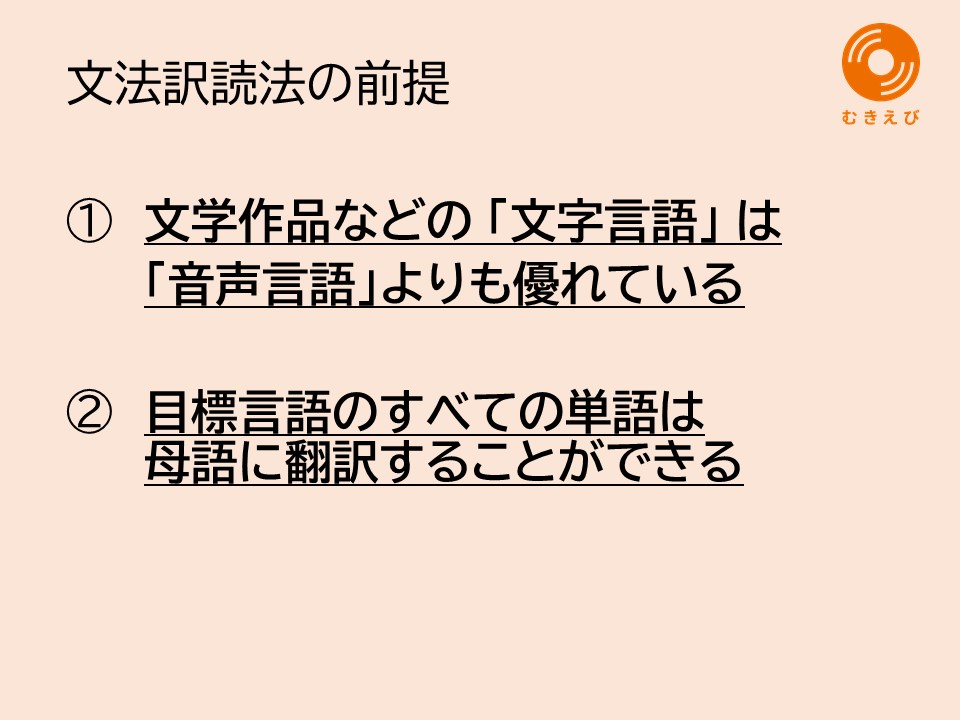

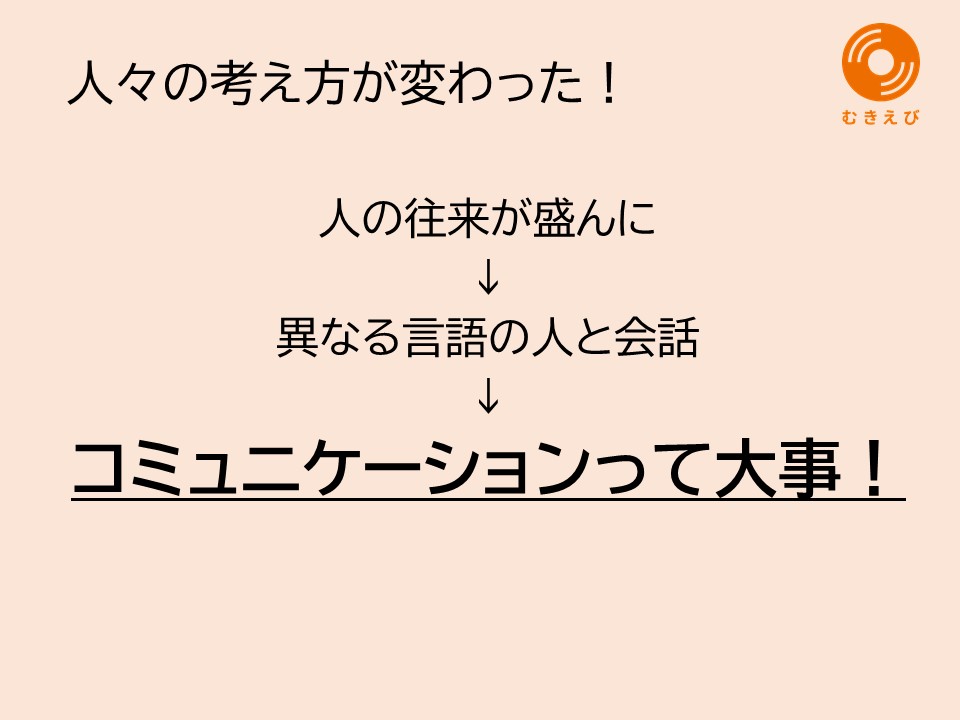
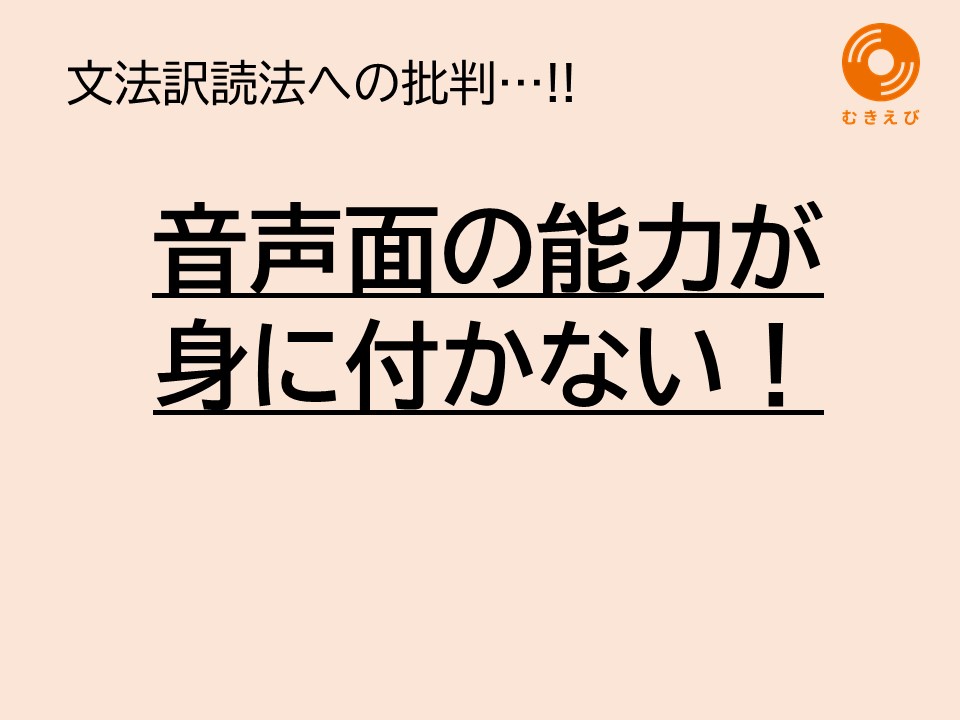
19世紀半ばまでは「文法訳読法」の一強時代
歴史の流れを確認しながら、「文法訳読法」がどのような教授法だったか確認していきましょう。
ヨーロッパで、グラマー・スクールによる教育が始まったのが16世紀ごろだと言われています。
世界史で16世紀と言えば、ルネサンスと宗教改革ですね。
地動説が発表されるなど、新しい世界観が生まれていった時代です。
(日本は室町時代後期なので、内戦の続く戦国時代でした。)
当時のヨーロッパにおける外国語教授法は、「文法訳読法」と呼ばれるものでした。
英語だと「Grammar Translation Method」、略して「GTM」とも呼ばれます。
(「文法翻訳法」「対訳法」という名称で記載されていることもあります。)
「外国語教授法」といっても最初から様々な言語におけるものだったわけではなく、伝統的に行われていた「ラテン語教育」からスタートしたものです。
16世紀当時は、エリートである宗教家や学者の共通言語が「ラテン語」であり、ラテン語の文献を読んだり、ラテン語での聖職者の演説を聞き取れることがエリートの一員となるための条件だったからです。
…とはいえ、「ラテン語」の天下がずっと続いていたわけではありません。
16世紀当時のグラマー・スクールで行われていたラテン語の授業では、「文学作品や聖書の翻訳による理解」が行われていました。
参考書などで語られる「文法訳読法」は、この時代に注目したものが多いですね。
● 文法規則の説明
● 対訳による単語の理解
● 翻訳による内容理解
といった指導を中心に行っていました。
「辞書を使って翻訳し、読解力をつける」ことが目的です。
時代が進み、18世紀半ばから19世紀半ば頃です。
産業革命の影響で鉄道網が整備され、次第に人の往来が盛んになりました。
(日本は江戸時代中期から後期なので、田沼意次や寛政の改革の頃です。)
この頃になると、ヨーロッパの共通語はラテン語だけでなく、英語・ドイツ語・フランス語などが取り入れられていきます。
それに伴い、ラテン語教育の立ち位置も、翻訳による文書作成といった実用的なものから、文学作品の理解・鑑賞といった教養的なものに移っていきました。
人の往来が盛んになったことで、異なる言語を話す人とのコミュニケーションが増え、外国語学習を必要とするのが限られたエリートたちだけではなくなったのです。
ここで、ようやく「文法訳読法」以外の教授法が台頭してきます。
後に「直接法」と呼ばれる「ナチュラル・メソッド」の登場です。
「ナチュラル・メソッド」については、次回の記事でご案内します。
ここまでの「文法訳読法」について整理しておきましょう。
「10分以内で内容を把握できること」を目標としているので、本記事はここまでとします。
次回は、「文法訳読法」への批判から生まれた「ナチュラル・メソッド」について一緒に取り組みましょう。
次の記事はこちら