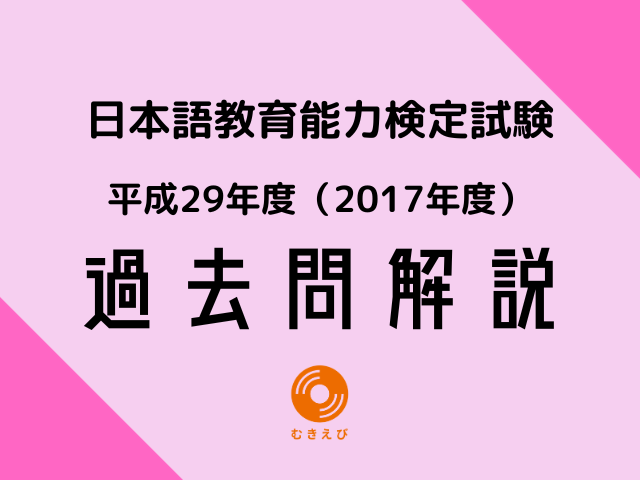平成29年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題12
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 公用語
解説 公用語
「公用語」とは、国家がその使用を公的に認めている言語のことです。
公文書などの公的な業務で使用されます。
1つの国につき1言語…というわけではなく、カナダのように英語とフランス語の2言語を公用語としている場合もあります。
令和3年度試験では「公用語」の前提となる言語計画が、令和元年度試験では各国の公用語が何かが設問になっています。
その答えになる理由


1が「公用語」の説明そのままですね。
これが正解です。
問2 現代仮名遣いで採用されている表記の例
その答えになる理由


これは解説不要ですね。
1が正解です。
問3 当用漢字表
その答えになる理由


参考はこちら
3が正解です。
問4 訓令式ローマ字
解説 ヘボン式ローマ字
「ヘボン式ローマ字」は、ヘボンが日本最初の和英辞典である「和英語林集成」を表すときに考案したローマ字の綴り方です。
「し・ち・ふ・しゃ」を「shi・chi・fu・sha」と表します。
解説 日本式ローマ字
「日本式ローマ字」は、1985年に田中館愛橘(たなかだて あいきつ)が考案したローマ字の綴り方です。
五十音図に基づいて子音と母音を組み合わせるのが基本となっており、「し・ち・ふ・しゃ」を「si・ti・hu・sya」と表します。
後述する「訓令式」との違いは、「ぢ・づ・を」を「di・du・wo」と表すことと、合拗音である「kwa」などがあることです。
解説 訓令式ローマ字
「訓令式ローマ字」は1937年にローマ字の綴り方を定める目的で考案されました。
日本式に準拠して作成されましたが、「じ・ず」「ぢ・づ」が音としては同じであることから、どちらも「zi・zu」としている点などが異なります。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「つき」を「tuki」とするのは、訓令式または日本式のローマ字表記です。
1が正解です。
「ふね」を「fune」とするのは、ヘボン式のローマ字表記です。
2は間違いです。
「はし」を「hashi」とするのは、ヘボン式のローマ字表記です。
3は間違いです。
「じゃま」を「jama」とするのは、ヘボン式のローマ字表記です。
4は間違いです。
問5 送り仮名の指導
その答えになる理由


参考はこちら
通則7より、「申込」は特定の領域の語で慣用が固定していると認められるものとされています。
修正は必要ないため、1は間違いです。
通則2より、「終る」は読み間違えるおそれがなく活用語尾以外の部分について送り仮名を省くことができるとされています。
修正は必要ないため、2は間違いです。
通則2より、「向かう」を「向う」とするのは誤りです。
修正が必要なため、3が正解です。
通則2より、「当り」は読み間違えるおそれがなく活用語尾以外の部分について送り仮名を省くことができるとされています。
修正は必要ないため、4は間違いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら