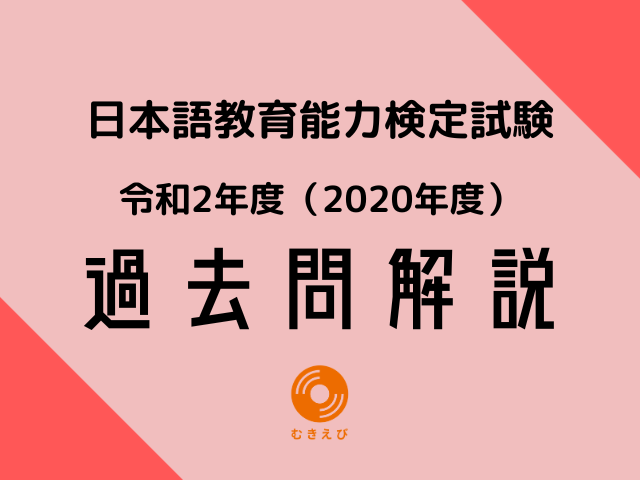令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題15
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 アイヌ語
解説 形態的類型論による言語分類
形態的類型論では、言語を
- 膠着語
- 屈折語
- 孤立語
に分類しており、各内容は以下の通りです。
なお、近年では、この3つの分類に加えて、第4の類型として
- 抱合語
を加えられる場合もあります。
解説 膠着語
英語の「play→plaed」
などが該当します。
身近な言語だと、日本語や韓国語が膠着語に分類されます。
解説 屈折語
英語の「eat→ate」
などが該当します。
身近な言語だと、ロシア語やドイツ語が屈折語に分類されます。
解説 孤立語
英語の「put→put→put」
などが該当します。
身近な言語だと、中国語やベトナム語などが孤立語に分類されます。
解説 抱合語
身近な言語だと、アイヌ語が抱合語に分類されます。
その答えになる理由


アイヌ語は、抱合語に分類されますが、語順は日本語と変わりません。
2が正解です。
問2 アイヌ民族支援法
解説 アイヌ民族支援法
その答えになる理由


サービス問題ですね…‼
アイヌ民族支援法の内容を知らなくても解くことができます。
公用語とは公文書などで使われる国家がその使用を公的に認めている言語のことです。
日本では法律で公用語自体を定めていないため、アイヌ語が公用語だという明記はありません。
3が正解です。
問3 ヤマトグチ
解説 ヤマトグチ
ヤマトグチは、漢字だと「大和口」と書きます。
いわゆる標準語のことです。
解説 ピジン
解説 クレオール
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
基本的に、方言は隣接する地域と近しくなります。
1は、間違いです。
第二次世界大戦後、沖縄では、ウチナーヤマトグチ(沖縄大和口)という方言が確立されていきました。
沖縄の住民が標準語を受容していった結果できた方言で、文法は標準語とほぼ同じで、アクセントや語彙に特徴があります。
2が正解です。
歴史の授業からわかるように、文書資料が残っていないということはありません。
3は、間違いです。
現在の沖縄方言が英語の影響で生じたクレールであれば、英語由来の言葉が残っているはずですね。
4は、間違いです。
問4 消滅の危機にある言語・方言に対する保存・継承のための様々な取り組み
解説 アーカイブ
解説 方言札
これは、方言撲滅運動と呼ばれる活動の1つです。
特に沖縄県では、強く推し進められ、標準語の使用を強制させる方言矯正教育が行われていました。
その答えになる理由


方言札の内容を知っているか・知らないかですね。
方言札は、方言を禁ずるためのものであり、方言使用を推奨するためのものではありません。
4が正解です。
問5 手話
その答えになる理由


手話は、平成25年度試験以来の出題です。
久しぶりですね。
ディスレクシア(dyslexia)とは、文字の読み書きに限定した困難さを持つ疾患のことです。
ろう者は関係ないですね。
1は、間違いです。
言語が異なるように、手話も国によって異なります。
2は、間違いです。
日本では、公的場面での手話通訳が行われることが多いものの、義務にまではなっていません。
3は、間違いです。
日本手話は、ろう者同士の交流から生まれており、日本語と同じ言語体系にはなっていません。
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら