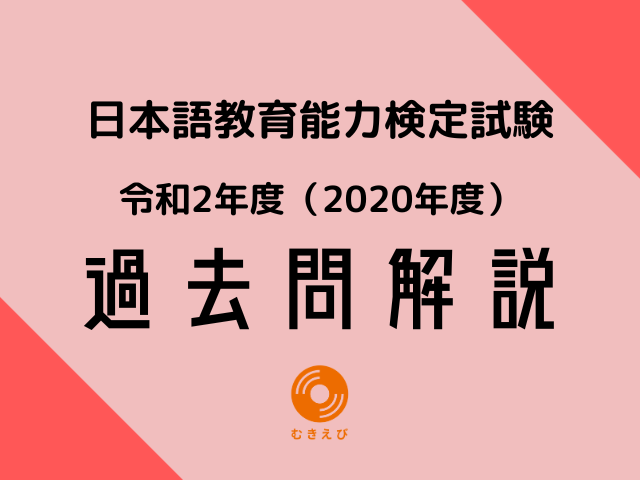令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題12
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 文脈指示
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
あの日のこと、覚えている?
のように、ア形指示詞は、話し手と聞き手が共通する情報を示します。
1が正解です。
「私」は話し手のことですが、話題に関する情報共有の有無とは関係ありません。
2は、間違いです。
すっかり秋だな。
のように、詠嘆の終助詞「な」が加えられていますが、話題に関する情報共有の有無とは関係ありません。
3は、間違いです。
聞き手は「誰」に当たる人物がわかっていますが、話し手はわかっておらず、情報共有がされていません。
4は、間違いです。
問2
その答えになる理由


下線部にある本来の聞き手以外の参加者がいるかがポイントです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の聞き手は、住民のみですね。
本来の聞き手以外の参加者はいません。
2の聞き手は、インタビューしている人ですが、背景に地元の聴衆がいますね。
本来の聞き手以外の参加者がいるため、これが正解です。
3の聞き手は、保護者・地域住民のみですね。
本来の聞き手以外の参加者はいません。
4の聞き手は、面接官のみですね。
本来の聞き手以外の参加者はいません。
問3 「って」
その答えになる理由


「って」の用法の中で、引用と反問の用法が問題になっています。
先生が自習しておいてって。
であれば、
先生が「自習しておいて」って。
のように、「 」でくくったり、
先生が自習しておいてって言ってたよ。
のように、「言った / 言っていた」などに繋げることができるのが引用の用法です。
一方、反問の用法は、
「レポートは、金曜日までだよね?」
「違うよ」
のように、相手の質問に直接答えるのではなく、
「レポートは、金曜日までだよね?」
「金曜日ではなく、水曜日だって」
のように、問い返して答えるもののことです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、
○ 「晴れる」って言ってたよ。
のように、「 」でくくったり、「言った」を繋げることができます。
これは、引用の用法です。
2は、
○ 「先に帰る」って言ってたよ。
のように、「 」でくくったり、「言った」を繋げることができます。
これは、引用の用法です。
3は、
× 「ない」って言ってたよ。
のように、「 」でくくったり、「言った」を繋げることができないですね。
これは、反問の用法です。
4は、
○ 「再来月に来るんだ」って言ってたよ。
のように、、「 」でくくったり、「言った」を繋げることができます。
これは、引用の用法です。
1・2・4が引用・3が反問の用法ですね。
3が正解です。
問4 非優先応答
解説 隣接ペア
およよう → おはよう
明日、何か予定がある? → 何もないよ
解説 優先応答・非優先応答
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「問い – 返答」は、相手の期待にもっとも応えられる隣接ペアですね。
1は、優先応答の例です。
「申し出 – 受諾」は、相手の期待にもっとも応えられる隣接ペアですね。
2は、優先応答の例です。
相手が期待しているのは、「苦情 – 弁明」ではなく、「苦情 – 謝罪」ですね。
3は、非優先応答の例です。
「要請 – 許可」は、相手の期待にもっとも応えられる隣接ペアですね。
3は、優先応答の例です。
問5 口頭のパフォーマンス・テスト
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
タスクの場面の説明をしないと、想定していた問答にならず、適切な評価ができないことがあります。
1は、間違いです。
評価方法を学習者に伝えた方が、何をすれば良いかが明確になり、緊張感や不安感を和らげることができます。
2は、間違いです。
ロールプレイの目的が果たせれば、モデル会話通りでなくても問題ありません。
3は、間違いです。
4は、何も問題ありません。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら