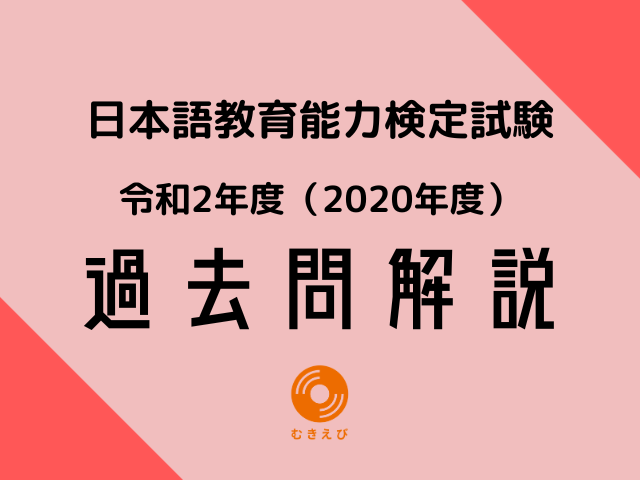令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題11
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 内発的動機づけ
解説 内発的動機づけ
興味がある
おもしろい
などが、例として挙げられます。
解説 外発的動機づけ
ほめられたい
お金が欲しい
などが、例として挙げられます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、必須科目の単位を取ることが動機づけになっていますね。
これは、外発的動機づけの内容です。
2は、知識を増やすこと・教養を高めることが動機づけになっていますね。
これは、内発的動機づけの内容です。
3は、今よりも待遇のよい仕事に就くことが動機づけになっていますね。
これは、外発的動機づけの内容です。
4は、奨学金に応募することが動機づけになっていますね。
これは、外発的動機づけの内容です。
問2
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
学習者の誤りを訂正していくことは大切なのですが、細かく1つ1つに対応していくと、学習者のモチベーションを削いでしまうことにもなりかねないですね。
1は、学習者の動機づけを維持するための有効な指導実践とは言えません。
タスクや活動を学習者が今できることから1歩進んだものにすることで、学習者のモチベーションを高めることができます。
2は、学習者の動機づけを維持するための有効な指導実践の1つです。
肯定的な自己イメージ・明確な学習目標のようなゴール設定により、学習者自身がどのようにしていけば良いかを考えることに繋がります。
3は、学習者の動機づけを維持するための有効な指導実践の1つです。
適宜褒める・励ますなどの声掛けをすることで、学習者が自信を失うのを避けることができます。
4は、学習者の動機づけを維持するための有効な指導実践の1つです。
問3 ビリーフ
解説 ビリーフ
教師側のビリーフと学習者側のビリーフがあり、両者が一致していればプラスな影響、異なっていればマイナスな影響を受けます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
学習者の言語習得における考え方が変わることで、習熟度が大きく伸びたり、逆に伸び悩んでしまったりすることは多々ありますね。
学習者のビリーフの変容と学習スキルの習熟度は、密接に関係していると言えます。
1は、適当な内容です。
母国で文法中心に学んでいた学習者がコミュニケーション中心の授業を受けたときに、想定よりも上手くいかないことがあります。
これは、母国での教育内容が学習方法の好みに影響していることが一つの要因になっていると言えそうですね。
2は、適当な内容です。
学習者のビリーフは、授業を受ける前から変わらないこともあれば、授業を受けて変化していくこともあります。
授業活動の影響を受けずに独立して形成されるとは限らないですね。
3は、不適当な内容です。
ビリーフは「考え方・信念」なので、必ずしも学習行動と一致するわけではありません。
4は、適当な内容です。
問4 言語適性
解説 言語適性
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
外向的・内向的が言語習得に影響を与えることはありますが、どちらが最終的な言語能力の高さに有利…というわけではありません。
1は、間違いです。
音を語のまとまりとして認識し再生する能力は、言語適性(センス)によるものであり、習得の初期段階で有利に働きます。
2が正解です。
相手や状況に合わせて言葉選びができる能力は、言語適性(センス)ではなく、言語能力(訓練)の影響を受けます。
3は、間違いです。
指導方法が学習者の特性に合えば効果はプラスになり、合わなければマイナスになります。
4は、間違いです。
問5 オートノミー
解説 オートノミー
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
目標設定をして、それを達成するための学習活動を自分で考えさせることで自律性が育ちます。
1が正解です。
教師が自身の教育経験のみから学習法を指定するのでは、学習者の自律性は育ちません。
2は、間違いです。
教師が独習用のテキストを決めるのでは、学習者の自律性は育ちません。
3は、間違いです。
この選択肢が間違いやすいですね。
一見正解のようなのですが、教師が授業をするのは、自律学習ではありません。
4は、間違いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら