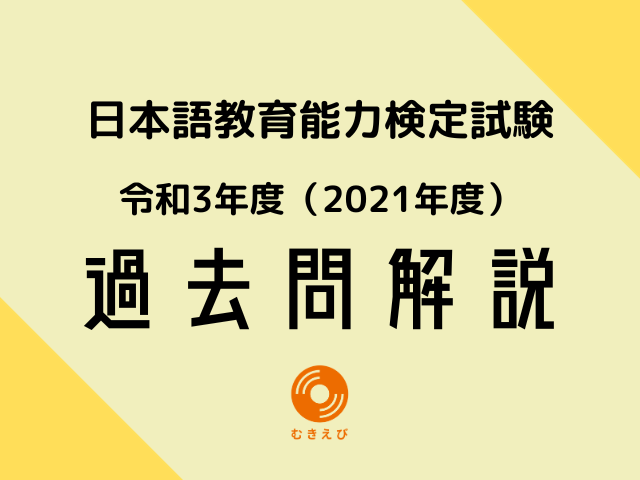令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題13
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 交話的機能
解説 ヤコブソンによるコミュニケーション機能の6分類
解説 指事的機能
彼が私の兄です。
などが該当します。
解説 情動的機能
感嘆詞
などが該当します。
解説 能動的機能
依頼
命令
禁止
などが該当します。
解説 交話的機能
挨拶
相づち
などが該当します。
解説 詩的機能
しりとり
シャレ
早口言葉
俳句
などが該当します。
解説 メタ言語的機能
その答えになる理由


「交話的機能」とは、挨拶・相づちなど、他者との関係を維持・構築するコミュニケーションの機能のことですね。
1が正解です。
問2 ラポート・トーク
解説 ラポート・トーク
ラポート・トークの対義語は、「リポート・トーク」です。
情報のみを淡々と伝える話し方を指します。
その答えになる理由


2が「ラポート・トーク」の内容そのままですね。
これが正解です。
問3 発語内行為
解説 発話行為理論
発話行為を
- 発語行為
- 発語内行為
- 発語媒介行為
の3段階に分けて説明しています。
解説 発語行為
「ひったくりだ!」
解説 発語内行為
「ひったくりの犯人を捕まえてほしい」という意図が聞いた人に伝わる
解説 発語媒介行為
聞いた人が「ひったくりを捕まえる」という行動をする
その答えになる理由


4が「発語内行為」の説明そのままですね。
これが正解です。
問4 スピーチレベルシフト
解説 スピーチレベルシフト
その答えになる理由


3が「スピーチレベルシフト」の説明そのままですね。
これが正解です。
問5 疑問文を用いたストラテジー
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、「普通、そんな言い方をする人はいない」という反語になっています。
非難の感情を表しているので、間違いではありません。
2は、「彼は緊張していたのかもしれない」という意図を相手に伝えようとしています。
情報提供として機能しているので、間違いではありません。
3は、発言が意図そのままですね。
話し手の主張を強調しているので、間違いではありません。
4は「誰にもこんなことができるはずがない」という反語になっています。
情報要求を表しているわけではないので、これが間違いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら