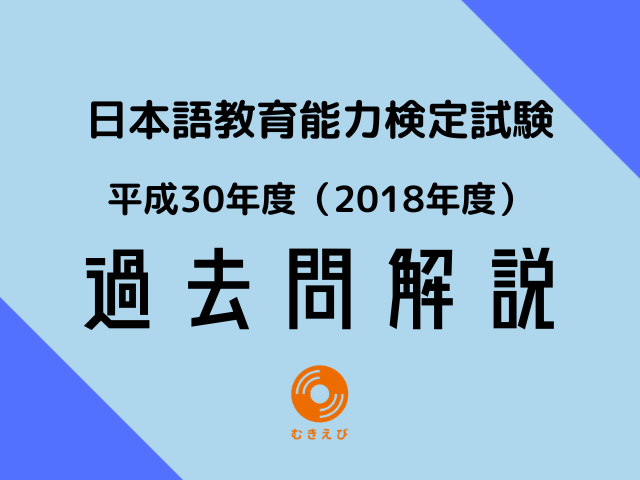平成30年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題6
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 JF日本語教育スタンダード
解説 JF日本語教育スタンダード
「JF日本語教育スタンダード」とは、国際交流基金が作成した日本語の教え方や、学習に対する評価の仕方の基準となるツールのことです。
どの言語にもあてはまる言語能力の測定基準を設定したCEFRの考え方に基づいており、 各レベルでの言語活動をCan-do評価の形式で例示しています。
それまでの日本語学習の目標は「日本語を母語話者レベルで使えるようにする」でしたが、CEFRの発表以後は、「学習者が目的に応じて何ができるか」の基準で考えられるようになりました。
その答えになる理由


出典元はこちら
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「JF日本語教育スタンダード」は、「Can-do Statements」を提供していますが、母語話者のコミュニケーションスタイルではなく「非母語話者が目標言語におけるコミュニケーションで何ができるか」をモデルにしています。
1は間違いです。
「JF日本語教育スタンダード」 は、授業や学習評価などの言語環境をデザインする際に必要な枠組みの提供のほか、Can-doの形で技能の目安を提供しています。
2が正解です。
「JF日本語教育スタンダード」 は、 A1→A2→B1→B2→C1→C2の順に6つのレベルを設定していますが、日本語能力試験のレベルではなく、CFERの考え方がベースになっています。
3は間違いです。
「JF日本語教育スタンダード」 は、 木の根となる「コミュニケーション言語能力」と木の枝として表現される「コミュニケーション言語活動」の関係を整理して「JFスタンダードの木」を図式化しています。
問2 話し合いのルール
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
ディスカッションでは、話し合いの展開をコントロールするのではなく、学習者同士の自由な意見が出るようにしていった方が良いです。
1は間違いです。
制限時間を意識する必要はありますが、1人当たりの発話の時間配分までのコントロールは必要ありません。
2は間違いです。
想定質問への準備を行ったり、賛成・反対の立場を明確にするのは、ディスカッションではなくディベートの場合です。
3は間違いです。
4は何も問題ありません。
日本語教育に関係なく、大切なことですね。
これが正解です。
問3
その答えになる理由


これは解説不要ですね。
2が正解です。
問4 ディスカッション
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
討論者は自分が観察者に見られていることは意識すべきですが、最優先は議論に集中することです。
1は間違いです。
討論者は主張するだけでなく、他の討論者にも気を配るべきです。
2は間違いです。
3は何も問題ありません。
これが正解です。
討論者の発言などの問題点は、行き過ぎていなければ後からの指摘の方が良いですね。
4は間違いです。
問5
その答えになる理由


これも解説不要ですね。
3が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら