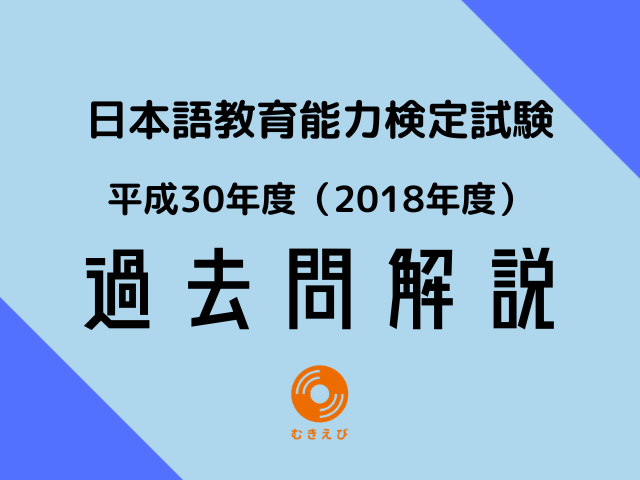平成30年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題8
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 OPI Oral Proficiency Interview
解説 OPI Oral Proficiency Interview
OPIとは、外国語の口頭運用能力を測定するためのインタビュー試験のことです。
ACTFL(American Council on the Teaching of Foreign Languages:米国外国語教育委員会)が開発した試験で、資格を持つテスターが被験者に1対1で最長30分のインタビューを行い、
●総合的タスクと機能
●場面/話題
●正確さ
●テキストの型
の4つの基準により測定します。
判定のレベルは、以下の10段階です。
①初級ー下
②初級ー中
③初級ー上
④中級ー下
⑤中級ー中
⑥中級ー上
⑦上級ー下
⑧上級ー中
⑨上級ー上
➉超級
その答えになる理由


参考はこちら
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「OPI」は汎言語的に使える会話能力テストのため、日本語以外の言語でも同基準の判定が可能です。
1が正解です。
「OPI」では、インタビューにより
●総合的タスクと機能
●場面/話題
●正確さ
●テキストの型
の4つの基準で判定を行います。
2は間違いです。
OPIの判定レベルは、以下の10段階です。
①初級ー下
②初級ー中
③初級ー上
④中級ー下
⑤中級ー中
⑥中級ー上
⑦上級ー下
⑧上級ー中
⑨上級ー上
➉超級
3は間違いです。
「OPI」ではプレゼンテーションは行わず、インタビューやロールプレイで判定されます。
4は間違いです。
問2 ロールプレイ
解説 ロールプレイ
「ロールプレイ」とは、会話の目的・状況等を設定し、与えられた役割に沿って会話を進める練習のことです。
●与えられた状況に限定して会話をする
●役割だけ与えて、自由に会話させる
など、学習者のレベルに応じて様々なやり方を取ることができます。
その答えになる理由


「ロールプレイ」では、基本的に途中で指摘行ったりすることはありません。
あらかじめ決めておいた内容を終えてから、フィードバックすることが多いです。
1・3・4は間違いです。
2が正解です。
問3 ロールプレイを優先させる目的
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
既習文型の定着度を見るのであれば、ロールプレイよりも表現の練習を行った方が良いです。
1は間違いです。
発話の流暢さを向上させるのであれば、 ロールプレイよりも表現の練習を行った方が良いです。
2は間違いです。
人前の発表場面に慣れさせるのであれば、ロールプレイよりも表現の練習を行った方が良いです。
3は間違いです。
ロールプレイを表現の練習よりも優先させることで、学習者自身が何をどこまでできるのかを自覚しやすくなります。
4が正解です。
問4 ロールプレイの難易度
その答えになる理由


参考はこちら
上級レベルの話者は、自分に関連した話題のみならず、地域社会、国レベルまたは国際レベルにおいて関心を集めている話題について情報を伝達するために、積極的な姿勢で会話に参加できる。これらの話題は、過去、現在、未来の主要な時制枠における語り(ナレーション)と描写を通して、具体的に扱われる。このレベルの話者は、不測の事態を伴う対人交流の場面にも対応することができる。上級レベルにおいては、口語的段落が発話のタイプと長さの基準であるが、このレベルの発話は、質・量ともに非常に豊富である 。上級レベルの話者は、非母語話者の発話に不慣れな者を含む母語話者に理解されるに十分な基本文法構造と一般的な語彙を習得している。
HomeResources & PublicationsACTFL Proficiency Guidelines 2012Japanese
中級レベルの話者は、主に、日常生活に関連した身近な話題について話しをする際、伝えたいことがらを言語を使って創造する能力によって特徴づけられる。このレベルの話者は、自分自身が意図した考え、伝達したいことを表現するために、習ったことを組み替えることができる。中級レベルの話者は、簡単な質問ができ、簡単な生活場面に対応することができる。単文や連文などの文レベルの談話を発し、それらは現在時制で行なわれることが多い。中級レベルの話者は、非母語学習者の応対に慣れた話し相手に理解してもらうことができる。
HomeResources & PublicationsACTFL Proficiency Guidelines 2012Japanese
上級と中級の境目は「相手が慣れた人か」「口語レベルの語彙・文法能力があるか」にありそうです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1・2は、相手が慣れた人ではなく、交渉内容も複雑なため「上級」に当たりそうです。
3は、スピーチなので相手は関係ありませんが、恩師に対しての待遇表現が必要になるため同じく「上級」に当たると考えられます。
4は、相手は話し慣れた友人で、交渉内容もシンプルです。
これが「中級」に当たりそうですね。
4が正解です。
問5 タスク先行型の会話指導を行う際の留意点
その答えになる理由


タスク先行型の会話指導を行う目的は、問3の通り「言語能力の限界に気づかせるため」です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
タスク先行型かどうかに関わらず、事前の準備は必要です
1は間違いです。
既習の語と表現だけで完結させてしまっては「言語能力の限界に気づかせる」ことはできません。
2は間違いです。
タスクをこなした上で「言語能力の限界に気づかせる」ことが目的なので、タスク自体が不能になる事態は避けるべきです。
3が正解です。
Yes/No疑問文よりも、WH疑問文の方が難易度が上がり、学習者に「言語能力の限界に気づく」機会を与えやすくなります。
4は間違いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら