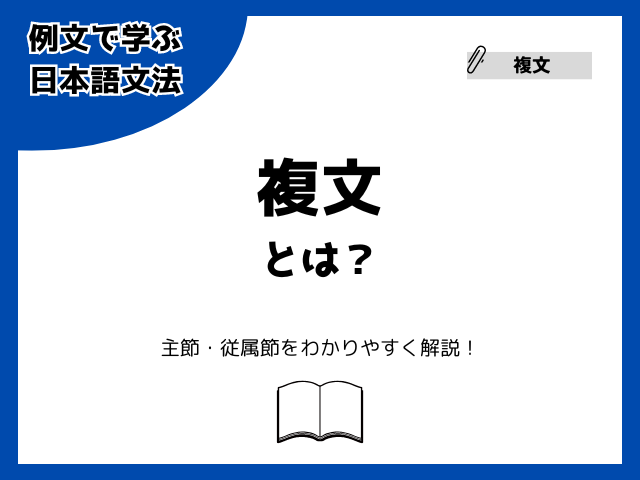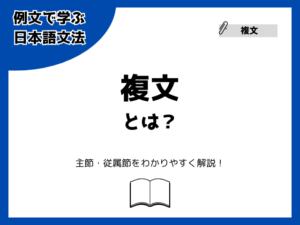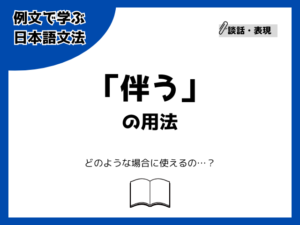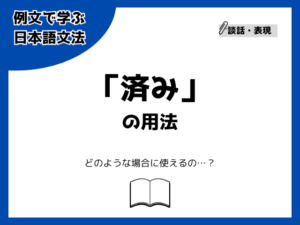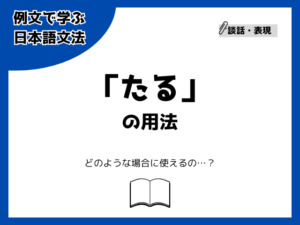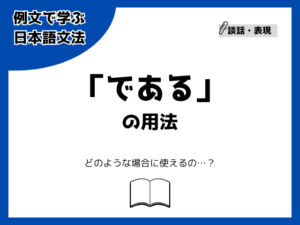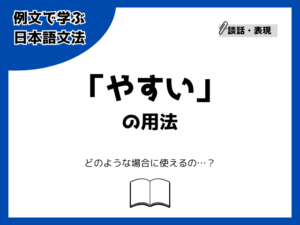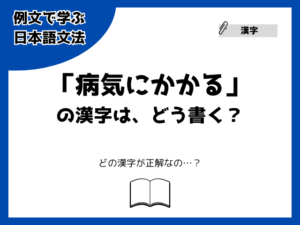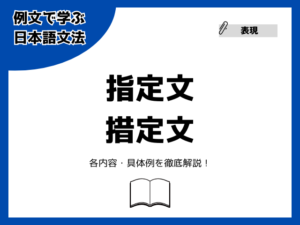今回は、
✅ 「複文」とは?
✅ 「節」とは?
✅ 「主節」「従属節」とは?
について、一緒に勉強していきましょう。
この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。
例文で学ぶ 日本語文法
複文とは?
単文と複文
まずは、「単文」から見ていきましょう。
日本語で述語にくるのは、
- 動詞
- イ形容詞
- ナ形容詞
- 名詞
の4つです。
【動詞文】
中華料理を食べた。
【イ形容詞文】
そなたは美しい。
【ナ形容詞文】
窓からの景色がきれいだ。
【名詞文】
こちらの女性が彼の妹だ。
これらの文は、すべて述語が1つですね。
このように、述語が1つの文を「単文」と言います。
それでは、次の文はどうでしょうか?
Aさんが作った中華料理を食べた。
「食べた」「作った」の2つの述語が存在していますね。
これのように、述語を2つ以上もつ文を「複文」と言います。
複文に該当しない例
Aさんが本を読んでいる。
- 読む
- いる
という2つの動詞が含まれているので、「これは、複文だ!」となるかもしれませんが、この文は単文です。
「読んでいる」の「いる」は、補助動詞なので、「読んでいる」で1語ですね。
そのため、この文は
- 読んでいる
という1つの述語をもつ単文であることがわかります。
赤いカバンが置いてある。
も同じく単文です。
- 置く
- ある
という2つの動詞が含まれていますが、「ある」が補助動詞なので、「置いてある」で1語です。
また、「赤い」というイ形容詞も含まれていますが、これは名詞を修飾する用法であり、述語として使われているわけっではありません。
そのため、この文は、
- 置いてある
という1つの述語をもつ単文であることがわかります。
このように、述語が複数含まれるものが「複文」・1つだけのものが「単文」です。
節とは?
Aさんが作った中華料理を食べた。
には、「食べた」「作った」の2つの述語が存在しています。
これらの述語を中心とした文のひとまとまりを見てみると、
- Aさんが作った
- 中華料理を食べた
ですね。
上の例文は、2つの節をもった複文です。
主節・従属節とは?
Aさんが作った中華料理を食べた。
には、
- 作った
- 食べた
の2つの述語があり、これらの述語を中心としたひとまとまりとして
- Aさんが作った
- 中華料理を食べた
という2つの節があります。
この2つの節のうち、どちらがメインかを考えてみると………
- Aさんが作った … サブ
- 中華料理を食べた … メイン
ですね。
「Aさんが作った」は、どのような中華料理だったかを説明する役割をしています。
このように、複数ある節のうち、メインとなるものが「主節」・サブとなるものが「従属節」です。
「主節」「従属節」について、もう少し例文で見ていきましょう。
私は、彼が犯人だと知っている。
この文の述語は、
- 知っている
- 犯人だ
ですね。
これらの述語が中心となる節は、
- 私は~と知っている
- 彼が犯人だ
です。
これらの節のうち、メインとなるものは「私は知っている」ですね。
この文の主節は「私は~と知っている」・従属節は「彼が犯人だ」です。
勉強しているときに、電話がかかってきた。
この文の述語は、
- 勉強している
- かかってきた
ですね。
これらの述語が中心となる節は、
- 勉強しているときに
- 電話がかかってきた
です。
これらの節のうち、メインとなるものは「電話がかかってきた」ですね。
この文の主節は「電話がかかってきた」・従属節は「勉強しているときに」です。
彼は就職し、私は進学した。
この文の述語は、
- 就職し
- 進学した
ですね。
これらの述語が中心となる節は、
- 彼は就職し
- 私は進学した
です。
これらの節のうち、メインとなるものは「私は進学した」ですね。
この文の主節は「私は進学した」・従属節は「彼は就職し」です。
この例文は、これまでの例文と比べて、メイン・サブの関係が曖昧に感じるのではないかと思います。
これは、複文というカテゴリの中でも、主節に対する従属節の「従属度」が異なるからです。
「従属度」については、以降の記事にて説明していきますが、今の時点では
彼は就職し、私は進学した。
のように、それぞれが単文に近い場合は従属度が低く、メイン・サブの関係が曖昧になる…と理解しておきましょう。
参考書籍
この記事では
✅ 「複文」とはどのような文のことか?
✅ 「節」とは?
✅ 「主節」「従属節」とは?
について、解説してきました。
を主に参考にしています。
さらに詳しく勉強したい方は、ぜひ手に入れてみてください。
また、この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、ブックマークしてご確認ください。


次の記事はこちら