
令和元年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題1
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
(1) 円唇性
日本語教育能力検定試験のトップバッターの問題は、例年「音声記号」です。
これは、私が過去問を持っている「平成26年度試験」から変更ありません。
試験Ⅰ 問題1は、【 】に示した観点から見て他と性質の異なるものを選ぶ問題です。
(1)であれば、今回の【調音点】以外にも、子音では【調音法】・母音では【唇のまるめ】などが出題されています。
まずは、用語の確認からしていきましょう。
解説 調音点
声道で鼻腔への通路を開閉したり、舌や唇を動かしたりして、声道の形などを変え様々な言語音をつくることを「調音」と言います。
● 両唇
● 歯茎
● 硬口蓋
などの調音を行う器官が調音点です。
解説 調音法
関連する用語も合わせて整理してしまいましょう。
呼気を妨害して子音を調音するときの方法を「調音法」と言います。
日本語の子音は
① 声帯振動の有無 (無声音・有声音)
② 調音点 (どこで)
③ 調音法 (どのように)
の3点の組み合わせで音が決まります。
解説 円唇母音
母音を唇の形で分類したときに、唇の両端が突き出され唇全体が丸まる母音を「円唇母音」と言います。
その答えになる理由


1 [a] あ 非円唇低母音
2 [i] い 非円唇前舌高母音
3 [ɯ] う 非円唇後舌高母音
4 [e] え 非円唇前舌中母音
5 [o] お 円唇後舌中母音
となり、5だけ円唇母音です。
(2) 撥音の音声
解説 撥音の音声記号
撥音の音は、次に続く音によって決まります。
●後続音が ない … [ɴ]
●後続音が アサワハヤ行 … 鼻母音 ⇒ 暗記:「朝は早」
●後続音が 上記以外 … 次の音の調音点
両唇 … [m] (後続が パ・バ・マ行)
歯茎 … [n] (後続が ラ行 イ段以外のタ・ダ・ナ・ザ行)
歯茎硬口蓋 … [ɲ] (後続が チ・ジ・ニ)
軟口蓋 … [ŋ] (後続が カ・ガ行)
その答えになる理由


「ん」の後ろを見てみると、
●後続音あり
●後続音がアサワハヤ行以外
なので、後続音の調音点で音が決まります。
1 かんたく [t] 歯茎
2 かんつう [ʦ] 歯茎
3 かんち [ʨ] 歯茎硬口蓋
4 かんとう [t] 歯茎
5 かんてい [t] 歯茎
となり、3が正解です。
(3) 拍数の変化
その答えになる理由


「書き表したとき」と「読み上げたとき」で拍数が変化するものがないかを見ていきましょう。
1 げつかすい → げっかあすい
(下線部は、1拍→2拍に変化)
2 げつすいきん → げっすいきん
(下線部は、2拍→2拍のまま)
3 かすいもく → かあすいもく
(下線部は、2拍→2拍のまま)
4 かもくど → かあもくど
(下線部は、2拍→2拍のまま)
5 きんどにち → きんどうにち
(下線部は、2拍→2拍のまま)
1だけ「1拍→2拍」に変化しています。
(4)読み方のバリエーション
その答えになる理由


1 きゅうさい
2 きゅうにん・くにん
3 きゅうこ
4 きゅうほん
5 きゅうかい
2だけ、読み方が2種類あります。
(5) 語形成
解説 語形成
「語形成」とは、語の組み立て方や結び付き方に注目した分類のことです。
その答えになる理由


1 耳に当てるもの
2 下に敷くもの
3 台を拭くもの
4 膝に掛けるもの
5 前に書くもの
3だけ前部の名詞が「ヲ格」・その他は前部の名詞が「ニ格」です。
「ヲ格」「ニ格」と書くとなんだか小難しく見えてしまいますが、
・名詞にどの格助詞がついて
・名詞と述語との間にどのような意味関係が成り立つか?
という文法用語として覚えておきましょう。
上記の選択肢であれば…
・1、2、4、5には格助詞「に」がついて
・格助詞がついた名詞は、述語の動作をする【場所】を表しています。
・3には格助詞「を」がついて
・格助詞がついた名詞は、述語の動作をする【対象】を表しています。
1は、「当てる」という動作をする【場所】が「耳」
2は、「敷く」という動作をする【場所】が「下」
3は、「拭く」という動作をする【対象】が「台」
4は、「掛ける」という動作をする【場所】が「膝」
5は、「書く」という動作をする【場所】が「前」
(6) 転成名詞の意味
解説 転成名詞
「転成」とは、既存の語の品詞を変えて、別の品詞として新しい語を作る方法のことです。
・動詞「話す」の連用形 → 名詞「話」
・イ形容詞「近い」の連用形 → 名詞「近く」
・ナ形容動詞「親切だ」の語幹+さ → 名詞「親切さ」
のようにできた名詞を「転成名詞」と言います。
その答えになる理由


転成名詞になる前の状態を見ていきましょう。
1 かばんを持つ
2 所帯を持つ
3 金を持つ
4 心を持つ(?)
5 力を持つ
4だけおかしいですね。
1・2・3・5は動詞「持つ」の元の意味のままですが、4は「心の持ち方」「心の持ち様」といった意味を表しています。
(7) デ格の意味
その答えになる理由


(5)の解説のように、「●格」とは
・名詞にどの格助詞がついて
・名詞と述語との間にどのような意味関係が成り立つか?
を表す文法用語です。
今回の問題であれば、「デ格」となることで名詞と述語の間にどのような意味関係が成り立つかを見ていきます。
「デ格」には、大きく分けて「場所」「手段」「起因・根拠」「主体」「限界」「領域」「目的」「様態」の8つの用法があります。
詳しくは、以下の2つの記事を参考にしてみてください。
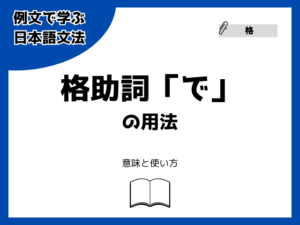
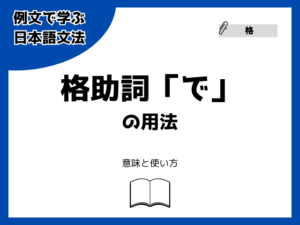
今回は、8つの用法のうち「手段」「起因・根拠」が出題されています。
選択肢を1ずつ見ていきましょう。
1は、「休む」という動作をする【起因・根拠】が「はしか」
2は、「送る」という動作をするときの【手段】が「メール」
3は、「話す」という動作をするときの【手段】が「日本語」
4は、「描く」という動作をするときの【手段】が「遠近法」
5は、「行く」という動作をするときの【手段】が「新幹線」
1だけ【起因・根拠】の用法です。
「●格」の問題は、どの用法かの判断をすることが大切です。
今回の問題であれば、
・1の「で」は「~が原因で」に言い換えられる
・2~5の「で」は「~を使って」に言い換えられる
のように解くこともできますが、これはあくまで「どの用法かを判別するために、言い換えて考えてみる」ということを意識しておきましょう。
(8) 補助動詞
解説 補助動詞
「補助動詞」とは、動詞で、本来の意味と独立性を失って付属的に用いられるものを言います。
窓際に本が置いてある。
窓際に女性が座っている。
その答えになる理由


「本来の意味が失われているか」の観点で見てみましょう。
1は、動詞「みる」の本来の意味が失われ、補助的に用いられているので補助動詞です。
2は、「持つ」「かえる」の2つの動作が同時に行われています。
動詞「かえる」の本来の意味が残っているので、補助動詞ではありません。
3は、動詞「ある」の本来の意味が失われ、補助的に用いられているので補助動詞です。
4は、動詞「しまう」の本来の意味が失われ、補助的に用いられているので補助動詞です。
5は、動詞「くる」の本来の意味が失われ、補助的に用いられているので補助動詞です。
(9) 指定文と措定文
解説 指定文
「指定文」とは、「AはBだ」の形の名詞文において、A=Bの関係にある文のことです。
「私の出身は北海道だ」 → 「北海道は私の出身地だ」
と言い換えることができます。
解説 措定文
「措定文」とは、「AはBだ」の形の名詞文において、AがBの属性に含まれる関係にある文のことです。
「イモリは両生類だ」 → 「両生類はイモリだ(?)」
のように言い換えることができません。
その答えになる理由


「指定文」と「措定文」は、「AはBだ」のAとBを入れ替えて文が成立するかで判別できます。
1 「男の人は私の先生だ(?)」
言い換えられないので「措定文」です。
2 「医師は山田さんだ(?)」
言い換えられないので「措定文」です。
3 「冷淡はあの人だ(?)」
言い換えられないので「措定文」です。
4 「有能は議長だ(?)」
言い換えられないので「措定文」です。
5 「あの人は院長だ」
言い換えられるので「指定文」です。
(10) 直接受身文における動作主の表示形式
解説 直接受身文
「直接受身文」とは、能動文の対象(目的語)が主語となる受身文のことです。
【能動文】彼が、この本を書いた。
【直接受身文】この本は、彼に書かれた。
「彼に」のように、直接受身文にしたときの動作主は「に」で表すのが基本ですが、「によって」「から」「で」で表すことができる場合もあります。
【能動文】彼が、この本を書いた。
【直接受身文】この本は、彼によって書かれた。
【能動文】先生が、私を褒めた。
【直接受身文】私は、先生から褒められた。
【能動文】ツタが、窓を覆っている。
【直接受身文】窓は、ツタで覆われている。
その答えになる理由


例文で考えてみましょう。
1 直接受身文にしたときの動作主の表示形式は「に」「によって」
【能動文】彼が、その理論を生み出した。
【直接受身文】その理論は、彼に生み出された。
【直接受身文】その理論は、彼によって生み出された。
2 直接受身文にしたときの動作主の表示形式は「に」「によって」
【能動文】彼が、その建物を建てた。
【直接受身文】その建物は、彼に建てられた。
【直接受身文】その建物は、彼によって建てられた。
3 直接受身文にしたときの動作主の表示形式は「に」「によって」
【能動文】彼が、その料理を作った。
【受身文】その料理は、彼に作られた。
【直接受身文】その料理は、彼によって作られた。
4 直接受身文にしたときの動作主の表示形式は「に」のみ
【能動文】彼が、その本を見た。
【直接受身文】その本は、彼に見られた。
5 直接受身文にしたときの動作主の表示形式は「に」「によって」
【能動文】彼が、その絵を描いた。
【直接受身文】その絵は、彼に描かれた。
【直接受身文】その絵は、彼によって描かれた。
4のみ、直接受身文における動作主の表示形式が限定されています。
(11) 述語が表す出来事とニ格の関係
その答えになる理由


「述語が表す出来事がいつ行われたか」を見ていきましょう。
1 映画館に行ったのは、発話時から見た「先週末」
2 ドライブをしたのは、発話時から見た「先週末」
3 残業をしたのは、発話時から見た「先週末」
4 ケーキを買ってきたのは、発話時から見た「先週末」
5 レストランを予約したのは、発話時から見た「先週末」または「過去のどこか」
「この前話したレストラン、先週末に電話で予約しておいたよ」のような発話意図であれば、予約したのは「先週末」で、実際に行くのは「これから」
「この前話したレストラン、今週末の日程で予約しておいたよ」のような発話意図であれば、予約したのは「過去のどこか」で、実際に行くのが「今週末」
1~4は述語の出来事が行われたのかが固定されますが、5だけ文脈での判断が必要です。
(12) 「の」の用法
その答えになる理由


この問題では「の」の用法のうち、2つが出てきています。
1つ目は、名詞と名詞を結びつける用法。
「私のカバン」「日本語の本」のように、前の名詞が後ろの名詞に様々な意味を加えます。
2つ目は、名詞修飾節の主語を表す用法。
「私の好きな曲」→「私が好きな曲」のように「が」に言い換えることができます。
1 「が」に言い換えられないので、名詞と名詞を結びつける用法
2 「が」に言い換えられるので、名詞修飾節の主語を表す用法
3 「が」に言い換えられないので、名詞と名詞を結びつける用法
4 「が」に言い換えられないので、名詞と名詞を結びつける用法
5 「が」に言い換えられないので、名詞と名詞を結びつける用法
2が正解です。
(13) 「のだ(んだ)」の方法
その答えになる理由


この問題では「のだ(んだ)」の用法のうち、2つが出てきます。
1つ目は、「発見」の用法。
「『のだ』には●●という用法もあるんだとわかった」
2つ目は、「意志」の用法。
「日本語教育能力検定試験に合格するために、毎日勉強するんだ」
1 発見
2 発見
3 意志
4 発見
5 発見
3が正解です。
(14) 「ところ」の用法
その答えになる理由


選択肢の中で2~5は「ところ」が含まれる節の事態は実際に起きていますが、1だけ「ところ」が含まれる節の事態が実際に起きるかは不明です。
1の「ところで」は逆接の内容になるため、「~ても」に言い換えることができます。
また、2~4の「ところで」「ところに」は時間節の内容になるため、「~とき」に言い換えることができます。
今回の問題では深く聞かれていませんが、節の事態が実際に起きる「ところ」には、大きく
① 補足節
1人で歩いているところを彼に見られた
② アスペクトに関わる助動詞
ちょうど宿題に取りかかったところだ。
③ 時間節
彼に事情を話したところ、すべてを理解してもらうことはできなかった。
の3の用法があります。
「補足節」とは、従属節に「こと」「の」「ところ」などの形式名詞がついて、従属節内が一つの名詞のようになり、主節の述語に対して補足語と同じ働きをする節のことです。
①の例文であれば、「1人で歩いているところを彼に見られた」「1人で歩いているのを彼に見られた」のどちらでも文が成立しますね。
「時間節」とは、主節の動きや状態が成立する時を別の事態との関係によって限定する従属節のことです。
③の例文であれば、「彼に事情を話したところ」「彼に事情を話したとき」のどちらでも文が成立しますね。
また、時間節の用法では、「ところ」のほかに「ところを」「ところが」「ところへ」「ところに」「ところで」の形があり、それぞれ接続の仕方や意味が異なります。
選択肢になっている「ところに」「ところで」を見ていきましょう。
「ところに」は、従属節の事態の発生している状況に別の事態が挿入的に発生することを表しています。
2であれば「先生に質問したい」という状況に「先生が来る」という事態を挿入、5であれば「リラックスしていた」という状況に「電話がかかってくる」という事態の挿入です。
「ところで」は、従属節の事態が一段落して主節の新しい事態が始まることを表しています。
3であれば「仕事」が一段落して「休憩を取る状態」が、4であれば「食事」が一段落して「財布がないことに気づいた状態」が新しく始まりますね。
(15) 「れる・られる」の用法
その答えになる理由


「れる・られる」には4つの用法があります。
● 自発 「吉報が待たれる」
● 尊敬 「お客様が来られた」
● 受身 「彼に殴られた」
● 可能 「いくらでも食べられる」
1 自発
2 自発
3 自発
4 可能
5 自発
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら












