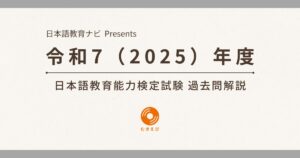令和元年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題3A
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


(1) 日本語の音声
その答えになる理由


日本語の共通語における調音法は、以下の6つです。
● 破裂音
● 摩擦音
● 破擦音
● 鼻音
● 弾き音
● 接近音
4が正解です。
(2) 声門
その答えになる理由


これは難しいですね。
1の「有声音」が合っている…と選べはするのですが、自信を持って他を消せた受験生は少なかったのではないかと思います。
「ささやき声」とは、声帯を振動させずに無声化した声のことです。
振動が伴わないので、2は間違いです。
息を吸うときは、声門が開いていて声帯は振動しません。
声門は閉まっていないので、3は間違いです。
「息もれ音」とは、声門を少し開いた状態で肺から気流を送ることにより、声帯をゆるく振動させる音のことです。
声門は大きく開かず、また声帯は振動しているので、4は間違いです。
(3) 調音
その答えになる理由


日本語の共通語の調音方法に「ふるえ音」はありません。
2が正解です。
1 両唇破裂音は、日本語の共通語におけるパ行・バ行が該当します。
3 硬口蓋接近音は、日本語の共通語におけるヤ行が該当します。
4 声門摩擦音は、日本語の共有後におけるハ・へ・ホが該当します。
(4)
解説 子音の発声
● 声帯振動の有無
● 調音点
● 調音法
で音が決まります。
どこで(調音点)・どのように(調音法)気流を妨げ、その際に声帯は振動しているか?
でどの子音が該当するかを判断します。
解説 母音の発声
● 口腔内での舌の高さ
● 口腔内での舌の前後位置
● 唇の丸め
で音が決まります。
気流を妨げることなく、舌・唇がどのような状態か?
でどの母音が該当するかを判断します。
その答えになる理由


4が正解です。
気流の流れを妨げるのが「子音」、妨げないのが「母音」を説明しています。
1~3のように、「気流を妨げる」のは子音の説明です。
(5) 帯気性
解説 帯気音
「帯気音」とは、破裂音は破擦音のうち「気音」を伴わないもののことです。
「有気音」とも言います。 ⇔ 無気音
解説 気音
「気音」とは、主に無声の破裂音や破擦音が後続する母音に移るときに、声帯振動が遅れることで間に聞こえる[h]のような音のことを言います。
中国語や韓国語では気音の有無によって、語が区別されます。
日本語や欧米の言語では、気音による語の対立はありません。
その答えになる理由


これは難しいですね。
● 中国語と韓国語は、有気音(帯気音)と無気音の対立がある。
● 日本語と英語は、有声音と無声音の対立がある。
までは知っていても、スペイン語・ベトナム語まではカバーできていない受験生の方が多いのではないかと思います。
● スペイン語は、日本語と同様に「有声音」と「無声音」の対立
● ベトナム語は、中国語と同様に「有気音(帯気音)」と「無気音」の対立
なので、3が正解です。
東南アジアの言語の多くはインドの影響を受けている中、ベトナム語は例外的に中国の影響を強く受けている…という背景知識があれば、スペイン語の内容がわからなくても解くことができます。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら