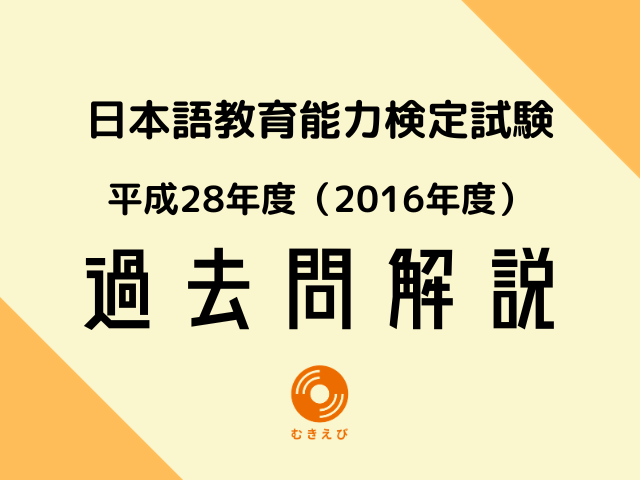平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題8
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 Uカーブ仮説
リスガードが提唱した「Uカーブ仮説」、ガラホーンらが提唱した「W字曲線」は頻出分野です。
用語の意味から確認していきましょう。
問1~問3まで、一気に解説していきますね。


解説 Uカーブ(U字曲線)
「Uカーブ」とはリスガードによって提唱された異文化適応の4つの段階を表した図のことです。
上の図の左半分が該当し、ハネムーン期→ショック期→回復期→安定期と段階を踏んで異文化に適応していくとされています。
解説 ハネムーン期
「ハネムーン期」とは、異文化接触の初期段階における、異文化への高い期待感で希望に満ち溢れている心理状態の時期のことです。
解説 ショック期
「ショック期」とは、異文化接触の興奮状態が収まり現実が見えてきて、期待感→失望感・焦燥感への変わっていく心理状態の時期のことです。
この時期に「カルチャーショック」に陥ることが多いとされています。
解説 回復期
「回復期」とは、一時期の落ち込みから回復し、異文化に適応していく時期のことです。
この時期に「カルチャーショック」から脱出していくとされています。
解説 安定期
「安定期」とは、異文化を受け入れ精神的にも安定してくる時期のことです。
「異文化理解」が進む時期だとされています。
解説 リエントリーショック(逆カルチャーショック)
「リエントリーショック(逆カルチャーショック)」とは、異文化に適応したのちに自分化に戻るときに感じる「異文化に入ったときと同じようなストレス」のことです。
解説 W字曲線
異文化適応の「Uカーブ」と、リエントリーショックからの脱出で起きるUカーブを合わせて、「W字曲線」と言います。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
短期の旅行ではカーブの山と谷を経験するのではなく、多くの場合は「ハネムーン期」のウキウキ感だけ経験します。
1は間違いです。
人によっては谷から脱出できないこともあれば、再びカルチャーショックに陥って山と谷を繰り返すこともあります。
2は間違いです。
3は何も問題ありません。
異文化と自文化の違いが少なければ緩い曲線に、異文化と自文化の違いが多ければ急勾配の曲線になります。
これが正解です。
異文化適応は、年齢・性別だけでなく、これまでの経験などの個人的要因に影響を受けます。
そのため、人によってカルチャーショックを受ける度合いや回復までの時間が異なり、カーブの形も変わってきます。
4は間違いです。
問2 カルチャーショック
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
同じ英語を公用語としている国でも、アメリカとオーストラリアでは文化が違うのでカルチャーショックは起こりえます。
1は間違いです。
カルチャーショックからの回復は、その文化に触れ続けなければ起こりません。
程度の差はあれ経験することなので、避けずに通っていった方が良いですね。
2は間違いです。
カルチャーショックはメンタル的な不調だけでなく、身体的症状にも表れます。
3は間違いです。
4は何も問題ありません。
これが正解です。
問3 リエントリーショック
その答えになる理由


「リエントリーショック」は、左半分のUカーブ(ハネムーン期→ショック期→回復期→安定期)を経験しているがゆえに起こります。
これは、あくまで「自身が異文化に適応した経験」です。
そこで経験したことが「自分化で通じず」に感じるストレスが「リエントリーショック」に当たります。
「異文化適応したことによる価値観」と「改めて自文化に戻ってきたときの価値観」のギャップが「リエントリーショック」なので、ギャップを客観的に見ることができていれば(=自身の価値観の変化に気づいていれば)「リエントリーショック」が起こらないこともあります。
3が正解です。
問4 ストレスを除去したり緩和したりすること
これは、用語の意味を知っているか知らないかですね。。
解説 コーピング
「コーピング」とはメンタルヘルス用語で、ストレス原因の解決や負担を減らすことを目的として、問題に対して何かしらの行動を起こすことです。
休日は仕事のことを忘れるために趣味に打ち込むなどの行動が該当します。
解説 アフォーダンス
「アフォーダンス」とは生態心理学などの用語で、環境のさまざまな要素が人間や動物に影響を与え、感情や動作が生まれることです。
概念なのでイメージがつきづらいですよね。
公園のベンチ → 座る
子ども時代を過ごした家 → なつかしい
のように「環境が、行動や感情に影響すること」自体を「アフォーダンス」と言います。
解説 フィルタリング
「フィルタリング」とは、条件に合致するもの・制限に抵触しないものだけを通過させることです。
子ども用スマホから有害サイトにアクセスできないようにすることなどが該当します。
解説 コンコーダンス
「コンコーダンス」とは、文学作品などの用語索引のことです。
その答えになる理由


下線部は、「コーピング」の内容そのままですね。
1が正解です。
問5 ソーシャルサポート
ソーシャルサポートは、平成30年度試験でも出題されています。
4つに分類されるので、一通り確認しておきましょう。
解説 ソーシャルサポート
「ソーシャルサポート」とは、社会の中で周辺の人から受けることができるサポートのことです。
以下の4つに分類することができます。
● 道具的サポート
● 情緒的サポート
● 情報的サポート
● 評価的サポート
解説 道具的サポート
「道具的サポート」とは、テキストや参考書を支給する等の物質的な援助のことです。
(サービスの提供も、道具的サポートに含まれます。)
解説 情緒的サポート
「情緒的サポート」とは、課題にぶつかったとき等に、感情面での解決で援助を行うことです。
解説 情報的サポート
「情報的サポート」とは、課題解決のために必要な情報やアドバイスを提供することです。
解説 評価的サポート
「評価的サポート」とは、相手に対して肯定的な評価を与えて、相手を励ましていくことです。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
出身国の異なる友人であっても「外国から来た」という共通点があるのえd、ソーシャルサポートが可能です。
1は間違いです。
渡航直後かどうかは、ソーシャルサポートか否かに関係ありません。
むしろ出身国が同じ友人は、渡航直後はとても心強いですよね。
2は間違いです。
ソーシャルサポートは「道具的サポート」「情緒的サポート」「情報的サポート」「評価的サポート」の4つに分類されます。
3は間違いです。
4は何も問題ありません。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら