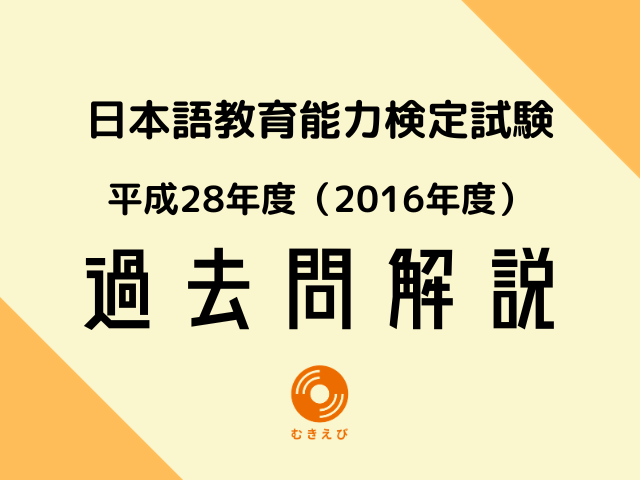平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題12
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 間接的表現
「間接的表現」とは、サールが定義した「間接発話行為」のことです。
用語の意味から確認していきましょう。
解説 間接発話行為
「間接発話行為」とは、相手に何らかの発話意図を伝える際に、直接的にではなく、間接的な別の発話をすることです。
「この部屋、暑いね」
→「窓を開けてほしい」「エアコンをつけてほしい」
「ハサミ持ってる?」
→「ハサミを貸してほしい」
その答えになる理由


直接的な表現ではなく、間接的に何らかの意図を伝えようとしているものを探しましょう。
「あそこの棚届く?」
→「棚の上の物を取ってもらいたい」
「届く?」という疑問文で、「取ってもらいたい」という依頼の意図を伝えていますね。
「間接的発話行為(間接的表現)」の例なので、1が正解です。
「~してよろしいでしょうか」は、マニュアル敬語で遠回りな言い方になっていますが、何か別の発話意図があるわけではありません。
「間接的発話行為(間接的表現)」の例ではないので、2は間違いです。
「次はぜひ」は、社交辞令かもしれませんが、何か別の発話意図があるわけではありません。
「間接的発話行為(間接的表現)」の例ではないので、3は間違いです。
「~させていただきます」は、過剰敬語の例ですね。
何か別の発話意図があるわけではありません。
「間接的発話行為(間接的表現)」の例ではないので、4は間違いです。
問2 母語習得
その答えになる理由


選択肢を1つずつ確認しておきましょう。
1のように、対象への注意を他者と共有することを「共同注意」と言います。
子どもに対して、視線を向けたり・指で指したり・持っているものを見せたりといった行動が該当します。
これが正解です。
令和3年度試験でも出題されているので、合わせてご確認ください。
「弁別」とは「区別する」ことです。
生まれた直後から母語の音韻を区別することができたら、超天才児ですね。
2は間違いです。
言語の発達の道筋が様々なのはその通りなのですが、どの言語にも共通する発達段階があるというのが「発達心理学」の考え方です。
「小さなうちから外国語を習わせよう!」というのは「共通の発達段階にいる年齢の方が、外国語が身に付きやすい」という主張に基づいています。
3は間違いです。
母語の音韻の大半は、子どもが養育者の発話を模倣うすることで習得されますが、文法は学校教育に頼る部分も少なくありません。
4は間違いです。
問3 英語母語話者が母語を直訳した結果、語用論的転移となった例
用語の意味を確認しておきましょう。
解説 語用論的転移(プログラマティック・トランスファー)
「 語用論的転移(プログラマティック・トランスファー) 」とは、文法的な間違いではなく、母語の影響を受けた不適切な表現使用のことです。
先生に対して「この本を読みたいですか」と言ってしまうように、文法的に間違っているわけではないが、それぞれの社会において適切な表現にちがいがあるために起きる誤用を指します。
その答えになる理由


「文法的には間違っているわけでないものの、その場面ではちょっと…」というものを探しましょう。
1は、自身の状態をどのように表現するかの違いだけなので、語用論的転移の例ではありません。
2は、英語の「Would you like to ~」をそのまま訳した結果、直接的な表現になってしまった例ですね。
「文法的には間違っているわけでないものの、その場面ではちょっと…」という内容なので、語用論的転移の例です。
これが正解です。
3は、伝えたい内容が変わってしまっていますね。
文法的に間違っているので、語用論的転移の例ではありません。
4は、助詞の選び方を間違えていますね。
文法的に間違っているので、語用論的転移の例ではありません。
問4 どのような場合に「語用論的転移」が起こりやすいか
その答えになる理由


問3の解説通り、語用論的転移は「母語の影響を受けた不適切な言語使用」です。
母語と目標言語がかけ離れている(と学習者が感じている)場合には起こりにくく、母語と目標言語が近い(と学習者が感じている)場合には起こりやすいと考えられています。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
母語と目標言語を「近い」と感じている場合、語用論的転移は起こりやすくなります。
1が正解です。
様々な表現方法を知っている場合、間違った表現を回避することができるので、語用論的転移は起こりにくくなります。
2は間違いです。
母語に特異性を感じているということは、母語と目標言語の差を感じているということです。
語用論的転移は起こりにくくなるので、3は間違いです。
母語と目標言語の違いを感じている場合は、語用論的手には起こりにくくなります。
4は間違いです。
問5 ロールプレイ
念のため、用語の意味を確認しておきましょう。
解説 ロールプレイ
「ロールプレイ」とは、会話の目的・状況等を設定し、与えられた役割に沿って会話を進める練習のことです。
●与えられた状況に限定して会話をする
●役割だけ与えて、自由に会話させる
など、学習者のレベルに応じて様々なやり方を取ることができます。
その答えになる理由


「表現学習」とは、講義形式でロールプレイで使用する表現・文型を教えることを指しています。
また「タスク」とは、実際のロールプレイのことを指しています。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
表現学習をタスクよりも先行させると、学習者は教えられた表現を使おうとするので、発言内容や表現形式の自由度が下がります。
1は間違いです。
初級前半レベルの学習者は何を話せばよいかわからないことが多いので、タスクよりも表現学習を先行させた方が良いですね。
2は間違いです。
表現学習をタスクよりも先行させると、学習者は教えられた表現を使おうとするので、状況対応力の養成にはつながりにくくなります。
3は間違いです。
タスクを表現学習よりも先行させることで、学習者に「この場合、どのように伝えたらよいのか」という気づきを与えることができます。
「したいこと」「できること」のギャップへの気づきにもつながりますね。
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら