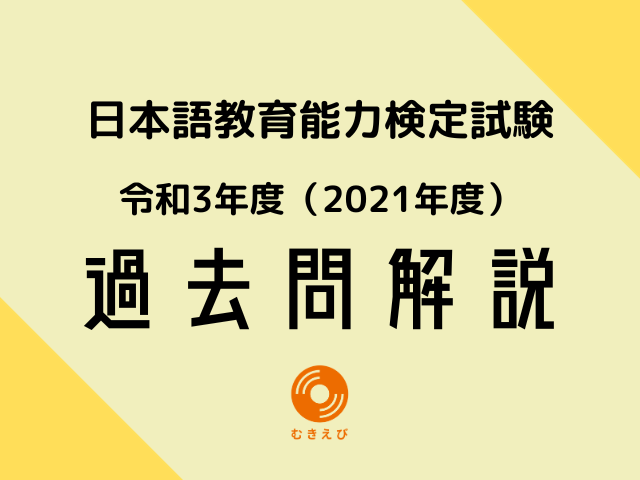令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題10
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 共同注意
解説 共同注意
視線を向ける
指で指す
持っているものを見せる
といった行動が該当します。
その答えになる理由


4が「共同注意」の説明そのままですね。
これが正解です。
問2 気づき仮説
解説 気づき仮説
その答えになる理由


1が「気づき仮説」の説明そのままですね。
これが正解です。
問3 維持リハーサル
解説 リハーサル
- 維持(型)リハーサル
- 精緻化リハーサル
に分けることができます。
解説 維持(型)リハーサル
解説 精緻化リハーサル
- 使用する状況を想定して、理解を深める
- 既習の知識と関連付ける
などが該当します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、既に知っている母語の意味と関連づけることで、対象の語を長期記憶に転送しようとしていますね。
これは、精緻化リハーサルの例です。
2は、すぐに忘れてしまわないように、対象の語を繰り返しるぶやいてワーキングメモリ内に残そうとしていますね。
これは、維持リハーサルの例です。
3は、共起する語と関連づけることで、対象の語を長期記憶に転送しようとしていますね。
これは、精緻化リハーサルの例です。
4は、類似の意味を持つ語と関連づけることで、対象の語を長期記憶に転送しようとしていますね。
これは、精緻化リハーサルの例です。
問4 ワーキングメモリ
解説 ワーキングメモリ
ワーキングメモリの容量には限界があり、ある作業で容量が取られてしまうと、別のことがスムーズに行えなくなるなどの現象が生じるとされています。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
語の記憶でワーキングメモリが圧迫されると、そのほかの処理に問題が生じることがありえます。
1は、間違いではありません。
談話において重要な部分をピックアップして記憶する能力は、高齢になると衰えていきがちです。
2は、間違いではありません。
第二言語では、母語と比べて語の意味を思い出したり、保持したりできる時間が短くなります。
3は、間違いではありません。
第二言語の使用経験が浅い場合、語の意味を思い出したり、保持したりするのにワーキングメモリが割かれやすいです。
そのため、思考などへの処理資源の割り当ては少なくなります。
4は、間違った内容です。
問5 チャンクの使用の効果
解説 チャンク
09012345678
だと覚えるのが大変ですが、チャンクにして
090-1234-5678
だと覚えやすくなりますね。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
ある語を別の語に置き換えてしまうのは、チャンクではありません。
1は、間違いです。
チャンクにすることで、注意を払わなくても自然な記憶・処理が可能になります。
結果、発話の流暢さが増すことになりますね。
2は、正しい内容です。
発話の間を埋めるのは、チャンクの役割ではありません。
「あの…」「ええと…」などは、フィラーと呼ばれます。
3は、間違いです。
チャンクはある語自体を区切って覚えるものなので、他の語は関係ありません。
4は、間違いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら