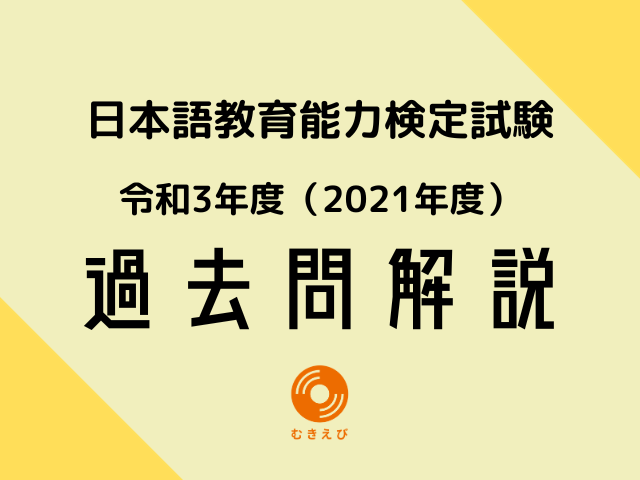令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題9
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 認知スタイル
解説 認知スタイル
さまざまな分類があり、令和5年度試験・令和3年度試験では、今回と同じ「場独立型⇔場依存型」が出題されました。
解説 場独立型
第二言語習得においては、
全体の把握や他の要素との関連づけがなくても回答が出せる文法
などに強いとされています。
解説 場依存型
第二言語習得においては、
社会的スキル
文脈からの判断
などに強いとされています。
その答えになる理由


「思考型」「内向型」については、出典元の論文を見つけられませんでした。。
3が「場依存型」の説明そのままなので、これが正解です。
問2 学習ストラテジー
解説 学習ストラテジー
大きく
- 直接ストラテジー
- 間接ストラテジー
に分けられます。
解説 直接ストラテジー
大きく
- 記憶ストラテジー
- 認知ストラテジー
- 補償ストラテジー
に分けられます。
● 記憶ストラテジー
記憶を定着させるために取る方法のことです。
語呂合わせや、繰り返し音読する等が該当します。
● 認知ストラテジー
言葉と言葉を関連づけたり、より大きな枠で取られるなと、認知的な理解を促進させる方法のことです。
教科書の内容をノートに自分の言葉でまとめる等が該当します。
● 補償ストラテジー
前後の文脈や背景知識を使って、言語の知識不足等による理解の支障を補っていく方法のことです。
解説 間接ストラテジー
大きく
- メタ認知ストラテジー
- 情意ストラテジー
- 社会的ストラテジー
に分けられます。
● メタ認知ストラテジー
自分自身の学習状況について客観的に観察し、把握するための方法のことです。
自身の得意・不得意を把握して学習計画を立てる等が該当します。
● 情意ストラテジー
自分の精神的な安定を保つためにとる方法のことです。
発表前に気持ちを落ち着かせる等が該当します。
● 社会的ストラテジー
人間社会や環境を利用する方法のことです。
母語話者の友人に質問したり、図書館で勉強したりする等が該当します。
その答えになる理由


各選択肢の例がどの学習ストラテジーに該当するかを見ていきましょう。
1は、「メタ認知ストラテジー」の例です。
2は、「情意的ストラテジー」の例です。
3は、「社会的ストラテジー」の例です。
4は、「補償的ストラテジー」の例です。
ストラテジーと例の内容が合致している4が正解です。
問3 キーワード法
解説 キーワード法
幼児が「ひらがな絵本」「ひらがなカード」などを使って
「あひる」の「あ」
「いるか」の「い」
のように、文字を覚えていくのは、キーワード法を使っています。
外国語学習であれば、覚えたい学習言語の語で使われている音をキーワードにして、似ている音が使われている母語を紐づけて記憶します。
その答えになる理由


1が「キーワード法」の説明そのままですね。
これが正解です。
問4 音韻処理能力
解説 音韻
日本語の音素は、
- 母音音素
- 子音音素
- 特殊(モーラ)音素
に分類され、特殊(モーラ)音素には、
- 促音
- 撥音
- 長音
の3つがあります。
その答えになる理由


「音韻処理能力」とは、
- 母音・子音などの音素
- イントネーション・アクセントなどの韻律
を処理する能力なので、音に関する情報を正しく把握する能力だと言えそうですね。
3が正解です。
問5 統合的動機づけ
解説 統合的動機
解説 道具的動機
解説 内発的動機
興味がある
おもしろい
などが例として挙げられます。
解説 外発的動機
ほめられたい
お金が欲しい
などが例として挙げられます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、自身の内面的な欲求が動機になっていますね。
これは、「内発的動機づけ」の内容です。
2は、外国語の上達そのものではなく、それによって利益を得ることが動機になっていますね。
外部報酬が目的になっていることから「外発的動機づけ」が、実利的な目的に向けたものであることから「道具的動機づけ」が該当します。
3は、自身の内面的な欲求が動機になっていますね。
これは、「内発的動機づけ」の内容です。
4は、「もっと知りたい」という自身の内面的な欲求と「もっと溶け込みたい」という願望が動機になっていますね。
これは、「内発的動機づけ」「統合的動機づけ」が該当します。
「統合的動機づけ」が含まれる4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら