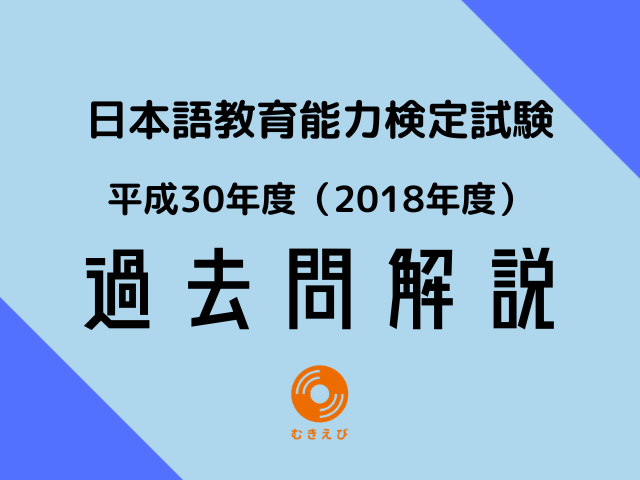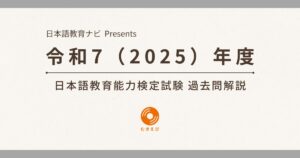平成30年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題13
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 言語景観
解説 言語景観
「言語景観」とは、街頭・公共施設・店舗などで見られる言語表記のことです。
広義では、上記のような場所で聞かれる音声も含みます。
新幹線内で次の停車駅を日本語と英語の両方で伝えるような「多言語使用」も、「言語景観」の一種です。
解説 コンバージェンス(収束・集中)
「コンバージェンス」とは、自分の話し方をできるだけ相手に近づけていくことです。
反対に、自分の話し方をできるだけ相手と話していくことを「ダイバージェンス」と言います。
解説 ダイグロシア
「ダイグロシア」とは、ある社会の中で「高変種(公的な場面で使用される言語形式)」「低変種(私的な場面で使用される言語形式)」の2つの言語変種が存在し、場面や状況によって、それぞれが使われる状況のことです。
※ 「言語変種」とは、同じ言語の中の異なった言語形式のことです。性別・年齢による違いや、方言などが例として挙げられます。
その答えになる理由


「道路標識」「広告看板」が例として挙げられているので「言語景観」のことです。
3が正解です。
4の「文字的場面」は初めて見ました。
Google先生も知らなかったので、受験生を混乱させるためだけの選択肢だと思われます。
問2 多言語表示
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
地域住民によって設置される看板等での多言語表示は、その言語の使用者の存在をアピールすることにもつながります。
1は間違いではありません。
多言語対応のガイドラインについては観光庁が定めていますが、私的表示は設置者の自由です。
そのため、どの言語を使用するかも恣意的に決めることができます。
2は間違いではありません。
「西友」「SEIYU」のように、複数の読み方ができる名称を正しく認識してもらうためにローマ字表記にすることがあります。
3が正解です。
「土日・夜間受付」を「After-hours Reception」と記載することがあります。
「土日・夜間」をそのまま翻訳するのではなく、「営業時間外」という内容で伝えています。
4は間違いではありません。
問3 案内板の多言語表示
その答えになる理由


下線部より、「音」「意味」が両方とも伝わるものを選びます。
「jinja(音)」「Shirine(意味)」と記載されている1が正解です。
問4 観光目的で日本を訪れる外国人
その答えになる理由


出典元はこちら
2が正解です。
問5 ピクトグラム
その答えになる理由


https://www.youtube.com/watch?v=Y-q7URCY7vY
東京2020オリンピック・パラリンピックで知った方も多いかと思います。
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら