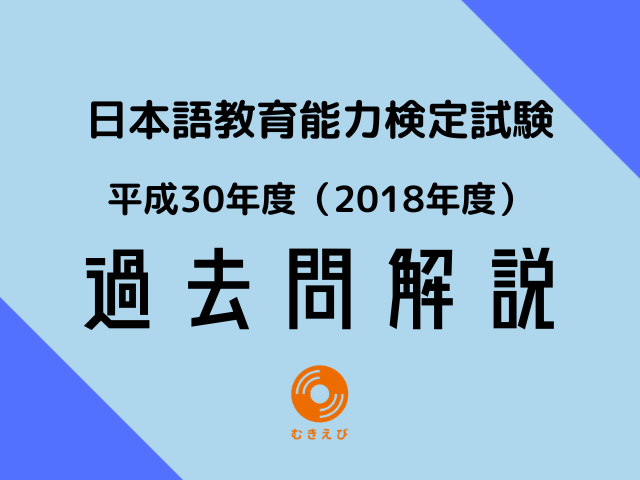平成30年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題15
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 c文化 (スモールシー文化)
解説 c文化 (スモールシー文化)
ブルックスによる文化の分類で、生活習慣や価値観などの目に見えないものが該当します。
(低文化・見えない文化とも言います。)
解説 C文化 (ラージシー文化)
ブルックスによる文化の分類で、歴史・文学・美術・音楽などの目に見えるものが該当します。
(高文化・見える文化とも言います。)
その答えになる理由


目に見えるものが「C文化(ラージシー文化)」、目に見えないものが「c文化(スモールシー文化)」です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 目に見えないので「c文化」
2 目に見えるので「C文化」
3 目に見えるので「C文化」
4 目に見えるので「C文化」
1が正解です。
問2 言語相対論(サピア・ウォーフの仮説)
解説 言語相対論(サピア・ウォーフの仮説)
「言語相対論」とは「言語と、その言語を母語とする人の思考や外界認識には何らかのかつながりがある」とする考え方のことです。
提唱者のサピアとウォーフの名を取って「サピア・ウォーフの仮説」とも呼ばれます。
解説 言語過程説
「言語過程説」とは、時枝誠記が提唱した「言語は単に音と意味が結合したものではなく、主体による表現や理解の過程である」とする考え方のことです。
解説 言語生得説
「言語生得説」とは、チョムスキーが提唱した「人間にはどんな言語であれ、それを母語として獲得する言語機能が生まれながらにして遺伝子の中に組み込まれている」という考え方のことです。
解説 言語行為論
「言語行為論」とは、オースティンによって提唱された「 従来の言語論が『命題の真偽』を主として問題にしてきたのに対し、文の発話は同時に『行為の遂行』となっている」という考え方のことです。
その答えになる理由


下線部が「言語相対論(サピア・ウォーフの仮説)」そのままですね。
4が正解です。
問3 菊と刀
その答えになり理由


人類学者ルース・ベネディクトが著した『菊と刀』では、日本文化を「恥の文化」・西洋文化を「罪の文化」として対比・分類しています。
3が正解です。
問4 タテ社会の人間関係
その答えになる理由


社会人類学者の中根千枝が著した「タテ社会の人間関係」では、「日本社会では、『場』(地域や職場など)という枠が、集団構成や集団認識において重要な役割を果たしている」とされています。
1が正解です。
問5 文化相対主義
解説 文化相対主義
「文化相対主義」とは、文化には多様性があるものの、その間には優劣はないとする立場のことです。
解説 自文化中心主義
関連する用語も合わせて整理してしまいましょう。
「自文化中心主義」とは、自身の文化が1番優れていると考え、自文化のものさしで他の文化も考えようとする立場のことです。
その答えになる理由


下線部が「文化相対主義」そのままですね。
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら