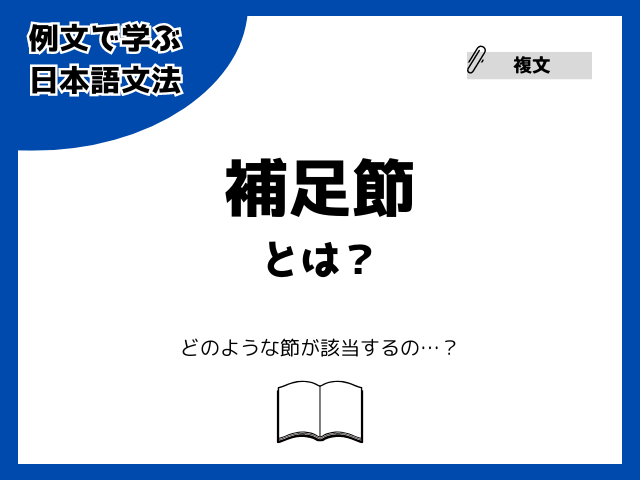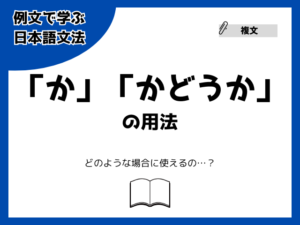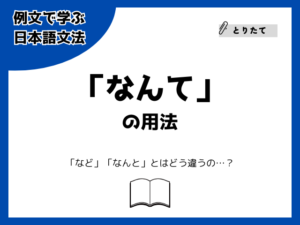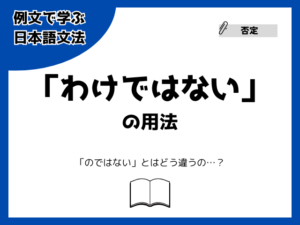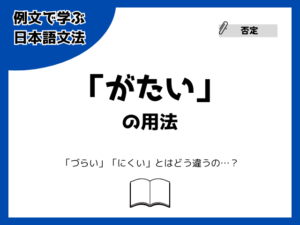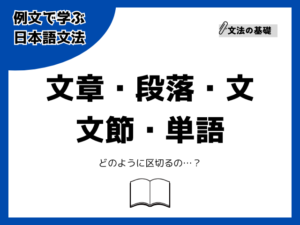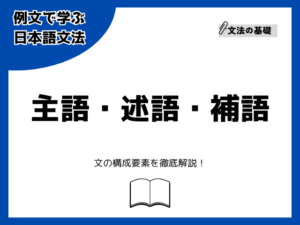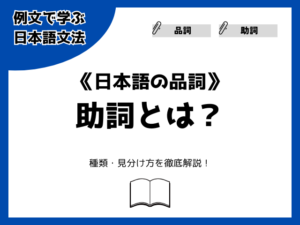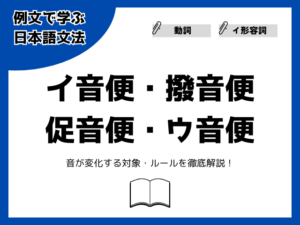今回は、
✅ 複文の種類
✅ 補足節とは?
✅ 補足節の3つのタイプ
について、一緒に勉強していきましょう。
この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、以下をブックマークしてご確認ください。
例文で学ぶ 日本語文法
前の記事はこちら
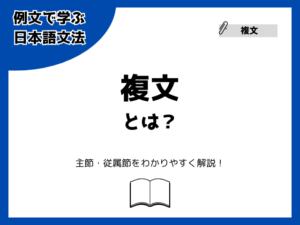
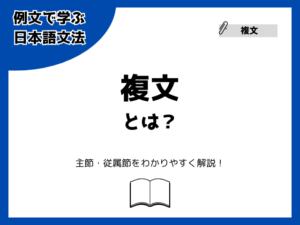
複文の種類
【① 補足節】
私は、小説を書くことが趣味だ。
【② 名詞修飾節】
Aさんが書いた小説を読んでいる。
【③ 副詞節】
小説を書いているときに、荷物が届いた。
【④ 等位節・並列節】
私が文を書いて、Bさんが挿絵を描いている。
今回は、【① 補足節】について、解説していきます。
補足節とは?
補足節を理解するためには、文の成分である「補語」について知る必要があります。
私は、日本酒が好きだ。
この文の述語は、「好きだ」ですね。
それでは、この文の「補語」は何でしょうか…?
「目的語」ではないの…?
と思った方もいるかもしれません。
中学・高校で習う英語では、
I am a student.
の「a student」を補語、
I play baseball.
の「basebnall」を目的語として勉強してきたかと思います。
SVCとSVOですね。
私は 大学で フランス語を 勉強しています。
この文の述語で使われているのは、動詞「勉強する」ですね。
「勉強する」には、主語以外に「●●を」の成分が必要です。
この文の補語は、「フランス語を」であることがわかります。
私は 母に 手紙を 送った。
この文の述語で使われているのは、動詞「送る」ですね。
「送る」には、主語以外に「●●に」「●●を」の成分が必要です。
この文の補語は、「母に」「手紙を」であることがわかります。
少し、練習してみましょう。
次の例文における「補語」は何でしょうか?
ねずみがネコにかみついた。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
ねずみがネコにかみついた。
この文の述語で使われているのは、動詞「かみつく」ですね。
「かみつく」には、主語以外に「●●に」の成分が必要です。
この文の補語は、「ネコに」であることがわかります。
もう1問やってみましょう。
私は 日本酒が 好きだ。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
私は 日本酒が 好きだ。
この文の述語で使われているのは、ナ形容詞「好きだ」ですね。
「好きだ」には、主語以外に「●●が」の成分が必要です。
この文の補語は、「日本酒が」であることがわかります。
ここまでの内容で、文中のどの語が補語にあたるかは大丈夫かと思います。
それでは、次の例文で「補語の役割を果たす」のはどこでしょうか?
私は 日本酒を集めることが 好きだ。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
私は 日本酒を集めることが 好きだ。
この文の述語で使われているのは、ナ形容詞「好きだ」ですね。
「好きだ」には、主語以外に「●●が」の成分が必要です。
この文の補語は、「日本酒を集めること」であることがわかります。
「日本酒を集めること」の述語は、「集める」ですね。
このような「述語を中心としたまとまり」のことを「節」と言います。
先ほどの
私は 日本酒が 好きだ。
では、補語が「日本酒が」でした。
私は 日本酒を集めることが 好きだ。
での「日本酒を集めることが」という節は、「日本酒が」と同じ役割をしていますね。
このように、補語の役割をする節のことを「補足節」と言います。
少し、練習してみましょう。
次の例文における「補足節」は、どの部分でしょうか?
彼は、Aさんが犯人だと言っている。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
彼は、Aさんが犯人だと言っている。
この文の述語で使われているのは、動詞「言う」ですね。
「言う」には、主語以外に「●●と」の成分が必要です。
この文の補語の役割をしているの補足節は、「Aさんが犯人だと」であることがわかります。
もう1問やってみましょう。
私には、誰が犯人であるかがわからない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
私には、誰が犯人であるかがわからない。
この文の述語で使われているのは、イ形容詞「わからない」ですね。
「わからない」には、主語以外に「●●が」の成分が必要です。
この文の補語の役割をしているの補足節は、「誰が犯人であるかが」であることがわかります。
それでは、次の例文ではどうでしょうか?
どこの部分が「補足節」にあたるかを考えてみてください。
日本酒を集めることが私の趣味だ。
「???」となった方は、ここまでの内容がきちんと理解できています…!!
- 「補足節」とは、補語の役割をする節のこと
- 「補語」とは、述語が必須に要求する成分のうち、主語以外として表れる成分のこと
として説明してきました。
そのため、
として、ご案内してきました。
私は、日本酒が好きだ。
私は、地元でつくられた日本酒が好きだ。
のように、「補語の位置にポンとあてはめられる節」が補足節のよくある形なのですが、別の形として
私の趣味は、日本酒を集めることだ。
のように、「だ」「である」などがついて述語化したり、
日本酒を集めることが私の趣味だ。
のように、主語化することがあります。
少し、練習してみましょう。
次の例文における「補足節」は、どの部分でしょうか?
1番嬉しかったのは、日本語教育能力検定試験に合格できたことだ。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
1番嬉しかったのは、日本語教育能力検定試験に合格できたことだ。
この文の補足節は、「日本語教育能力検定試験に合格できたこと」です。
「だ」がついて述語化していますね。
もう1問やってみましょう。
用語を丸暗記しないことが大切だ。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
用語を丸暗記しないことが大切だ。
この文の補足節は、「用語を丸暗記しないこと」です。
「が」がついて主語化していますね。
補足節の3つのタイプ
として整理しておきましょう。
最後に、例文で確認してみます。
次の例文における「補足節」は、どの部分でしょうか?
彼の使命は、世界の平和を守ることである。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
彼の使命は、世界の平和を守ることである。
この文の補足節は、「世界の平和を守ること」です。
「である」がついて述語化していますね。
次の文はどうでしょうか?
娘は、父の正体がスパイだと知っている。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
娘は、父の正体がスパイだと知っている。
この文の述語で使われているのは、動詞「知る」ですね。
「知る」には、主語以外に「●●と」または「●●を」の成分が必要です。
この文の補語の役割をしているの補足節は、「父の正体がスパイだと」であることがわかります。
次の文はどうでしょうか?
寝る前に過去問を解くのが私の習慣だ。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
寝る前に過去問を解くのが私の習慣だ。
この文の補足節は、「寝る前に過去問を解くのが」です。
「が」がついて主語化していますね。
参考書籍
今回は、
✅ 複文の種類
✅ 補足節とは?
✅ 補足節の3つのタイプ
について、解説してきました。
を主に参考にしています。
さらに詳しく勉強したい方は、ぜひ手に入れてみてください。
また、この記事以外にも、文法の記事を数多く掲載しています。
ぜひ、ブックマークしてご確認ください。


次の記事はこちら