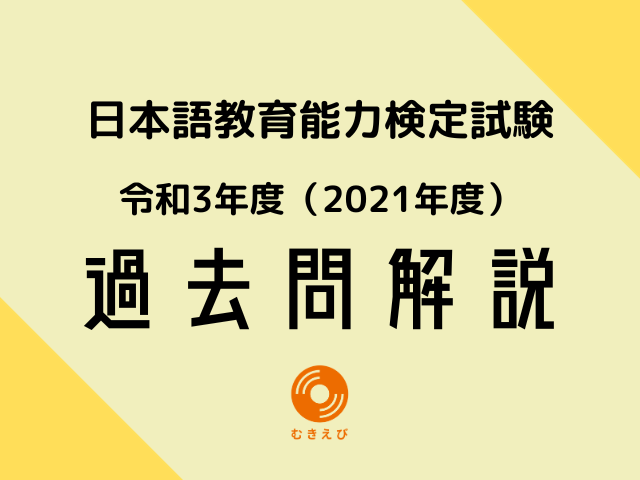令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題17
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


アウトラインの作り方
何について、どのように書かなければならないかを整理する
動画を用いた反転授業を行う上で、どのような動画を用意し、動画の内容を踏まえて授業時間内でどのような活動を展開するか?
- 上級の文法クラス
- 授業時間は、60分
- 動画を用いた反転授業を初めて取り入れる
- 400字程度
- 反転授業のメリットが十分活用できるような計画
- その活動が上級文法クラスにおいて効果的に考えられる理由についても言及
「上級の文法クラス」の具体的なイメージが湧かない…
「上級であれば、このレベル!」ではなく、
- 1つ1つの語彙・文型を丁寧に説明する必要がある「初級レベル」の導入まではいらない
というような極端な難易度のものを避けることができれば、それで問題ありません。
また、「文法クラス」なので、
- 「会話クラス」のようなコミュニケーション中心の授業
- 「読解クラス」のような読み物中心の授業
という内容は求められていません。
「400字程度」ってどれくらいまでが許容範囲?
記述式問題の解答用紙は、20字×21行=420字でマス目が印刷されています。
±1行以内として、400字よりも少ない場合は380字以上・多い場合は420字以内に収めるようにしましょう。
採点基準は公表されていませんが、極端に字数の不足・過多がある場合は、そもそも採点されないこともありえます。
段落構成を考える
動画内容・授業内容で段落分けする
この段落構成の場合、1段落目・2段落目ともに200字程度が目安になります。
各段落で書く内容を考える
パターン①
【動画の内容】
授業で取り扱う文法項目の意味・接続方法を一通り学べる内容
【動画を踏まえた授業での活動内容】
文法項目の導入を最低限の内容で行い、練習などに時間を割く
- 上級クラスであることから、動画で補助を行うことで、ある程度の内容までは学習者だけで進めることができる。
- 授業で一から導入する場合よりも導入部分の時間が削減できるため、発展した内容・応用の内容に取り組むことができる。
パターン②
【動画の内容】
授業で取り扱う文法項目の例文を複数提示する内容
【動画を踏まえた授業での活動内容】
その文法項目は、どのような意味で・場面で使われるのかを学習者同士で発表しあう
- 上級クラスであることから、既存知識を使って文法項目の内容を推測できる。
- 自身で考え、またほかの学習者の意見を聞くことで、一方的に教えられるよりも能動的に学習に臨むことができる。
書きながらチェックする内容
満たしていない条件はないか?
今回の条件は、
- 400字程度
- 反転授業のメリットが十分活用できるような計画
- その活動が上級文法クラスにおいて効果的に考えられる理由についても言及
でした。
問題文に線を引いていっても良いのですが、上記のように箇条書きにしてみると、漏れなくチェックすることができます。
本文を書き終えてからだと修正が難しいため、書きながら項目を1つずつ消していきましょう。
誤字・脱字はないか?
漢字が間違っていた場合は減点対象ですが、漢字で書けそうなところがひらがなになっていても減点されることはありません。
不安になるくらいであれば、ひらがなにしたり、漢字を使わない表現にしましょう。
最後に
記述式問題は、1回解いて終わりではなく、複数回取り組むのがおススメです。
やっていくうちに、やり方がパターン化できていくので、
- 日にちを空けて、再チャレンジしてみる
- 前回とは違う立場で書いてみる
- 前回とは違うキーワードを使って書いてみる
など、自身の勝ちパターンを増やしていきましょう。