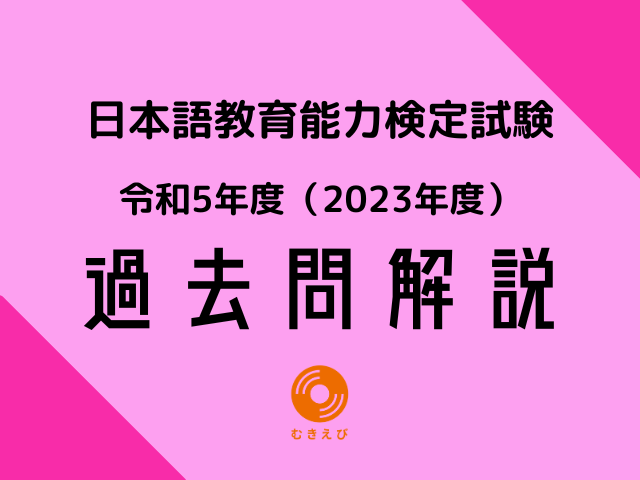令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題1
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
(1)摩擦音
日本語教育能力検定試験のトップバッターは、例年「音声記号」です。
これは、私が過去問を持っている「平成26年度試験」から変更ありません。
その答えになる理由


調音法が「摩擦音」でないものを選ぶ問題です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 [ɾ] 有声歯茎弾き音
2 [s] 無声歯茎摩擦音
3 [ʒ] 有声後部歯茎摩擦音
4 [h] 無声声門摩擦音
5 [ð] 有声歯摩擦音
1のみ、調音法が「弾き音」ですね。
これが正解です。
近年、日本語の子音にない音が出題される傾向にあります。
今回は、
1 日本語の「ラ行」の子音
2 日本語の「サ・ス・セ・ソ」の子音
4 日本語の「ハ・へ・ホ」の子音
ですが、3・5は初見の方も多かったのではないかと思います。
言語学を基礎から学んでいないと難しく感じるかもしれませんが、「仲間外れ」を探す問題なので、日本語の子音に使われる音声記号をしっかりと押さえておけば大丈夫です。
(2)促音の調音法
解説 促音の調音点・調音法
撥音(ん)・長音(-)と同じく「特殊拍」に分類され、1拍カウントです。
基本的に、後続するのは無声音のみです。
・ 鼻音
・ 弾き音
・ 接近音(半母音)
は有声音なので、促音で現れる調音法は、無声音の
・ 破裂音
・ 破擦音
・ 摩擦音
ですね。
後続音の子音が「摩擦音」の促音の場合は、その摩擦音の子音が1拍分発音されている状態です。
喫茶[kissa]であれば、後続する子音[s]の調音点・調音法なので「無声歯茎摩擦音」ですね。
後続音の子音が「破裂音・破擦音」の促音の場合は、1拍分の無音状態です。
嫉妬[sitto]であれば、後続する子音[t]の調音点・調音法なので「無声歯茎破裂音」なのですが、音は出ていません。
破裂音・破擦音は、一時的に呼気をため、それを開放して音を作っています。
促音の部分は「準備状態が前倒しされているだけ」のため、無音です。
このように、後続音が先行音に影響を与えて、同じ種類の音にする同化現象を「逆行同化」と言います。
撥音(ん)の音声記号が後続音によって変わるのも、「逆行同化」の例の1つです。
その答えになる理由


促音の調音法は、後続音の調音法と同じです。
各選択肢を簡易表記にしてみましょう。
1 [kikkɯ]
後続音は、[k] 無声軟口蓋破裂音です。
2 [gohho]
後続音は、[h] 無声声門摩擦音です。
3 [toppɯ]
後続音は、[p] 無声両唇破裂音です。
4 [hotto]
後続音は、[t] 無声歯茎破裂音です。
5 [ɾappa]
後続音は、[p] 無声両唇破裂音です。
2のみ、調音法が「摩擦音」ですね。
これが正解です。
(3)複合名詞のアクセント
解説 複合名詞
「合成法」とは、複数の形態素(意味を担う最小単位)を結合する方法で、「複合」と「派生」の2つに分かれます。
今回の問題とは関係ないのですが、「派生」とは、自由形態素と拘束形態(単独で語になることができない形態素)を結合させるもののことです。
その答えになる理由


アクセントとは、
のことでしたね。
複合名詞のアクセントの特徴は、複合することにより、単独の語のものから変化することです。
世界(高低低)+記録(低高高)→ 世界記録(低高高 高低低)
各選択肢のアクセントが複合することによってどう変化したかを見ていきましょう。
1 チーズ(高低低) + かまぼこ(低高高高)
→ チーズかまぼこ(低高高 高低低低)
2 クラブ(高低低)+ かつどう(低高高高)
→ クラブかつどう(低高高 高低低低)
3 ようじ(高低低) + きょういく(低高高高)
→ ようじきょういく(低高高 高低低低)
4 うちゅう(高低低) + かいはつ(低高高高)
→ うちゅうかいはつ(低高高 高低低低)
5 せいり(高低低) + せいとん(低高高高)
→ せいりせいとん(高低低 低高高高)
5のみ、複合名詞になっても、個々の語のアクセント型が変化していないですね。
これが正解です。
…というのが想定されている解き方だと思ったのですが、複合する前の状態のアクセントを確認しなくても、各複合名詞の高低を見るだけでも正解は選べます。
試験Ⅰ 問題1ですし、前部の名詞・後部の名詞の拍数・アクセント型が統一されているので、もっと単純に考えれば良かったのかもしれません。
(4)連声の有無
解説 連声
「反(はん)」+「応(おう)」→「反応(はんのう)」
「輪(りん)」+「廻(え)」→「輪廻(りんね)」
その答えになる理由


1 「おん+みつ」なので、特に音韻の変化はありません。
2 「けい+ねん」なので、特に音韻の変化はありません。
3 「すいとう」は、慣用読みの一種ですね。音韻が変化しているわけではありません。
4 「はん+おう」→「はんのう」なので、連声の例です。
5 「ちん+み」なので、特に音韻の変化はありません。
4が連声の例で、その他は音韻変化はありません。
これが正解です。
(5)音読み・訓読み
その答えになる理由


学習者を悩ませることが多い数字の読み方の問題ですね。
「いち・に・さん・し・ご・ろく・しち・はち・きゅう・じゅう」と数える場合、すべて音読みなのですが、この中に曲者が2ついます。
それは、「4」と「7」です。
「し」「しち」は聞き取りにくいので、「いち・に・さん・よん・ご・ろく・なな・はち・きゅう・じゅう」のように、「よん」「なな」と読む場合もあります。
「し」「しち」は音読みですが、「よん」「なな」は訓読みです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 に 音読み
2 さん 音読み
3 よん 訓読み
4 ご 音読み
5 きゅう 音読み
3が訓読みで、その他は音読みですね。
3が正解です。
(6)漢字の字源
解説 字源
漢字の字源は、
・ 象形
・ 指事
・ 会意
・ 形声
・ 転注
・ 仮借
の6種に分類され、「六書」と呼ばれています。
解説 象形
「日」「月」「人」「木」
などが該当します。
解説 指事
「一」「二」「上」「下」「本」
などが該当します。
解説 会意
「人+言→信」
などが該当します。
解説 形声
「日(意味の記号)+青(発音の記号)→晴」
などが該当します。
解説 転注
音楽の意義である「楽」を「ラク」と発音して「たのしい」という意義に転用
などが該当します。
解説 仮借
食物を盛る器の「豆(とう)」を「まめ」の意義に当てる
などが該当します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見てみましょう。
1 「山」は、物の形を絵画的にかたどって字形としているので「象形文字」です。
2 「木」は、物の形を絵画的にかたどって字形としているので「象形文字」です。
3 「日」は、物の形を絵画的にかたどって字形としているので「象形文字」です。
4 「月」は、物の形を絵画的にかたどって字形としているので「象形文字」です。
5 「上」は、事柄や数などの抽象的な概念を象徴的に記号化して字形としているので「指事文字」です。
5が「指事文字」で、その他は「象形文字」ですね。
5が正解です。
(7)短い形の使役受身形の有無
解説 使役受身形
国語教育では、
・ 未然形
・ 連用形
・ 終止形
・ 連体形
・ 仮定形
・ 命令形
という6つの活用形がありました。
日本語教育では、
・ 否定形(読まない)
・ 意向形(読もう)
・ テ形(読んで)
・ タ形(読んだ)
・ 辞書形(読む)
などの活用形を用いています。
日本語を話すことが目的なので、細かく分類するのではなく、ひとまとまりの表現として扱っているのが特徴です。
「使役形」や「受身形」も、日本語教育における活用形の1つです。
「読む」であれば、使役形が「読ませる」・受身形が「読まれる」ですね。
「使役受身形」は、この2つが合体します。
「読む」であれば、「読ませられる」ですね。
行為が強制されたことを被使役者(させられる側)から表現した文になるので、「嫌だ」「迷惑だ」と感じていることを表しています。
動詞のグループによって作り方が異なるので、それぞれ見てみましょう。
Ⅰグループ(五段動詞)の場合、
「読む」であれば…
・ 語幹「yom」に使役の接辞「-ase-」を付加して「yomase」
・ ↑に受身の接辞「-rare-ru」を付加して「yomaserareru」
→ 「読ませられる」
Ⅱグループ(一段動詞)の場合、
「着る」であれば…
・ 語幹「ki」に使役の接辞「-sase-」を付加して「kisase」
・ ↑に受身の接辞「-rare-ru」を付加して「kisaserareru」
→ 「着させられる」
Ⅲグループ(変格動詞)の場合、
「する」であれば、「させられる」
「来る」であれば、「来させられる」
使役受身形には、「読ませられる」のような通常の形以外にも、「読まされる」のような短い形(縮約形)が存在します。
ただ、使役受身形の「縮約形」は、すべての動詞にあるわけではありません。
基本的には、Ⅰグループ(五段活用)の動詞のみです。
「読む→読まされる」からわかるように、Ⅰグループ(五段活用)の動詞は、語幹に「-as-are-ru」を付加することで使役受身形の縮約形にすることができます。
その答えになる理由


上記ルールに基づき、語幹に「-as-are-ru」を付加して使役受身形の縮約形にできるかを見ていきましょう。
「話させられる」の語幹は、「hanas」ですね。
これに「-as-are-ru」を付加すると、「話さされる(hanasasareru)」となります。
不自然な形なので、1には短い形での使役受身形はありません。
「笑わせられる」の語幹は、「waraw」ですね。
これに「-as-are-ru」を付加すると、「笑わされる(warawasareru)」となります。
自然な形なので、2には短い形での使役受身形が存在します。
「泣かせられる」の語幹は、「nak」ですね。
これに「-as-are-ru」を付加すると、「泣かされる(nakasareru)」となります。
自然な形なので、3には短い形での使役受身形が存在します。
「働かせられる」の語幹は、「hatarak」ですね。
これに「-as-are-ru」を付加すると、「働かされる(hatarakasareru)」となります。
自然な形なので、4には短い形での使役受身形が存在します。
「待たせられる」の語幹は、「mat」ですね。
これに「-as-are-ru」を付加すると、「待たされる(matasareru)」となります。
自然な形なので、5には短い形での使役受身形が存在します。
1のみ、短い形での使役受身形が存在しないですね。
これが正解です。
蓋を開けてみれば、
使役受身形にするときは語幹に「-as-are-ru」を付加するが、語幹が「s」で終わるときは「さされる」のように「さ」が重複するので不自然になる。
というだけの問題なのですが、きちんと考えるのであれば上記のイメージです。
活用形の問題は、語幹と付加要素を分けるのが基本なので
ということに気づけたかがポイントですね。
(8)動詞の意志性
解説 意志動詞・無意志動詞
「意志動詞」は、その行動や状況を主体がコントロールすることができます。
「食べる」「読む」
などが意志動詞に該当します。
「無意志動詞」は、その行動や状況を主体がコントロールすることができません。
「咲く」「びっくりする」
などが無意志動詞に該当します。
その答えになる理由


意志をもつ動物の代表例である「人間」を主体にして、各選択肢を文にしてみましょう。
文が成り立てば「意志動詞」・成り立たなければ「無意志動詞」です。
1 ○ Aさんが移る。
2 ○ Aさんが去る。
3 × Aさんが茂る。
4 ○ Aさんが残る。
5 ○ Aさんが回る。
3のみ、文が成り立たないので「無意志動詞」ですね。
これが正解です。
今回の問題の引っ掛けポイントは、
1 ○ 首都が移る。
2 ○ 秋が早々に去っていった。
3 ○ 草が茂る。
4 ○ お酒が残っている。
5 ○ お酒が回る。
のように、意志性がないものを主体にして文をつくると、すべてが成立してしまうことです。
このように、「意志性があるか」の分類では、どちらにでも属することができる動詞が複数存在しています。
(9)接続詞の用法
その答えになる理由


「用法」の問題なので、語は違っていても共通する使い方があるということですね。
各選択肢を例文に挿入して考えてみましょう。
「仕事が忙しい。●●●、日本語教育能力検定試験に絶対に合格したい。」
1 仕事が忙しい。けれども、日本語教育能力検定試験に絶対に合格したい。
2 仕事が忙しい。しかし、日本語教育能力検定試験に絶対に合格したい。
3 仕事が忙しい。だが、日本語教育能力検定試験に絶対に合格したい。
4 仕事が忙しい。でも、日本語教育能力検定試験に絶対に合格したい。
5 仕事が忙しい。むしろ、日本語教育能力検定試験に絶対に合格したい。
5が不自然ですね…!!
1~4は、後続する内容が先行する内容から推論される内容とは異なる「逆接」の用法です。
5は、2つのうち「AよりもBを選ぶ」という気持ちを表しています。
「目先の合格よりも、むしろ、今後に活きる勉強方法を選びたい」のような使い方ですね。
「どちらかといえば」なども同じ使い方をします。
5が正解です。
(10)「を」の用法
解説 「を」の用法
【対象】の用法
【変化の対象】
本を棚に戻した。
【動作の対象】
文法を勉強した。
【心的活動の対象】
悲しい過去を思い出した。
【起点】の用法
【移動の起点】
最後に学校を出た。
【経過域】の用法
【空間的な経過域】
道の真ん中を通った。
【時間的な経過域】
ゴールデンウィークを海外で過ごした。
格助詞「を」の用法については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。
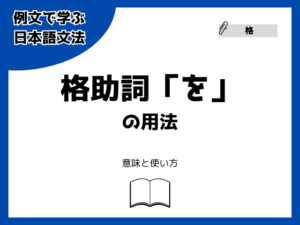
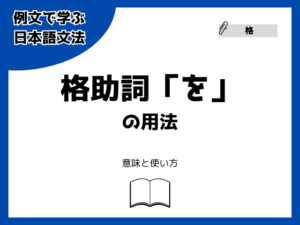
その答えになる理由


・ 格助詞の用法
・ ●格の用法
とあったら、見るのは「格助詞の直前の名詞」です。
「直前の名詞が述語に対してどのような関係か?」を確認していきましょう。
1 「大通り」は、「横切る」という述語の「空間的な経過域」に当たります。
2 「川」は、「渡る」という述語の「空間的な経過域」に当たります。
3 「車」は、「通す」という述語の「動作の対象」に当たります。
4 「廊下」は、「走ってはいけない」という述語の「空間的な経過域」に当たります。
5 「土手」は、「散歩する」という述語の「空間的な経過域」に当たります。
3が「対象」で、その他は「経過域」の用法ですね。
3が正解です。
「格」の問題は、毎年必ず複数出題されています。
こちらの記事も、あわせて確認してみてください。
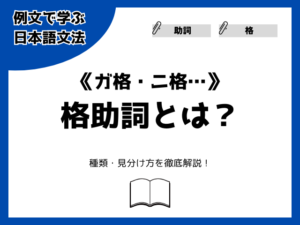
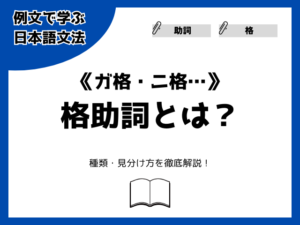
・格
— むきえび|日本語教育ナビ運営 (@E6b4eQSNWEXYZXB) June 1, 2023
・複文
・音声記号
あたりが「必ず出題されて・配点も多く・合格後も使う知識」です。
「フォーカス・オン・○○」のような紛らわしいカタカナ語に翻弄されているかもしれませんが、全体から見れば枝葉に過ぎません。
大きな石から積んでいくことが大切です。#日本語教育能力検定試験
「●格の用法」といった格助詞の問題は、毎年必ず出題されています。
— むきえび|日本語教育ナビ運営 (@E6b4eQSNWEXYZXB) October 3, 2023
「覚えることが多い…」となるかもですが、副詞や複文のような「例文を作る」ハードルがないので、安定した得点源にしやすいはず…
解き方を言語化できているかが重要です。https://t.co/cuxlowWzvC#日本語教育能力検定試験
(11)「まで」の用法
その答えになる理由


先ほどの「を」と同じく、「まで」も格助詞の1つです。
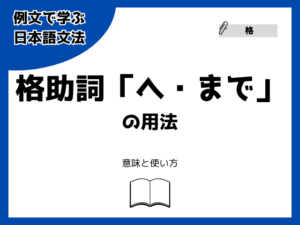
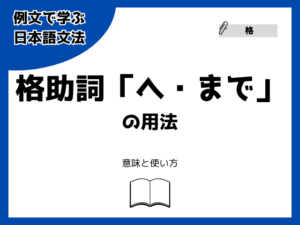
「赤本の学習を10ページまで終えた」のように【(範囲の)着点】を表すのですが、他の格助詞のように複数の用法を持っているわけではありません。
よくセットで出てくるのは、【(範囲の)起点】を表す「から」です。
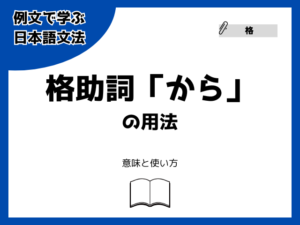
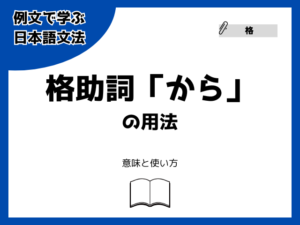
今回は、同じ格助詞の別の用法を探す問題ではなく、そもそも格助詞ではないものが紛れ込んでいますね。
【(範囲の)起点】を表す「から」を付加して検証して見ましょう。
付加できれば、格助詞「まで」です。
2 自宅から会社まで
3 35度から38度まで
4 今日から3か月後まで
5 前日の夜から朝まで
のように、2~5は【(範囲の)起点】を表す「から」を付加しても文が成り立つので【(範囲)の着点】を表す格助詞「まで」ですね。
1の「まで」は、とりたて助詞です。
とりたて助詞とは、他の要素との関係を背景に、文中の語について様々な意味を付け加える働きをする助詞のことです。
文中では明示されていませんが、「ほかの簡単なものだけでなく、作るのが難しいチーズまで…」という情報を読み取ることができますね。
極端な例示の用法で、同じような使い方をする取り立て助詞に「さえ」があります。
1が正解です。
(12)「ておく」の用法
解説 「ておく」の用法
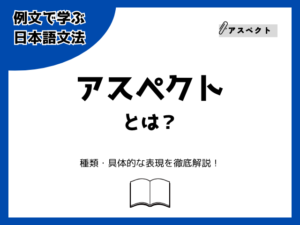
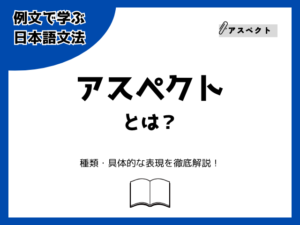
「ておく」の用法は、大きく分けて2つ。
【行為の結果の維持】と【事前の処置】です。
【行為の結果の維持】換気のため、窓を開けておいた。
【事前の処置】あらかじめ野菜を切っておいた。
その答えになる理由


各選択肢が【行為の結果の維持】【事前の処置】のどちらかを見ていきましょう。
その行為を「あえて、やりっぱなしにしている」のであれば【行為の結果の維持】・「事前準備としてやっているだけで、継続的な状態ではない」のであれば【事前の処置】です。
1 「流す」という行為の結果の維持
2 「閉める」という行為の結果の維持
3 「見直す」という事前の処置
4 「エンジンを掛ける」という行為の結果の維持
5 「つける」という行為の結果の維持
3が【事前の処置】で、その他は【行為の結果の維持】の用法ですね。
3が正解です。
(13)「ながら」の用法
その答えになる理由


「ながら」は、【付帯状況】と【逆接】の用法でよく出てきます。
【付帯状況】Aさんが歌いながら教室に入ってきた。
【逆接】Aさんは真実を知っていながら教えてくれなかった。
「ある動作が別の動作に付随して行われている」のであれば【付帯状況】・「後続する内容が先行する内容から推論される内容とは異なる」のあれば【逆接】です。
各選択肢が【付帯状況】【逆接】のどちらかを見ていきましょう。
1 「出す」という動作が「発酵し続ける」という動作に付随して行われている
2 「抱く」という動作が「励む」という動作に付随して行われている
3 「連携する」という動作が「取り組む」という動作に付随して行われている
4 「醸成する」という動作が「構築する」という動作に付随して行われている
5 友人の家の前まで行ったのであれば、謝れたはずだが…
5が【逆接】で、その他は【付帯状況】の用法ですね。
5が正解です。
(14)副詞的成分と述語の関係
その答えになる理由


紅に染まったこの俺を慰める奴はもういない
であれば、副詞的成分は「紅に」・述語は「染まった」です。
また、
しっとりと歌い上げた
であれば、副詞的成分は「しっとりと」・述語は「歌い上げた」です。
副詞の用法はいくつかあるのですが、選択肢となっているものに絞ってみてみましょう。
「紅に染まった」は、染まったことで紅になっていますね。
この場合、副詞成分「紅に」は【結果】を表しています。
「しっとりと歌い上げた」から、どのようにその動作をしたかがわかりますね。
この場合、副詞成分「しっとりと」は【様態】を表しています。
各選択肢が【結果】【様態】のどちらかを見ていきましょう。
1 砕け散った結果、粉々になった
2 煮込んだ結果、柔らかくなった
3 どのように炒めたか?→さっと炒めた
4 焼き上がった結果、ふっくらとなった
5 塗った結果、桜色になった
3が【様態】で、その他は【結果】の用法ですね。
3が正解です。
(15)「については」の用法
その答えになる理由


私は、↓の赤字のように考えて3を選びました。
公式解答を見て出題意図が理解できたので、改めて解説します。
(どのように間違えたか?を見てほしいので、過去の内容を赤字で残しておきます。)
「について」のように、格助詞+αの形式で格助詞と同じような働きをするものを「複合格助詞」と言います。
子どもたちの将来を考えた。
子どもたちの将来について考えた。
どちらも【対象】を表していますが、「について」の方が【思考や言語活動のテーマとしての対象】という意味がより明示的になっていますね。
また、
本学で式典が執り行われます。
本学において式典が執り行われます。
だと、どちらも【場所】を表していますが、「において」の方があらたまったニュアンスになりますね。
このように、複合格助詞は、格助詞でも表すことができる意味をさらに明示かしたり、文体的な性質を変えたりする働きを持っています。
「については」は、複合格助詞の「について」の後ろにとりたて助詞の「は」が接続されたものです。
とりたて助詞「は」の主な用法は、主題と対比ですね。
今日の晩御飯はカレーです。
のように、その文が何について述べているのかを示すのが「主題」の用法で
Aさんとは仲良しです。
のように、複数の同類のものを比べるのが「対比」の用法です。
上の例文は晩御飯のメニューについて述べているだけですが、下の例文では「ほかに仲良しではない人がいる」ということがわかりますね。
整理すると、
「について」には、思考や言語活動のテーマとしての対象の用法
「は」には、主題と対比の用法
があるということです。
これらが組み合わさった「については」は、どちらの要素が強いかによって、2つの用法があります。
1つ目は、「は」の要素が強い「対比要素のある主題」の用法です。
機能については問題ないのですが、価格がネックですね。
「機能」を主題としているのですが、単に述べているだけでなく、「価格」と対比させています。
この例文は、
○ 機能は問題ないのですが、価格がネックですね。
× 機能について問題ないのですが、価格がネックですね。
のように、「は」だけにしても文は成立しますが、「について」だけだと不自然ですね。
これは、ここでの「については」が「対比要素のある主題」の用法だからです。
「は」には主題と対比の用法があるので、「については→は」に置き換えられます。
「について」にあるのは対象の用法しかないので、置き換えることができません。
2つ目は、「について」の要素が強い「思考や言語活動の対象である主題」の用法です。
新製品については私がご説明します。
「何を説明するか?」の「何」に入るのが「新製品」ですね。
この「新製品」は、説明するという言語活動の対象に当たります。
この例文は、
○ 新製品について私がご説明します。
× 新製品は私がご説明します。
のように、「について」だけにしても文が成立しますが、「は」だけだと不自然ですね。
これは、ここでの「については」が「思考や言語活動の対象である主題」の用法だからです。
「説明する」のような対象となる補語が必要な場合だと、対象の用法がない「は」は単独で使えないですね。
ただし、置き換えだけで考えると、「なんだかどちらでも良い気がする…」となるので注意しましょう。
今回の問題の真のポイントは、
「については」に続く部分に、「述語の対象となる語句」が欠けていないか?
です。
欠けていれば「●●については」の●●部分が対象に当たるので「思考や言語活動の対象である主題」の用法・欠けていなければ「対比要素のある主題」の用法ですね。
選択肢を見ていきましょう。
1の「問題ありません」に、欠けている「対象となる語句」はありません。
また、「この案件は」に置き換えも可能ですね。
これは、「対比要素のある主題」の用法です。
2の「設営が終わっていません」には、「設営」という「『終わる』の対象となる語句」が含まれています。
また、「講演会の会場は」に置き換えも可能ですね。
これは、「対比要素のある主題」の用法です。
3の「ご迷惑をお掛けしました」には、「ご迷惑」という「『お掛けする』の対象となる語句」が含まれています。
また、「この度の納品は」に置き換えも可能ですね。
これは、「対比要素のある主題」の用法です。
4の「現在調べを進めております」では、「『調べ』の対象となる語句」が欠けています。
また、「その容疑者の身辺について」に置き換えも可能ですね。
これは、「思考や言語活動の対象である主題」の用法です。
5の「ご好評いただいております」には、「お客様」という「『ご好評いただく』の対象となる語句」が含まれています。
また、「こちらの商品は」に置き換えも可能ですね。
これは、「対比要素のある主題」の用法です。
4だけ「思考や言語活動の対象である主題」の用法・その他は「対比要素のある主題」の用法ですね。
4が正解です。
当初の解説内容
↓ここから
「について」のように、格助詞+αの形式で格助詞と同じような働きをするものを「複合格助詞」と言います。
子どもたちの将来を考えた。
子どもたちの将来について考えた。
どちらも【対象】を表していますが、「について」の方が【思考や言語活動のテーマとしての対象】という意味がより明示的になっていますね。
また、
本学で式典が執り行われます。
本学において式典が執り行われます。
だと、どちらも【場所】を表していますが、「において」の方があらたまったニュアンスになりますね。
このように、複合格助詞は、格助詞でも表すことができる意味をさらに明示かしたり、文体的な性質を変えたりする働きを持っています。
「については」は、複合格助詞の「について」に取り立て助詞の「は」が接続されたものです。
取り立て助詞とは、他の要素との関係を背景に、文中の語について様々な意味を付け加える働きをする助詞のことでしたね。
ピーマンが好きです
ピーマンは好きです
だと、「は」が使われることで「ほかの野菜は嫌い…」という意味が付け加えられていることがわかると思います。
この「意味が付け加えられているか?」が今回のポイントです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 この案件だけは、問題がなさそうなことがわかっている
(他の案件は、問題があるかわからない)
2 講演会の会場だけは、設営が終わっていない
(他の会場は、設営が終わっている)
4 容疑者の身辺だけは、調べを進めている
(身辺調査以外は、調べを進めていない)
5 こちらの商品だけは、好評だ
(他の商品は、好評かわからない)
のように、1・2・4・5は、「●●だけは~」という【限定叙述】の用法です。
「については」を「は」だけにしても同じことを表しますが、「について」だけにすると意味合いが変わってきますね。
3は、「については」を「について」だけにしても「は」だけにしても同じ内容を表すことができます。
「この度の納品は迷惑を掛けたが、それ以外は迷惑を掛けていないもんね!」のように内容を限定しているわけではなく、単に迷惑を掛けた対象として「この度の納品」を挙げているだけですね。
「Aさんは日本語教師です」
のときに、「Bさんは違うが、Aさんは…」というように限定しているか、ただ「Aさん=日本語教師」ということを表しているかの違いをイメージするとわかりやすいのではないかと思います。
前者は「限定」の意味を付け加えていますが、後者は「主題」として述べているだけです。
3が正解です。
↑ここまで
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら