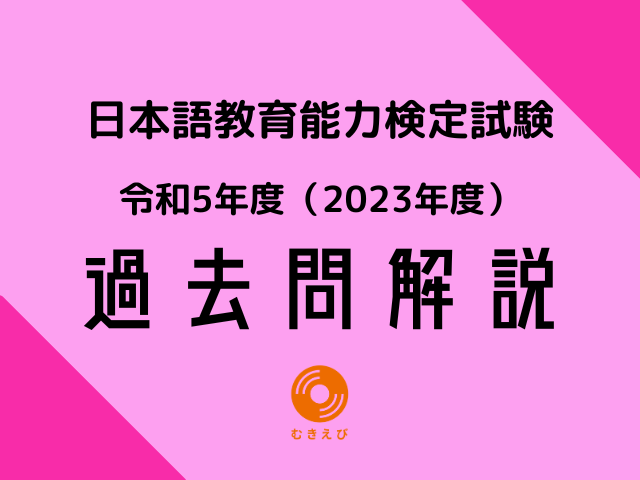令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題2
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


(1)
その答えになる理由


【 】内では、「がいこく」とすべきところが「かいこく」になっています。
[g] 有声軟口蓋破裂音
[k] 無声軟口蓋破裂音
のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、「だいこう」とすべきところが「たいこう」になっています。
[d] 有声歯茎破裂音
[t] 無声歯茎破裂音
のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。
2は、「げんこう」とすべきところが「けんこう」になっています。
[g] 有声軟口蓋破裂音
[k] 無声軟口蓋破裂音
のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。
3は、「でんとう」とすべきところが「てんとう」になっています。
[d] 有声歯茎破裂音
[t] 無声歯茎破裂音
のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。
4は、「ぶちょう」とすべきところが「ふちょう」になっています。
[b] 有声両唇破裂音
[ɸ] 無声両唇摩擦音
のように、声帯振動が有声→無声に置き換わり、さらに調音法も変わる誤用です。
音声記号や口腔断面図を「五十音順」で覚えていると、即答できないですね…!!
調音法ごとに、ミニマルペアを押さえていれば楽勝です。
4は、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用だけであれば
[b] 有声両唇破裂音
[p] 無声両唇破裂音
となるので、「ぶちょう」と発音すべきところが「ぷちょう」になります。
4が正解です。
(2)
その答えになる理由


【 】内では、「しつれい」とすべきところが「しちゅれい」になっています。
[ʦ] 無声歯茎破擦音
[ʨ] 無声歯茎硬口蓋破擦音
のように、調音点が置き換わる誤用です。
1は、「ございます」とすべきところが「ごじゃいます」になっています。
[z] 有声歯茎摩擦音
[ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音
のように、調音点が置き換わる誤用です。
2は、「ちゅうい」とすべきところが「じゅうい」になっています。
[ʨ] 無声歯茎硬口蓋破擦音
[ʥ] 有声歯茎硬口蓋破擦音
のように、声帯振動が有声→無声に置き換わる誤用です。
3は、「どうぞ」とすべきところが「どうじょ」になっています。
[z] 有声歯茎摩擦音
[ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音
のように、調音点が置き換わる誤用です。
4は、「とうぜん」とすべきところが「とうじぇん」になっています。
[z] 有声歯茎摩擦音
[ʑ] 有声歯茎硬口蓋摩擦音
のように、調音点が置き換わる誤用です。
2だけ誤用の種類が違いますね。
これが正解です。
今回の誤用は、すべて調音点が「歯茎→歯茎硬口蓋」になっていますね。
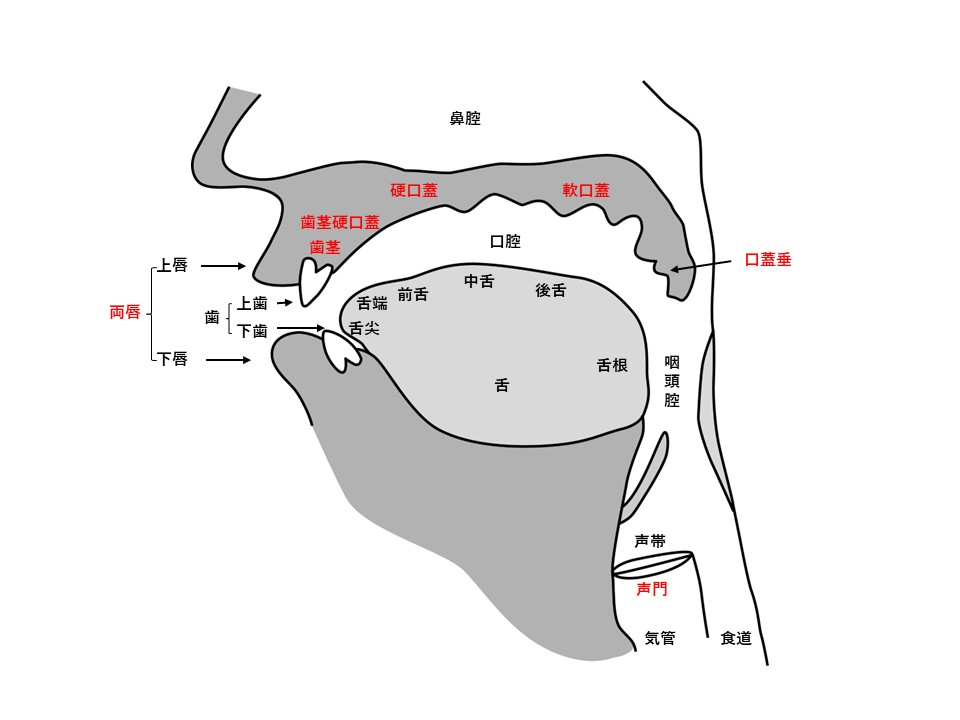
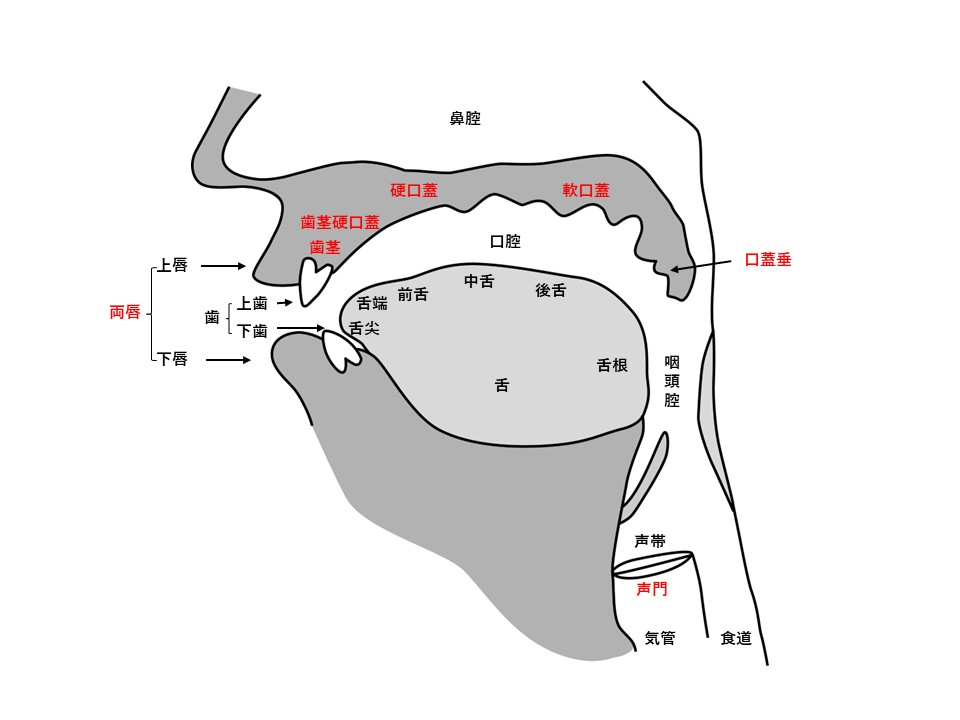
このような現象のことを「硬口蓋化」と言います。
試験Ⅱで出てくることもあるので、あわせて確認しておきましょう。
解説 硬口蓋化
日本語では、
・ イ段の子音
・ それを用いた拗音の子音
で見られる現象です。
① 調音に舌を用いない場合(両唇音)
子音の調音時に、母音の[i]のような舌の硬口蓋への盛り上がりが同時調音として加わります。
② 調音に舌を用いる場合(鼻音・破裂音・摩擦音…)
子音の調音時に、舌が硬口蓋の方向にズレます。
・ 歯茎音であれば、後ろにある歯茎硬口蓋へ
・ 軟口蓋音であれば、前にある硬口蓋後部~軟口蓋前部へ
(3)
解説 言語転移
学習言語の習得にプラスに働く場合を「正の転移」、マイナスに働く場合を「負の転移」と言います。母語と学習言語に共通点が多い場合は「正の転移」、異なる点が多い場合は「負の転移」が出やすくなります。
その答えになる理由


「Old person」を直訳したような誤用ですね。
母語が英語である学習者による負の転移だと思います。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、「多くの本」とすべきところが「多い本」となっています。
イ形容詞は
・ この本は分厚い
・ 分厚い本
のように、述語になることも・直接名詞を修飾することもできます。
特殊なパターンとして出てくることが多いのは「多い」「少ない」です。
○ 会場に人が多い
△ 多い人が会場にいる
○ 会場に人が少ない
△ 少ない人が会場にいる
これらは直接名詞を修飾すると不自然になることがあり、その場合は
○ 多くの人が会場にいる
△ 少しの人が会場にいる
のように表します。
「多く」「少し」は、連体助詞「の」に接続しているので名詞ですね。
このように、他の品詞から名詞になった語のことを「転成名詞」と言います。
1は、転成名詞を使うべきところに、そのままの品詞を当てはめてしまった誤用です。
2は、「heavy rain」の直訳ですね。
母語が英語である学習者による負の転移です。
3は、「busy street」の直訳ですね。
母語が英語である学習者による負の転移です。
4は、「cold drink」の直訳ですね。
母語が英語である学習者による負の転移です。
1だけ誤用の種類が違いますね。
これが正解です。
(4)
その答えになる理由


【 】内では、「食べずに」とすべきところが「食べなくて」になっています。
「AずにB」を「AなくてB」にする誤用ですね。
先に、答えを確認しておきましょう。
1は、「諦めずに」とすべきところが「諦めなくて」になっています。
「AずにB」を「AなくてB」にする誤用です。
2は、「せずに」とすべきところが「しなくて」になっています。
「AずにB」を「AなくてB」にする誤用です。
3は、「来ないので」とすべきところが「来なくて」になっています。
「AずにB」を「AなくてB」にする誤用ではないですね。
4は、「使わずに」とすべきところが「使わなくて」になっています。
「AずにB」を「AなくてB」にする誤用です。
3だけ誤用の種類が違いますね。
これが正解です。
【 】内は、「食べないで」とすべきところを「食べなくて」とする誤用では…?でも合っています。
「AないでB」と「AずにB」は、同じことを表しているからです。
勉強しないで、試験に臨んだ。
勉強せずに、試験に臨んだ。
「AないでB」の方が、口語の色が強くなりますね。
(5)
その答えになる理由


【 】内では、「分かっているという意味」とすべきところが「分かっている意味」になっています。
「という」が抜け落ちる誤用ですね。
「という」「っていう」は、聞き手が知らないであろう人・物などを話すときに用いられます。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、「~遅れるという意味」とすべきところが「~に遅れる意味」になっています。
「という」が抜け落ちる誤用ですね。
2は、「~鳴くという意味」とすべきところが「~鳴く意味」になっています。
「という」が抜け落ちる誤用ですね。
3は、「~授けるという意味」とすべきところが「~授ける意味」になっています。
「という」が抜け落ちる誤用ですね。
4は、「呼び方の一種」が正しい表現でしょうか…?
これだけ誤用の種類が違いますね。
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら