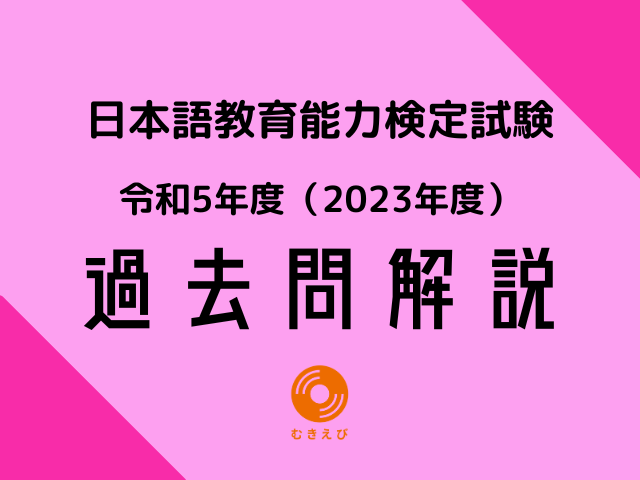令和5年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題12
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 字音・字訓
解説 字音
伝わった時期によって
呉音・漢音・唐音
などの種類があります。
解説 字訓
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「漢語」は古来中国から伝来して日本語となった語・「和語」は日本固有の語です。
「字音」は古来日本に伝来して国語化した漢字の音のことなので、字音が使われるのは漢語のみですね。
1は間違いです。
「和製漢語」とは、日本で・日本人によって作られた漢語のことです。
漢語なので、字訓ではなく字音が使われています。
特に幕末・明治維新以降、欧米由来の概念を表すための翻訳借用語として増えていきました。
「科学」「哲学」「郵便」「野球」などが、よく例として挙げられますね。
2は間違いです。
「行」には「行く(いく)」「行う(おこなう)」の2つの字訓が割り当てられていますね。
字訓とは「漢字の意味に当たる日本語がその漢字の読みとして固定化したもの」なので、意味が複数あれば字訓も複数割り当てられることが多いです。
3が正解です。
ちなみに、字音は1つの漢字に対して1つ…というわけではありません。
「行」には「行動(こうどう)」「修行(しゅぎょう)」「行脚(あんぎゃ)」という3つの字音があります。
これは、いつの時代の中国語かの違いです。
「こう」は呉音・「ぎょう」は漢音・「あん」は唐音ですね。
和語は日本固有の語なので、漢字に関係のある字訓とはイコールではありません。
「Aさん」「勉強したい」のように漢字で表さない和語も多く存在しますね。
4は間違いです。
和語・漢語などの語種については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。


問2 現代仮名遣い・送り仮名の付け方
その答えになる理由


日本語の表記関連の内閣告示・内閣訓令は、文化庁のHPの内容がベースになっています。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1の参考はこちら
現代仮名遣い 本文 第2(表記の慣習による特例)
6 次のような語は,オ列の仮名に「お」を添えて書く。
例 おおかみ おおせ(仰) おおやけ(公) こおり(氷・郡△) こおろぎ
ほお(・朴△) ほおずき ほのお(炎) とお(十)
いきどおる(憤) おおう(覆) こおる(凍) しおおせる とおる(通) とどこおる(滞)
もよおす(催) いとおしい おおい(多) おおきい(大) とおい(遠)
おおむね おおよそこれらは,歴史的仮名遣いでオ列の仮名に「ほ」又は「を」が続くものであって,オ列の長音として発音されるか,オ・オ,コ・オのように発音されるかにかかわらず,オ列の仮名に「お」を添えて書くものである。
文化庁HP
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 現代仮名遣い > 本文 第2(表記の慣習による特例)
表記の特例の中に歴史的仮名遣いの痕跡が残されています。
1が正解です。
2の参考はこちら
現代仮名遣い 前書き
この仮名遣いは,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。
文化庁HP
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 現代仮名遣い > 前書き
現代仮名遣いは、科学技術分野の語彙の表記を整えるために定められたものではないですね。
2は間違いです。
3の参考はこちら
送り仮名の付け方 単独の語 1 活用のある語 通則1
許容次の語は,( )の中に示すように,活用語尾の前の音節から送ることができる。
表す(表わす) 著す(著わす) 現れる(現われる) 行う(行なう) 断る(断わる) 賜る(賜わる)
文化庁HP
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 送り仮名の付け方 > 本文 通則1
「活用のある語は、活用語尾を送る」が通則ですが、いくつか許容の例が記載されていますね。
3は間違いです。
4の参考はこちら
これは,昭和47年6月28日,国語審議会会長から文部大臣に答申した「改定送り仮名の付け方」を政府として採択し,「一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころ」として,翌48年6月18日に内閣告示第1号をもって告示したものです。
文化庁HP
政府は,内閣告示と同じ日に内閣訓令第2号「「現代仮名遣い」の実施について」を発し,今後,各行政機関においてこれを送り仮名の付け方のよりどころとすべき旨を訓令しました。
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 送り仮名の付け方 > 解説
公用文が横書きになった際の正書法ではないですね。
4は間違いです。
問3 手紙での会話と異なる表現
解説 接辞
新社会人
「新」が接辞
子どもっぽい
「っぽい」が接辞
「新」のように語の前に付く接辞を「接頭辞」・「っぽい」のように語の後ろにつく接辞を「接尾辞」と言います。
解説 卓立(プロミネンス)
解説 頭語・結語
組み合わせがあり、
- 一般的な手紙 拝啓→敬具
- 丁寧な手紙 謹啓→謹言
- 親しい人への手紙 前略→草々
などが使われます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
接頭辞とは「僕は、新世界の神となる」の「新」のような語の前に付く接辞のことです。
会話にも見られる表現なので、1は間違いです。
手紙は会話よりも文語的ですが、さすがに「社会人ぞ、かくあるべき」のように、現代語で係り結びを使うことはないですね。
2は間違いです。
卓立(プロミネンス)は「伝達の意図で、文中の特定の部分を際立たせて発音すること」なので、会話には見られますが、音声ではない手紙には見られません。
3は間違いです。
頭語は結語とセットで手紙の最初に用いられる語で、丁寧さによって「拝啓」「謹啓」「前略」などを使い分けします。
4が正解です。
問4 意味範囲が限定的で比喩的な使われ方をする定型表現
その答えになる理由


下線部は小難しいですが、比喩表現を探すだけの問題ですね。
「さくらさく」は、実際に桜が咲いているわけではなく、合格による嬉しい気持ちを表した隠喩(メタファー)です。
電報は文字数で料金が決まるので、短く表現するために生まれた…という説があります。
1が正解です。
比喩の種類については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。
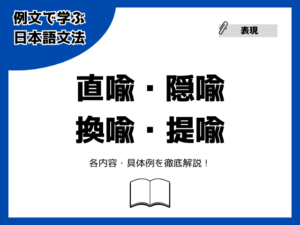
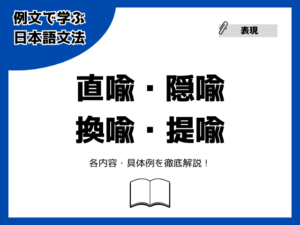
問5 前方照応
解説 現場指示・文脈指示
【現場指示】
これが、最近買った言語学の本です。
【文脈指示】
学生時代に留学生と関わる機会が多くて…それが日本語教師を目指すきっかけになりました。
解説 前方照応・後方照応
【前方照応】
学生時代に留学生と関わる機会が多くて…それが日本語教師を目指すきっかけになりました。
【後方照応】
どちらにしようか迷っていて…講座Aと講座Bなんですが…
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
正しくは、「そこ1年」ではなく「ここ1年」ですね。
発話時を基準にした現場指示の内容なので、1は間違いです。
正しくは、「そのように」ではなく「このように」ですね。
指示しているのは、後ろに続く「勉強すれば、将来豊かな生活ができる」です。
後方照応の内容なので、2は間違いです。
正しくは、「これほど」ではなく「それほど」ですね。
「それほど」の「それ」は、指示詞の色が薄れており、会話や文中に指示するものがなくても使えるので、一語で副詞として扱うのが一般的だと思います。
3は間違いです。
正しくは、「あの歌手」ではなく「その歌手」ですね。
指示しているのは、前にある「若手のオペラ歌手」です。
前方照応の内容なので、4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら