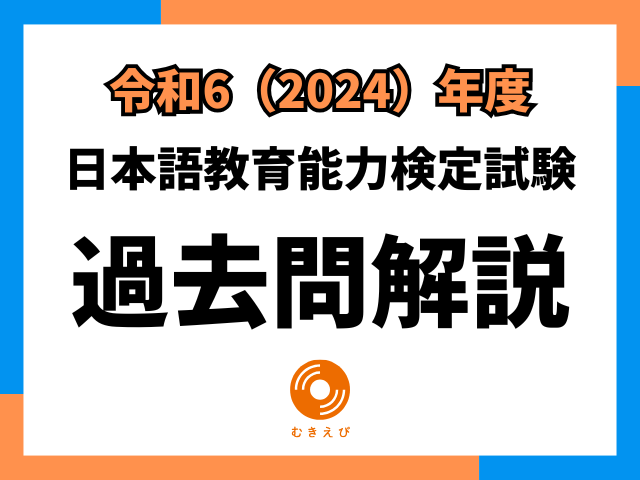令和6年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題10
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 PPP(Presentation-Practice-Production)
解説 PPP(Presentation-Practice-Production)
- Presentation(導入・提示)
- Practice(練習)
- Procuction(産出)
の略であり、
- 教師が新しい文法項目を学習者に提示し、
- 学習者が教えられた文法を練習、
- 最後に、実際にその文法項目を会話や作文をしてみる
といった内容が該当します。
解説 CBI(Contents Based Instruction)
教科学習では、数学の授業を目標言語で行う…などがCBIを取り入れた授業例です。
- 各課ごとに「教科の目標」と「言語の目標」を設定し、言語指導では教科学習に必要な語彙や表現とあわせて「学習スキル」を養成を図る。
- 4技能を統合的に取り入れる。
- 評価基準にルーブリックを活用する。
- 活動時の発問は、証拠の裏付けをしながら論理的に述べる本質的な内容が重視される。
- これらを協同学習の場で身につける。
といった特徴があります。
解説 TBLT(Task-Based Language Teaching)
「タスク中心の教授法」とも言います。
解説 TPR(Total Physical Response)
「全身反応教授法」とも言います。
その答えになる理由


「文法を重視した教授法」なので、
- 教師が新しい文法項目を学習者に提示し、
- 学習者が教えられた文法を練習、
- 最後に、実際にその文法項目を会話や作文をしてみる
という流れになる「PPP(Presentation-Practice-Production)」が最も適当ですね。
2が正解です。
問2 社会言語能力
解説 カナル&スウェインによるコミュニケーション能力(伝達能力)の分類
解説 社会言語能力
解説 文法能力
解説 ストラテジー能力
伝達が上手くいかなった際の対応の仕方
などが含まれます。
解説 談話能力
会話の切り出し方
発話の順番の取り方
などが含まれます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
言い間違いを修正してやり取りを立て直すためには、語彙や文法を正確に使用する力が必要ですね。
1は、文法能力の内容です。
自分の考えを順序立てて分かりやすく伝えるためには、発話を理解・構成する力が必要ですね。
2は、談話能力の例です。
初めて聞いた表現を理解し、それを正しく理解するためには、コミュニケーションを円滑に進める力が必要ですね。
3は、ストラテジー能力の例です。
参加者に対する敬称を正確に使い分けるためには、場面に応じて適切な表現を使用する力が必要ですね。
4は、社会言語能力の例です。
問3 コミュニカティブ・アプローチ
解説 コミュニカティブ・アプローチ
文法や文型の反復練習中心である「オーディオ・リンガル・メソッド」への批判から発展しました。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう
コミュニカティブ・アプローチでは、コミュニケーション能力の獲得・養成が目標です。
そのため、学習項目の導入で、難易度ではなく、学習者のニーズが優先されます。
1は、間違いです。
コミュニカティブ・アプローチでは、グループワークなどを通じて、目標の言語形式ではなく、意味に焦点を当てて学習していきます。
2は、間違いです。
コミュニカティブ・アプローチにおいて、母語の使用が少ない(=目標言語の使用が多い)に越したことはありませんが、母語の使用自体が禁じられているわけではありません。
3は、間違いです。
4は、何も問題ありません。
これが正解です。
問4 機能シラバス
解説 シラバス
「シラバス」は、何を基準にどんな項目を集めたかの点において
- 構造シラバス
- 機能シラバス
- 技能シラバス(スキル・シラバス)
- 場面シラバス
- 話題シラバス(トピック・シラバス)
- 課題シラバス(タスク・シラバス)
に分類されます。
解説 構造シラバス
言語を体系的に学べる一方で、実際のコミュニケーションで使う表現がすぐに学べないというデメリットもあります。
解説 機能シラバス
実際のコミュニケーションにおける運用力が身に付く一方で、基礎的な文法や言語構造を体系的に学ぶのが難しいというデメリットもあります。
解説 技能シラバス(スキル・シラバス)
「書く」であれば、「単語の書き取り→短い文章を書く→長めの文章を書く→作文を書く」のように段階化するイメージで、副教材として他のシラバスとの併用される場合が多くあります。
解説 場面シラバス
学んだことがすぐに活かせる一方で、文法を体系的に学ぶわけではないため、最初から複雑な文構造が出てくる場合もあるというデメリットもあります。
解説 話題シラバス(トピック・シラバス)
学習者のニーズ・関心と合致していれば、学習動機が教科されて高い学習効果が期待できます。
解説 課題シラバス(タスク・シラバス)
「病院の受診」であれば、「予約の電話をする→受付で症状を話す→診察してもらう」の中でそれぞれのタスクを遂行するために必要となる表現を学ぶイメージです。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう
1は、「言語形式の持っている働き」のような機能面が軸になっています。
これは、機能シラバスの内容です。
2は、「学習者の関心のあるトピック」のような学習者のニーズ・関心事が軸になっています。
これは、話題シラバス(トピック・シラバス)の内容です。
3は、「特定の状況でよく使われる会話」のような場面が軸になっています。
これは、場面シラバスの内容です。
4は、「学習者の生活や仕事で必要とされる言語技能」のような技能面が軸になっています。
これは、技能シラバス(スキル・シラバス)の内容です。
問5 第二言語不安を緩和するために有効な教師の対応
解説 第二言語不安
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう
学習者同士で競い合いを行うことは、第二言語不安を増大させる可能性がありますね。
1は、間違いです。
学習者の能力を正しく評価・支援することにより、第二言語不安が減少していきますね。
2は、正しいです。
学習者に多くの課題を与えて緊張感を構築することは、第二言語不安を増大させる可能性がありますね。
3は、間違いです。
個人差を排除し、どの学習者にも共通した対応をすることは、第二言語不安を増大させる可能性がありますね。
4は、間違いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら