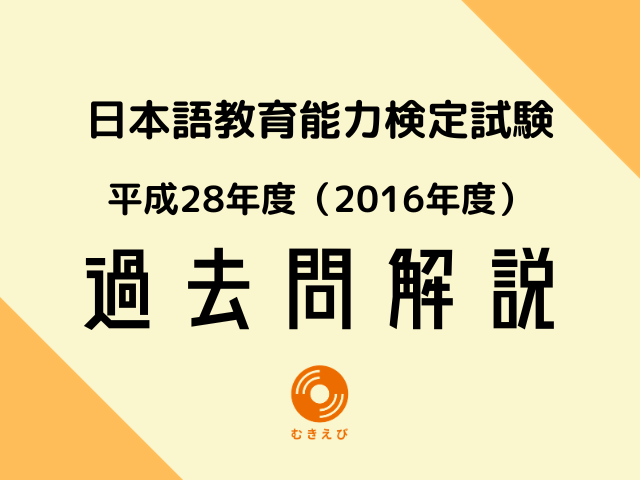平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題12
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 サピア・ウォーフの仮説
令和2年度試験でも出題された「サピア・ウォーフの仮説」の問題です。
出題形式も同じで、用語の意味がそのまま出てきています。
解説 サピア・ウォーフの仮説 言語相対論
「サピア・ウォーフの仮説」とは、「ある言語と、その言語を母語とする人の考え方・物の見方には、何らかの関わりがあるという考え方」のことです。
提唱者のサピアとウォーフの名を取ってそう呼ばれていますが、「言語相対論」の名称で扱われることもあります。
多くの場合、人の考え方・物の見方は母語の影響を受けています。
そのため、「サピア・ウォーフの仮説」では人の考え方・物の見方は全て同じではなく、それぞれの母語によって違うものとしています。
その答えになる理由


「『言語』と『その言語を母語とする人の考え方・物の見方』には何らかの関係がある」というのが「サピア・ウォーフの仮説」です。
「物の見方」=「認知」ですね。
3が正解です。
問2 単純語レベルでの区別
「単純語」とは、1つの自由形態素(=単独で語になれるもの)でできていて、それ以上分けることができない語のことです。
2つ以上の語が組み合わさると「合成語」になります。
その答えになる理由


下線部の前部分も読まないと解けない問題です。
例として挙げられている「コメ」は、英語だと状態に関係なく「rice」ですが、日本語だと「イネ(植わっている状態)」「コメ(収穫された状態)」「メシ(調理された状態)」と同じものの名称が変わります。
他には「water」なんかも同じ例ですね。
英語だと温度に関係なく「water」ですが、日本語では「水(冷たい状態)」「お湯(温かい状態)」と同じものの名称が変わります。
例と同様に、同一のものを指しているが、状態によって呼び方が変わるものを探しましょう。
「単純語レベル」なので、複合語だとNGだということに注意してください。
「雲」は、形状によって「飛行機雲」「雨雲」「雷雲」のように呼び方が変わりますが、いずれも複合語ですね。
1は間違いです。
「牛」は、家畜としての用途に応じて「肉牛」「乳牛」のように呼び方が変わりますが、いずれも複合語ですね。
2は間違いです。
「魚」の中では、ブリやボラ、スズキなどが出世魚として有名ですね。
大きさによって
モジャコ→ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ
のように名称が変化します。
いずれも単独語なので、3が正解です。
出世魚の呼び方は、方言と紐づいていて地域によって異なります。
興味のある方は調べてみてください。
「火」は、用途に応じて「たき火」「送り火」のように呼び方が変わりますが、いずれも複合語ですね。
4は間違いです。
問3 英語と日本語で区別の仕方が異なる親族名称の例
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
母は「mother」、娘は「daughter」ですね。
日本語と英語で区別の仕方が同じなので、1は間違いです。
母は「mother」、義母は「mother-in-low」ですね。
義母は「法律上の」という意味がくっついていますが、「母」「mother」で表すことには変わりありません。
日本語と英語で区別の仕方が同じなので、2は間違いです。
息子は「son」、娘は「daughter」ですね。
日本語と英語で区別の仕方が同じなので、3は間違いです。
「兄」も「弟」も英語では「brother」です。
日本語と英語で区別の仕方が異なるので、4が正解です。
問4 日本語の慣用句で用いられる色彩語に関する記述
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「黒いうわさ」「腹黒い」のように。「黒」は悪いことを意味します。
1は例として適当です。
「赤字」「赤信号」のように、「赤」は危険を表す色としてよく使われます。
「明るい前途」はイメージがつかないですね。
2が正解です。
「青二才」「青春」のように、「青」は未熟なさまを意味します。
3は例として適当です。
「灰色な未来」と聞くと、なんだか前途多難な暗い感じがしますね。
4は例として適当です。
問5 忌み言葉
解説 忌み言葉
「忌み言葉」とは、不吉な意味・連想を持つことから、場面によっては使用を避ける言葉のことです。
結婚式の場で「去る」「切る」等の語を避けてスピーチをすることなどが該当します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「故人を偲ぶ」は、葬儀の場面では適切な表現ですね。
1は間違いではありません。
「善処する」は、実質「やらない」なので、不適切と言えば不適切ですが…。
場面に合っていないわけではないので、2は間違いではありません。
「お開きにする」は「解散する」という意味で「終わり」を連想させます。
宴会の場面ではあまり適切でないですね。
3が正解です。
ちなみに、披露宴では「お開き」を「お披楽喜」のように表現して忌み言葉ではなくすようにすることもあるそうです。
なんだか暴走族みたいですね…!!
「慚愧に堪えない」とは、「恥じ入っていること」を意味します。
政治家が使うと「自身の言動について、恥ずかしく思っている」ですね。
場面にあった表現なので、4は間違いではありません。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら