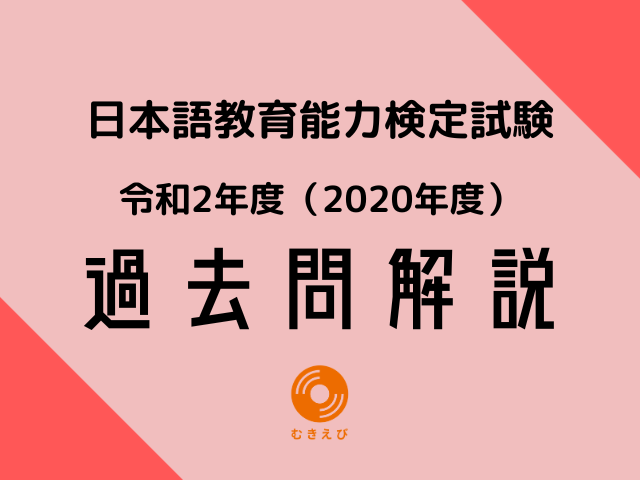令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題12
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 サピア・ウォーフの仮説 言語相対論
解説 サピア・ウォーフの仮説 言語相対論
提唱者のサピアとウォーフの名を取ってそう呼ばれていますが、「言語相対論」の名称で扱われることもあります。
多くの場合、人の考え方・物の見方は母語の影響を受けています。
そのため、サピア・ウォーフの仮説では、人の考え方・物の見方は全て同じではなく、それぞれの母語によって違うものとしています。
その答えになる理由


4が「サピア・ウォーフの仮説」の内容そのままですね。
これが正解です。
問2
その答えになる理由


傍線部の「色彩や気候に関する語彙は」の部分は、ただの例なので無視して構いません。
ポイントは「事象の切り取り方」の部分です。
「他の言語だと切り分けていないが、日本語だと切り分けている事象」の例を探す問題なので、1・2・4は、的外れな選択肢であることがわかります。
英語だと「男の兄弟」はbrotherですが、日本語だと生まれた順番によって「兄」「弟」と区別していますね。
同じ事象が言語によって切り分け方が異なる例なので、3が正解です。
問3 一般化
解説 一般化
ご飯
米を炊いたもの → 食事全般
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「瀬戸物」は、もともとは愛知県の瀬戸地域での陶磁器を指していましたが、一般化して、陶磁器全般を指すようになりました。
1が正解です。
「卵雑炊」は、時代に関係なく、卵を入れた雑炊を指しています。
2は、間違いです。
「桜吹雪」は、「桜の花びらが吹雪のようにたくさん舞い散ること」を表す比喩表現です。
「ような」などを使わずに例えているので、隠喩(メタファー)の例ですね。
3は、間違いです。
「親子丼」は、「親(=卵の親=鶏)」「子(=鶏の子=卵)」を表す比喩表現です。
それぞれ、上位概念で下位概念を表しているので、提喩(シネクドキー)の例ですね。
4は、間違いです。
問4 忌み言葉
解説 忌み言葉
するめ → あたりめ
博打でお金がなくなる意味の「擦る」や、財布などを盗む意味の「掏る」を連想して縁起が悪いことから、「当たり」に言いかえられています。
その答えになる理由


3が「最後になりますが」という忌み言葉を避けた表現ですね。
これが正解です。
そのほかは、場面に応じた適切な表現であり、忌み言葉ではありません。
問5 混種語
解説 和語
主に
- ひらがなの語
- 訓読みの漢字
- 助詞・助動詞
などが和語に分類されます。
解説 漢語
主に
- 音読みの漢字
が漢語に分類されます。
解説 外来語
外来語は、近世以降、主に欧米の諸言語から新たな事物や概念として取り入れられたもので
- カタカナで表記されることが多い
- 新しい文化とともに取り入られるため、洗練された印象を与える
- 多用すると、意思疎通に支障が出る場合も…
という特徴があります。
解説 混種語
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 中華(漢語) + ソバ(和語)
2 窓(和語) + ガラス(外来語)
3 長(和語) + ズボン(外来語)
4 生(和語) + ビール(外来語)
となり、ほかと語種の組み合わせが異なるのは、1ですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら