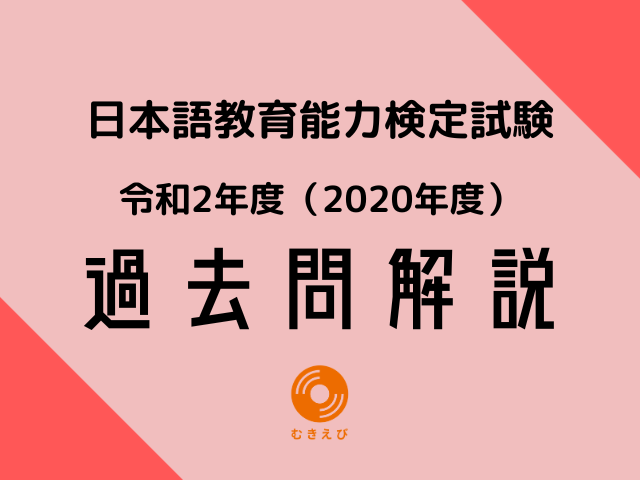令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題13
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 統語
解説 統語
その答えになる理由


文章中で、コミュニケーション上の行き違いの例として
- 音韻レベル … 発音やアクセントが原因のミス
- 統語レベル … 句・節・文の配置が原因のミス
- 意味レベル … (音韻・統語は合っているが)内容の捉え方が原因のミス
が挙げられています。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、「あれ取って」自体にミスはないものの、指示詞の内容を取り違えています。
これは、意味レベルでの誤解です。
2は、「『小さな猫』の声」なのか「小さな『猫の声』」なのかの表現を取り違えています。
これは、語の配置のひとまとまりがどこまでかによるものであり、統語レベルでの誤解です。
3は、/wa/を/na/に取り違えています。
これは、音韻レベルでの誤解です。
4は、「結構です」自体にミスはないものの、それがどのような回答なのかを取り違えています。
これは、意味レベルでの誤解です。
問2 高コンテクスト
解説 高コンテクスト
この場合、コンテクスト(文脈)から得られる情報が多いため、相対的に言語そのものへの依存度が低くなります。
解説 低コンテクスト
この場合、コンテクスト(文脈)から得られる情報が少ないため、相対的に言語そのものへの依存度が高くなります。
その答えになる理由


- コンテクスト(文脈)への依存度が高い
- コンテクスト(文脈)から得られる情報が多いので、言語そのものへの依存度は低い
のが高コンテクスト文化の特徴です。
選択肢を見てみると…
「個人間で共有された情報・経験を前提に」からコンテクスト(文脈)への依存度が高いことがわかりますね。
1が正解です。
2~4は、発話した言語の内容そのものへの依存度が高いので、低コンテクスト文化の内容になっています。
問3 否定応答
その答えになる理由


文章中に
- 肯定応答
- 否定応答
- 回避
という語があるので、整理しやすいのではないかと思います。
今日のヘアスタイルすてきですね。
に対して、
そうなんです。昨日美容院に行ってきて…
であれば、肯定応答
そんなことないですよ。Aさんの方が…
であれば、否定応答
ありがとうございます。ところで…
であれば、回避が応答として選択されています。
相手の発話を
- 受け入れている
- 受け入れていない
- 受け入れる・受け入れないの選択を避けている
のいずれに当たるかがポイントです。
選択肢を見てみると…
4のみ否定応答で、そのほかは肯定応答ですね。
4が正解です。
問4 逸脱
解説 社会言語学
「文法的には合っているが、場面には合っていない」という場合は、社会言語学的には逸脱が起きていると言えます。
その答えになる理由


選択肢が小難しく書いてあるので、身構えてしまいますね。
傍線部の前に「円滑なコミュニケーションを目指して」とあるので、「円滑なコミュニケーションにするために、非母語話者(学習者)が言い間違いをしたときに、どのように対応するか」がポイントです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1では、非母語話者とのコミュニケーション維持が難しいときに、
- 自身の発話を簡単なものにする
- 非母語話者の発話を聞き返す
という対応をとることが述べられています。
これは、正しい対応方法です。
2では、非母語話者の日本語に誤りがあるときに、
- 相づちにより非母語話者が発話しやすいようにする
- 非母語話者の発話を先取りしてサポートする
という対応をとることが述べられています。
これは、正しい対応方法です。
3では、非母語話者が場面に合っていない言い間違いをするときに、
- 「間違っていますよ」「●●の方が良いですよ」という否定的な評価をしない
ことが述べられています。
言い方は気をつけなければなりませんが、正しい内容ではありません。
4では、非母語話者が言い間違いをしたとしても、
- 大きな問題が起きないのであれば、重要なミスではない
と捉えることが述べられています。
これは、正しい対応方法です。
選択肢の内容を簡易な表現に置き換えてみると、そこまで難しく感じないですね。
3が間違いです。
問5 意味交渉
解説 意味交渉
その答えになる理由


選択肢を見てみると…
1・3・4は、相手の発話に対してボールを投げ返しているだけです。
2は、相手の発話の解釈が合っているかを確認しています。
2が意味交渉の例として適当ですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら