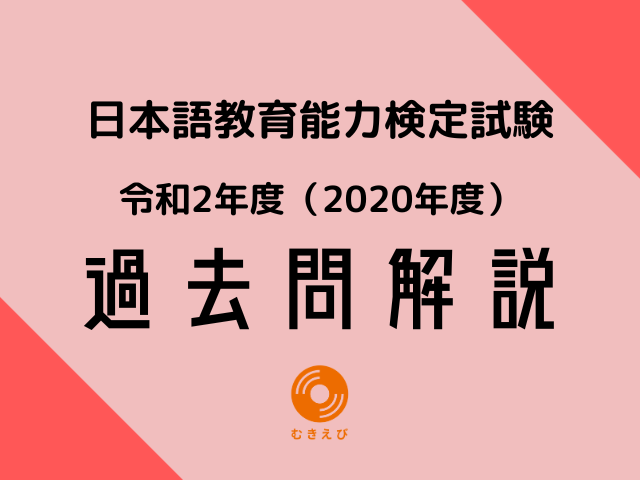令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題11
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 外来語
その答えになる理由


それぞれが日本の何時代にあたるかを見てみましょう。
- 6世紀半ばから17世紀初め … 安土桃山時代
- 18世紀から19世紀半ば … 江戸時代 中期~後期
安土桃山時代に行われていたのは、南蛮貿易です。
ここでの南蛮とは、「スペイン」「ポルトガル」が該当します。
江戸時代 中期~後期と言えば、鎖国ですね。
キリスト教の布教を禁じるために、貿易を「オランダ」「中国」に限定しました。
(ア)(イ)どちらも正しい答えになるのは、3です。
問2 アイヌ語
その答えになる理由


アイヌなので、北海道の地名ですね。
青森県の地名である3と4は、この時点で間違いです。
アイヌの人々は、川や沢を非常に大事にしていました。
そのため、アイヌ語で川を指す「ペッ」・沢を指す「ナイ」は今でも地名に残っている場合が多いです。
読み方まで覚える必要はありませんが、「川」や「沢」にはアイヌ語特有の音があることがわかっていれば、1の「旭川」を除外できますね。
2が正解です。
ちなみに、私はこの辺りの知識は「ゴールデンカムイ」というマンガで覚えました。
問3 ダイグロシア 二言語変種併用社会
解説 ダイグロシア 二言語変種併用社会
ダイグロシアの状態で使われる言語形式は、「高変種」「低変種」と呼ばれています。
解説 高変種
解説 低変種
その答えになる理由


2が「ダイグロシア」の内容そのままですね。
これが正解です。
問4 リンガフランカ 共通言語
解説 リンガフランカ 共通言語
その答えになる理由


1が「リンガフランカ」の内容そのままですね。
これが正解です。
問5 クレオール ピジン
解説 ピジン
植民地地域で支配国の言語を簡略化して使用されたものが多くあります。
解説 クレオール
その答えになる理由


「ピジン」「クレオール」それぞれの用語がわかっていれば、3が明らかに間違いだとわかります。
共通言語として使用される以上、体系的な文法構造ができあがっているはずですね。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら