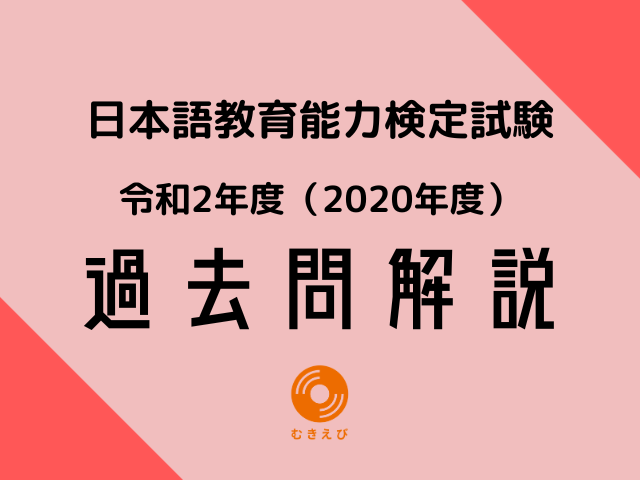令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題10
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 スキーマ
解説 スキーマ
…ピンとこないですよね。
動詞の「タ形」であれば、
食べる → 食べた
見る → 見た
の事例から「語幹+タ」のスキーマが抽出できる…といったイメージです。
具体的な事例から、抽象的な法則や枠組みを抽出した際の「法則」や「枠組み」がスキーマに当たります。
解説 レキシーム 語彙素
…これも、ピンとこないですよね。
日本語であれば、
行く (辞書形)
行って (テ形)
行った (タ形)
などは、形は異なりますが、全て「行く」という同じ語です。
これらは、全て「行く」のレキシーム(語彙素)であると言えます。
その答えになる理由


一般的に、「ボクシング選手は、女性よりも男性が多い」という認識があるのではないでしょうか?
例文が「彼」ではなく「彼女」だと読み時間が長くなるのは、「ボクシング選手は、女性よりも男性が多い」という脳内の枠組みに当てはまらないものだからです。
(ア)には、「スキーマ」が入ります。
(イ)については、「ボクシング選手」と「彼女」の語の関係で考えてみましょう。
例文では、「ボクシング選手」を言い換えた語が「彼女」ですね。
語と語を結びつけているので、(イ)には「結束」が入ります。
ちなみに、包摂関係とは、
木
∟ カエデ
∟ イチョウ
鳥
∟ スズメ
∟ カラス
などの関係のことです。
問2 精緻化推論
解説 精緻化推論
主に読解後に行われるのが特徴です。
文章を理解したあとに推理します。
解説 橋渡し推論
主に読解中に行われるのが特徴です。
文章を理解するために推理します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
原因・結果などの関係づけを行うのは、主に読解中ですね。
文章を理解するために行う推論です。
1は、橋渡し推論が該当します。
未知語の意味を推測するのは、主に読解中ですね。
文章を理解するために行う推論です。
2は、橋渡し推論が該当します。
文章の大意を把握するのは、主に読解中ですね。
文章を理解するために行う推論です。
3は、橋渡し推論が該当します。
文章に書かれていないその後の展開を予測するのは、主に読解後ですね。
文章を理解したあとに行う推論です。
4は、精緻化理論が該当します。
問3 照応
解説 照応
「佐藤さん、日本語教育能力検定試験に合格したらしいよ」
「良かった。彼、毎日勉強していたもんね」
であれば、「佐藤さん = 彼」で照応しています。
その答えになる理由


「彼女 = ボクシング選手」が照応の内容ですね。
2が正解です。
問4 メトノミー
解説 直喩 シミリー
見ろ!人がゴミのようだ!
隠喩(暗喩)とペアにして、明喩と呼ばれることもあります。
解説 隠喩 メタファー
目の前が真っ暗になった。
記憶が飛んだ。
直喩(明喩)とペアにして、暗喩と呼ばれることもあります。
解説 換喩 メトニミー
風呂が沸いた。
は、「風呂(浴槽)」そのものが沸いたのではなく、「風呂の中の水」が沸いたことを表しています。
解説 提喩 シネクドキー
花見に行く。
では、上位概念「花」が、下位概念「桜」を表しています。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
飲み干したのは、「ジョッキそのもの」ではなく、「ジョッキの中に入っている飲み物」ですね。
「飲み物」を隣接関係にある「ジョッキ」で表しています。
1は、メトニミーの例です。
「花見」で見に行くのは、タンポポやパンジーではなく、「桜」ですね。
上位概念「花」で下位概念の「桜」を表しています。
2は、シネクドキーの例です。
「破った」は、約束という形のないものを契約書のような形のあるものに例えています。
「ような」などを使っていないので、3は、メタファーの例です。
パンの端の部分を動物の「耳」に例えています。
「ような」などを使っていないので、4は、メタファーの例です。
比喩の種類については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもあわせてご確認ください。
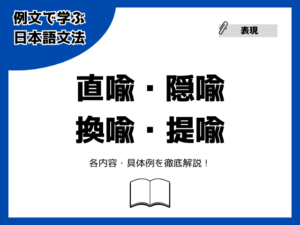
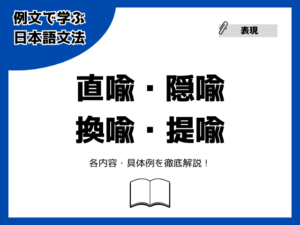
問5 理解補償方略
その答えになる理由


参考はこちら
「理解補償方略」という用語は、初見でした。
調べてみたら、犬塚美輪先生の論文から来ているんですね。
著書は拝読したことがあるのですが、恥ずかしながら、この論文は読んだことがありませんでした。
設問からヒントを得ながら、問題にチャレンジしてみましょう。
今回のように、
- 理解補償方略
- 内容理解方略
- 理解深化方略
と似た用語が並んでいるときは、ダミーの選択肢は、ほかの用語を指していることがほとんどです。
選択肢を見てみると…
1は、文章の内容自体を理解するための行動です。
これは、内容理解方略が該当します。
2は、内容はわかったうえで文を要約するための行動です。
これは、理解深化方略が該当します。
3は、内容の全体観はわかった上での個別部分を埋めるための行動です。
これは、理解補償方略が該当します。
4は、1と同じく文章の内容自体を理解するための行動です。
これは、内容理解方略が該当します。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら