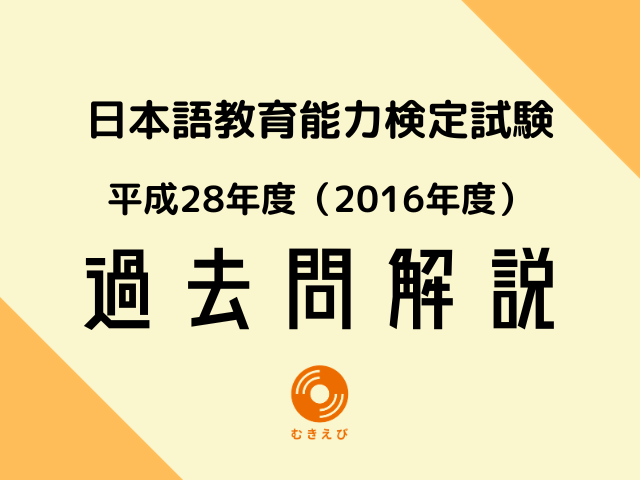平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題13
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 フェイス
まずは、用語の意味を順に確認していきましょう。
解説 ポライトネス理論
「ポライトネス理論」とは、ブラウン&レビンソンが提唱した「ポライトネス」と「フェイス」を鍵概念として、コミュニケーションにおいて人間関係を円滑にするための言語的な工夫・方法を考察する理論のことです。
【令和3年度試験 試験Ⅲ 問題14 問1】
【令和2年度試験 試験Ⅲ 問題14 問2】
【令和元年度試験 試験Ⅲ 問題12 問3】
でも出題されています。
解説 ポライトネス
「ポライトネス」とは、会話の参加者が心地よくなるようにするなど、人間関係を円滑にするための言語活動のことです。
解説 フェイス
「フェイス」とは、人と人との関わり合いに関する基本的な欲求を指します。
他者に近づきたい・好かれたいという「ポジティブフェイス」と、他者と離れていたい・立ち入られたくないという「ネガティブフェイス」に分類されます。
その答えになる理由


ポライトネス理論における「フェイス」とは、人と近づきたい⇔離れていたいという「欲求」のことです。
1が正解です。
ちなみに、2の「信念」も「ビリーフ」という用語でよく出題されています。
問2 ポライトネス理論
その答えになる理由


下線部の内容が「ポライトネス理論」の内容そのままですね。
3が正解です。
問3 「ポジティブフェイス」への配慮の例
その答えになる理由


「ポジティブフェイス」は「他者に近づきたい・受け入れてもらいたい」という欲求のことです。
そのため、「ポジティブフェイスの配慮」とは「どのようにしたら、その人ともっとお近づきになれるか…」という言動のことを指しています。
1・2・4は相手と距離を置こうとしているので、「ネガティブフェイスへの配慮」ですね。
3が正解です。
問4 「フェイス」への配慮よりも伝達の効率性が優先される場合
その答えになる理由


「もっとお近づきになりたい」「もっと距離をあけておきたい…」という気持ちよりも、効率性が優先されるものを探しましょう。
3が正解です。
問5 フェイスの侵害の度合い
令和3年度試験と同じ形式ですね。
フェイスの侵害の度合いを「FTA」と呼びます。
解説 FTA face-threatening act
「FTA」とは、人間の基本的欲求であるフェイス(ポジティブ・フェイス / ネガティブ・フェイス)を他者が脅かすような言語的な行動のことです。
(ファイスを脅かさないようにすることが「ポライトネス」であると言えます。)
FTAの度合いは
●特定の行為の負荷の度合い(Rank)
●相手との社会的距離(Distance)
●相手との相対的権力(Power)
の3つの総和によって決まるとされています。
数式自体が出ることは考えにくいので、「FTAの度合いは、上記の3つの総和で決まる」レベルまで覚えておけば良いと思います。
FTA度合いの見積もり公式:Wx=D(S,H1)+P(H,S)+Rx
Wx:ある行為xが相手のフェイスを脅かす度合い(Weight)
大塚 生子 「ポライトネス理論におけるフェイスに関する一考察」
D(S,H):話し手と聞き手の社会的距離(Distance)
P(S,H):話し手と聞き手の相対的権力(Power)
Rx:ある行為xの、ある文化における押しつけがましさの程度の絶対的な順位付け(Rank)
その答えになる理由


1 相手との相対的権力(Power)
2 相手との社会的距離(Distance)
3 特定の行為の負荷の度合い(Rank)
4が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら