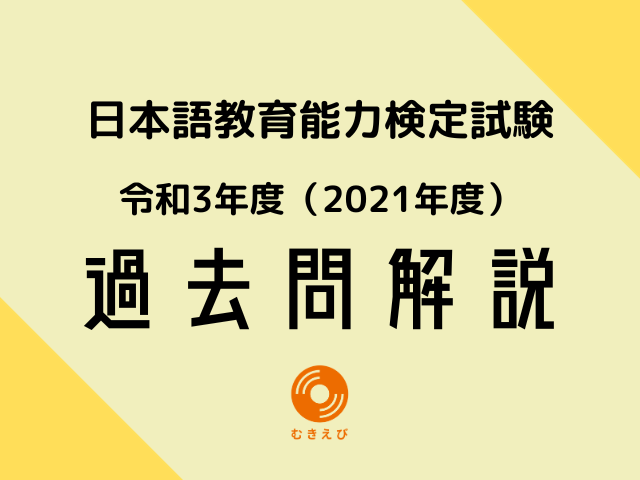令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題14
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 フェイス
解説 ポライトネス理論
解説 ポライトネス
解説 フェイス
他者に近づきたい・好かれたいという「ポジティブ・フェイス」と、他者と離れていたい・立ち入られたくないという「ネガティブ・フェイス」に分類されます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「ポジティブ・フェイス」は、立場をわきまえて行動したいという欲求ではなく、他者に近づきたい・好かれたいという欲求のことです。
1は、間違いです。
行為回避を行うのは、相手のフェイスを侵害するリスクが高い場合です。
2は、間違いです。
フェイスへの配慮が必要かどうかは、文化によってではなく、相対する人によって決まります。
3は、間違いです。
4は、何も問題ありません。
これが正解です。
問2 FTA face-threatening act
解説 FTA face-threatening act
FTAの度合いは
- 特定の行為の負荷の度合い(Rank)
- 相手との社会的距離(Distance)
- 相手との相対的権力(Power)
の3つの総和によって決まるとされています。
Wx:ある行為xが相手のフェイスを脅かす度合い(Weight)
D(S,H):話し手と聞き手の社会的距離(Distance)
P(S,H):話し手と聞き手の相対的権力(Power)
Rx:ある行為xの、ある文化における押しつけがましさの程度の絶対的な順位付け(Rank)FTA度合いの見積もり公式:Wx=D(S,H1)+P(H,S)+Rx
大塚 生子
「ポライトネス理論におけるフェイスに関する一考察」
数式自体が出ることは考えにくいので、「FTAの度合いは、上記の3つの総和で決まる」レベルまで覚えておくようにしましょう。
その答えになる理由


選択肢の内容は、それぞれ
2 特定の行為の負荷の度合い(Rank)
3 相手との相対的権力(Power)
4 相手との社会的距離(Distance)
が該当します。
残った1が正解です。
問3 謙譲語Ⅰ
敬語の種類を確認しておきましょう。
敬語の指針では、敬語を以下の5つに分類しています。
解説 尊敬語
いらっしゃる
お忙しい
~られる
などが該当します。
解説 謙譲語Ⅰ
申し上げる
伺う
(立てる相手への)お手紙
などが該当します。
解説 謙譲語Ⅱ(丁重語)
参る
申す
いたす
などが該当します。
解説 丁寧語
です
ます
などが該当します。
解説 美化語
お料理
お手紙
などが該当します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「伺う」は、話し手から先生に向かう行為で、先生を立てて述べています。
1は、謙譲語Ⅰです。
「参る」は、話し手の行為を聞き手に対して丁重に述べています。
2は、謙譲語Ⅱ(丁重語)です。
「いたす」は、話し手の行為を聞き手に対して丁重に述べています。
3は、謙譲語Ⅱ(丁重語)です。
「申す」は、話し手の行為を聞き手に対して丁重に述べています。
4は、謙譲語Ⅱ(丁重語)です。
問4 二重敬語
解説 二重敬語
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
案内 → ご案内
する → 申し上げる
それぞれの語を敬語にしているだけですね。
1は、二重敬語ではありません。
聞く → 伺う
くれる → くださる
それぞれの語を敬語にしているだけですね。
2は、二重敬語ではありません。
言う → おっしゃる
とすべきところが、さらに尊敬表現の「~られる」をつけて加えています。
1つの語に尊敬語を二重に使っているので、3が正解です。
話す → お話しになる
いる → いらっしゃる
それぞれの語を敬語にしているだけですね。
4は、二重敬語ではありません。
問5 語用論的指導
解説 語用論
寒いですね。
は「体感の気温が低いこと」について相手に同意を求める内容ですが、窓が開いている部屋の中で発話された場合には、
窓を閉めてほしい
窓を閉めてもよいか?
という捉え方をすることができます。
このように、特定の文脈や状況の中での発話の解釈を扱うのが「語用論」です。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
(雪が降っている中を一緒に歩きながら)
寒いですね。
(窓から冷たい空気が入ってきている部屋の中で、窓の傍にいる人に対して)
寒いですね。
では、言語形式は「寒いですね」で共通しているものの、社会的・状況的文脈の関係によって意味が変わってきます。
この違いを学習者に記述させ、気づきの機会を与えることは、語用論的指導として有効ですね。
1は、適当な内容です。
フィードバックの際に誤りに対する訂正を避けてしまうと、その場での学習者の発話意欲は向上するかもしれませんが、語用論的な気づきを得る機会としてはマイナスですね。
2は、不適当な内容です。
(窓から冷たい空気が入ってきている部屋の中で、窓の傍にいる人に対して)
寒いですね。
という表現は、相手によっては意図が伝わりにくかったり、逆に遠回しな嫌味に聞こえてしまったりします。
意図の伝達と対人関係における配慮のバランスが必要ですね。
3は、適当な内容です。
- 語用論的規範
- 発話行為の談話構造
- 丁寧度の調整
などがフワッとしていると、意図が正しく伝わらなかったり、相手にとって失礼な物言いになったりしてしまいます。
これらは、明示的に教えていくことが必要ですね。
4は、適当な内容ですね。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら