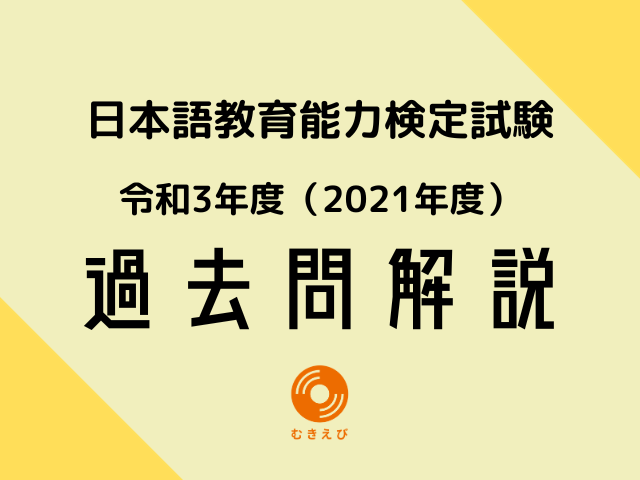令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題15
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 公的な支援
その答えになる理由


インドシナ難民定住促進事業が開始されたのは、「1979年」です。
1は間違いです。
外国人技能実習制度による受け入れが開始されたのは、「1993年」です。
2は間違いです。
中国人孤児定着促進センターの運営が開始されたのは、「1984年」です。
3が正解です。
日系南米人に対する「虹の架け橋教室」事業が開始されたのは、「2009年」です。
4は間違いです。
問2 令和元年度夜間中学校等に関する実態調査
その答えになる理由


出典元はこちら
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
P18より、外国籍(=日本国籍を有しない者)の生徒数は1,384人で、夜間中学に通う生徒1,729人中の80%を占めています。
1は、正しいです。
P19より、ブラジル籍の生徒数は、1,384人中の21人で全体の1.5%です。
2は、間違いです。
P18より、外国籍の生徒の年齢は、1,384人中の314人で全体の22.7%を占める「20~29歳」が1番多いです。
3は、間違いです。
P20より、外国籍の生徒の入学理由は、1,384中の654人で全体の47.3%を占める「日本語が話せるようになるため」が1番多いです。
4は、間違いです。
問3 銀行型教育
解説 銀行型教育
ブラジルの識字運動を実践したフレイレは、どれだけ多くの知識を「貯蓄」したかが評価される状態を「銀行型教育」として批判し、新たに「問題提起型教育」という概念を主張しています。
解説 問題提起型教育
その答えになる理由


フレイレを知っているかどうかですね。
4が正解です。
問4 意識化
解説 意識化
フレイレが識字教育を実践する中で提唱した概念で、単なる暗記教育(=銀行型教育)は記憶学習に過ぎず、現実を告発して変革しようとする教育のあり方(=問題提起型教育)が必要だとしています。
その答えになる理由


4が上記解説に1番近い内容ですね。
これが正解です。
問5 課題提起型日本語教育
その答えになる理由


フレイレの「問題提起型教育」を日本語教育に取り入れたのが「課題提起型日本語教育」です。
問3・4の内容を踏まえると……
「対話」「対等な関係」がキーワードになっている1が良さそうですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら