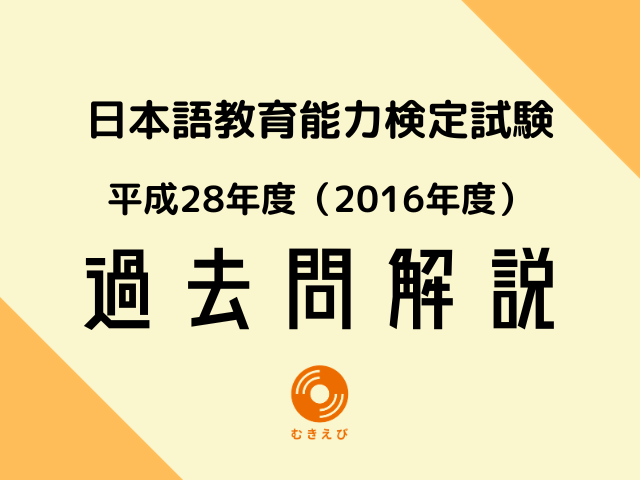平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題4
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 ハ行点呼音
解説 ハ行点呼音
ハ行の子音は、もともと [p]などの唇音 であったのではないかと推定されています。
濁音であるバ行に対する清音として、「声帯振動の有無」で対立する [p] の音を想定すると理論的に整合性が取れること
ハ行音を表すのに使われている万葉仮名としての漢字を見ると、両唇破裂音[p] [b] あるいは唇歯摩擦音[f] を頭子音に持つものばかりであること
東北・山陰・南九州・琉球の諸方言において、ハ行子音に[p]や[Φ]が対応すること
などが根拠です。
もともとは 唇音[p] であったと推定されるハ行音は、橋本新吉の「p音考」によれば、奈良時代には [Φ]に変化したとされています。
(858年の「在唐記」の記述が根拠になっています。)
その後、平安時代に「語頭以外のハ行音がワ行音で発音」されるようになりました。
この現象のことを「ハ行点呼」と言います。
川 [kaΦa] → [kawa]
のように語頭以外のハ行音はワ行音で発音されるようになりましたが、
箸 [Φaɕi] → [Φaɕi]
のように語頭のハ行音は [Φ] のまま発音されていたとされています。
その答えになる理由


上記解説より、もともとハ行音は [p] で発音されていたと考えられています。
[p] 無声両唇破裂音
なので、1が正解です。
問2 ハ行点呼音
その答えになる理由


上記解説より、語頭以外のハ行音がワ行音で発音されるようになった現象を「ハ行点呼」と言います。
2が正解です。
問3 ハ行・バ行の調音点・調音法
その答えになる理由


日本語のハ行音は
[h] 無声声門摩擦音 → ハ・へ・ホ
[ç] 無声硬口蓋摩擦音 → ヒ
[Φ] 無声両唇摩擦音 → フ
で表されます。
バ行音は全て
[b] 有声両唇破裂音
で表されるので、声帯振動の有無だけでなく、調音点・調音法も違いますね。
(ウ)に入るのは「調音点と調音法」です。
また「は」「ひ」「ふ」の音声記号を確認すると、調音法は共通して「摩擦音」ですが、調音点はそれぞれで違うことがわかります。
(エ)に入るのは「調音法」です。
3が正解です。
問4 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示)
その答えになる理由


出典元がなくなってしまっているため、執筆段階での内閣告示をもとに解説していきます。
この仮名遣いは,「ホオ・ホホ(ホホ)」「テキカク・テッカク(的確)」のような発音にゆれのある語について,その発音をどちらかに決めようとするものではない。
文化庁HP
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 現代仮名遣い > 前書き
1は間違いです。
この仮名遣いは,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。
文化庁HP
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 現代仮名遣い > 前書き
2は間違いです。
この仮名遣いは,擬声・擬態的描写や嘆声,特殊な方言音,外来語・外来音などの書き表し方を対象とするものではない。
文化庁HP
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 現代仮名遣い > 前書き
3は間違いです。
この仮名遣いは,主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによる必要のあるもの,固有名詞などでこれによりがたいものは除く。
文化庁HP
HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 内閣告示・内閣訓令 > 現代仮名遣い > 前書き
選択肢3の内容+上記により、4が正解です。
問5 日本語の発音と表記に関する記述
その答えになる理由


「ハ行点呼」がどのようなものなのかがわかっていれば楽勝ですね。
1が正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら