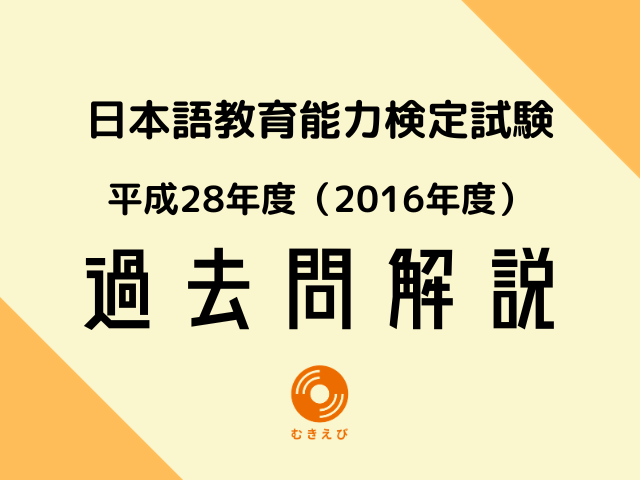平成28年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題1
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
(1)調音法
日本語教育能力検定試験のトップバッターの問題は、例年「音声記号」です。
これは、私が過去問を持っている「平成26年度試験」から変更ありません。
試験Ⅰ 問題1は、【 】に示した観点から見て他と性質の異なるものを選ぶ問題です。
(1)であれば、今回の【調音法】以外にも、子音では【調音点】・母音では【唇のまるめ】などが出題されています。
音声記号の知識は、試験Ⅱ 問題3 の8問でも活きてきます。
しっかりと得意分野にしていきましょう。
その答えになる理由


1 [ɸ] 無声両唇摩擦音
2 [ç] 無声硬口蓋摩擦音
3 [s] 無声歯茎摩擦音
4 [ɾ] 有声歯茎弾き音
5 [θ] 無声歯摩擦音
4だけが「弾き音」で調音法が違いますね。
これが正解です。
それぞれ、日本語の子音で該当するものを見ていくと
1 フ・ファ・フェ・フォ
2 ヒ・ヒャ・ヒュ・ヒョ
3 サ・ス・セ・ソ・スィ
4 ラ・リ・ル・レ・ロ
5 該当なし
です。
[θ]は日本語の子音にない音ですが、thinkの発音が思い出せれば摩擦音だとわかります。
(2)「~年(ねん)・~月(がつ)を付けた場合の読み方
その答えになる理由


難しく考えず、問題文の通りに「~年(ねん)」「~月(がつ)」を付けて読み方を見てみましょう。
1 にねん・にがつ
2 よねん・しがつ
3 ろくねん・ろくがつ
4 はちねん・はちがつ
5 じゅうねん・じゅうがつ
2だけ「~年(ねん)」「~月(がつ)」を付けたときに読み方が変わりますね。
これが正解です。
こういった数詞で読み方が変わるものは、母語話者は意識せずに話していますが、学習者は混乱しがちな分野です。
日頃から「そう言えば、何でなんだろう…?」とアンテナを張っておくようにしましょう。
(3)接辞の付加に伴う品詞変化
文法用語が来ると身構えてしまうかもしれませんが、問題自体は難しくありません。
先に用語の意味を確認しておきましょう。
解説 語基(語幹)
「語基」とは、語の構成上の根幹としていろいろな活用においても変化しない部分のことです。
「走る」であれば {hashi}が該当します。
国語では「語幹」として習っていると思うので、こちらの呼び名の方が馴染み深いかもしれません。
解説 接辞
「接辞」とは、単独で用いられることはなく、語基(語幹)に接続して文法機能などを表す部分のことです。
「走る」であれば {ru} が該当します。
その答えになる理由


それでは、問題の内容を見ていきましょう。
【接辞の付加に伴う品詞変化】なので、選択肢の接辞を適当な語につけて品詞が変わらないかを見ていきます。
1 欲しい(イ形容詞) → 欲しがる(動詞に変化)
2 私(名詞) → 私たち(名詞のまま)
3 美しい(イ形容詞) → 美しさ(名詞に変化)
4 かたい(イ形容詞) → かためる(動詞に変化)
5 建設(名詞) → 建設的(ナ形容詞に変化)
2だけ、選択肢の接辞をつけても品詞が変化していないですね。
これが正解です。
(4)ナイ形
その答えになる理由


各選択肢をナイ形に変えてみましょう。
1 けらない
2 みない
3 はしらない
4 いない
5 おきない
4だけ、「ある」という動詞から「いない」というイ形容詞に品詞が変化しましたね。
これが正解です。
他の選択肢と同様のルールを適用するのであれば「あらない」になるのですが、4だけが例外として逆、の意味を表すのに「ナイ形」ではなく別の語を用います。
(5)連体詞
先に用語を確認しておきましょう。
解説 連体詞
「連体詞」とは品詞の1つで、体言を修飾するがイ形容詞・ナ形容詞とは異なり活用しないもののことです。
「あの」「ある」「大きな」などが該当します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
まず、すべて後続の名詞を修飾しているので「イ形容詞」「ナ形容詞」「連体詞」のどれかです。
次に、その語が活用するかを見てみると
1 活用しない
2 活用しない
3 活用しない
4 活用しない
5 同じだ・同じでない→ 活用する
ですね。
5だけが「ナ形容詞」で、それ以外が「連体詞」です。
5が正解です。
(6)動詞の自他
その答えになる理由


「自動詞」「他動詞」が問題になるときは、「自動詞」「他動詞」のペアについて聞かれることが多いです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 【自動詞】走る ⇔ 【他動詞】走らす
2 【自動詞】渡る ⇔ 【他動詞】渡す
3 【自動詞】通る ⇔ 【他動詞】通す
4 【自動詞】回る ⇔ 【他動詞】回す
5 【自動詞】移る ⇔ 【他動詞】移す
1だけ、他の選択肢と形が違いますね。
他と同じルールであれば「走す」になっているはずです。
これが正解です。
「走る」は他動詞がない動詞(無対自動詞)なので、「~させる」の意味にしたいときは「使役受身形」にする必要があります。
(7)複合動詞の意味
その答えになる理由


「切る」は「ものを切断する」が本来の使い方ですが、動詞のマス形に接続したときは「その動作を終えた」という完了の意味を表すことがあります。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 「飲む」という動作を終える
2 「使う」という動作を終える
3 「噛んで」「切る」
4 「出す」という動作を終える
5 「走る」という動作を終える
3だけ「切る」本来の意味で使われています。
これが正解です。
(8)形式名詞
先に用語を確認しておきましょう。
解説 形式名詞
「形式名詞」とは、名詞としての実質的な意味がなく、文法的機能だけを表す名詞のことです。
「こと」「ほど」「ところ」などが該当します。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 遅刻した「理由」 ← 実質的な意味がある
2 分かる「はず」 ← 実質的な意味はない
3 集中した「ため」 ← 実質的な意味はない
4 失敗した「こと」 ← 実質的な意味はない
5 気づかない「うち」 ← 実質的な意味はない
1だけが「理由」「原因」などの語に置き換えられるので、形式名詞ではありません。
これが正解です。
(9)「勧め・忠告」のモダリティ形式
先に用語を確認しておきましょう。
解説 命題
文は「命題」と「モダリティ」から成り立っています。
「命題」は文の骨格とも言える事柄を表し、「モダリティ」は話し手の心的態度を表します。
「彼が犯人のようだ」であれば
● 彼が犯人だ → 文の骨格となる「命題」
● ようだ → 話し手の心的態度を表す「モダリティ」
です。
解説 モダリティ
「モダリティ」とは、「命題」に対する話者の気持ちなどを表す文の構成要素です。
「私は彼が犯人だと思う」のように話し手が命題をどう捉えているかを表す「対時的モダリティ」と、「明日一緒に行こうよ」のように命題について聞き手に同意や確認を表す「対人的モダリティ」に分かれます。
その答えになる理由


今回の問題では「モダリティ」の部分が「勧め・忠告」になっているかを聞かれています。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 勧め・忠告
2 勧め・忠告
3 勧め・忠告
4 許可
5 勧め・忠告
4だけ、モダリティ部分の意味が違いますね。
これが正解です。
(10)「から」の用法
その答えになる理由


いくつかある「から」の用法のうち、「起点」と「主体」が聞かれています。
「起点」は何の起点なのかによって、さらに分類されていきます。
【移動の起点】駅からタクシーで向かいましょう。
【方向の起点】ここから子供たちの様子が見える。
【範囲の起点】「言語と社会」の章から勉強を始める。
「主体」は「が」と近い使い方で
【動きの主体】書き終わった人から、退出してください。
のように使います。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 移動の「起点」
2 動作の「主体」
3 移動の「起点」
4 範囲の「起点」
5 移動の「起点」
2だけが「主体」の用法ですね。
これが正解です。
(11)「~ぱなし」の意味
その答えになる理由


「ぱなし」は「動詞のマス形+っぱなし」で
① その行為を終えた結果のままにしている(結果の放置)
② その行為自体を継続したままにしている(動作の継続)
などの使い方をします。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 開けたままにしている(結果の放置)
2 置いたままにしている(結果の放置)
3 「歌う」という動作の継続
4 干したままにしている(結果の放置)
5 つけたままにしている(結果の放置)
3だけ用法が違いますね。
これが正解です。
(12)「~ことにする」の用法
その答えになる理由


各選択肢を「~に決める」で言い換えられないかを見ていきましょう。
1 ○ ジョギングすることに決めた
2 ○ 車を買い替えることに決めた
3 ? 母が病気だということに決めた
4 ○ 明日やることに決めた
5 ○ 帰ることに決めた
3の「ことにする」は「~だとみなす」、その他は「~に決める」の意味で使われています。
これが正解です。
(13)割合を表す用法
その答えになる理由


変わった問題ですね。。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1 スタンプ50個 に対して 500円の値引き
2 留学生5人 に対して 日本人学生1人
3 1㎡ に対しての ●●円
4 50名 までは 申し込める
5 成人男性5人 に対しての 1人
4だけ割合の用法ではなく、「まで」に言い換えられるような上限の用法ですね。
これが正解です。
(14)「~ので」節の前件と後件の関係
その答えになる理由


「ので」を別の語に言い換えてみると…とするとドツボに嵌ります。
単純に順序の問題ですね。
1 おかしな臭いがした → ガス漏れだと思った
2 アイスが欲しいと言った → 買ってきた
3 子供が泣いた → お菓子をあげた
4 周りの人が笑った → 付けひげを取った
5 掃除した → 友達が来る
時系列で見ると、5だけ「後件→前件」の順番ですね。
これが正解です。
(15)言語の類型
その答えになる理由


これは知っているか知らないかですね。
各言語は「統語的類型」や「形態的類型」などで分類することができます。
これは慣れてしまった方が早いので、問題で知識として入れておきましょう。




まず、「統語的類型」で分類してみると
1 sov型
2 svo型
3 sov型
4 sov型
5 ovs型
となり、答えを絞り込めませんでした。
次に、「形態的類型」で分類してみると
1 膠着語
2 孤立語
3 膠着語
4 膠着語
5 膠着語
となり、2が仲間外れになりました。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら