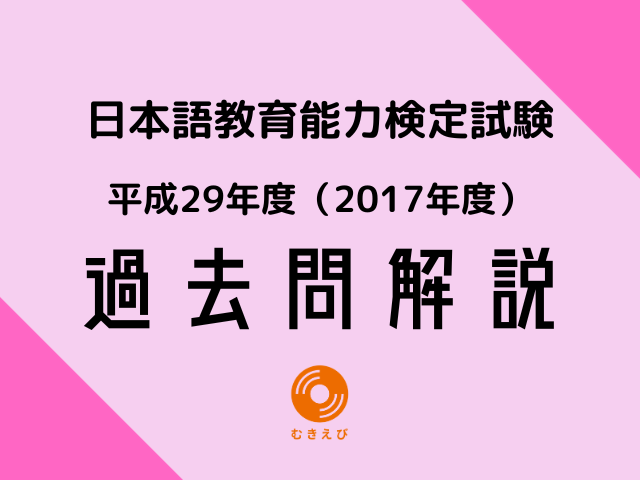平成29年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題9
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 行動主義心理学に基づく言語習得観
解説 行動主義心理学
「行動主義心理学」とは、客観的に観察できる「行動」を観察対象とし、条件(刺激)と行動の関係を分析することで、行動の予測を行うことを目的とした心理学のことです。
学習は刺激に対する反応を繰り返すことによって、習慣的に形成されるとしています。
1900年代前半にアメリカで主流になり、この理論を体系化した教授法が「オーディオ・リンガル・メソッド」です。
その答えになる理由


2が「行動主義心理学」の内容そのままですね。
これが正解です。
問2 対照分析仮説
解説 対照分析仮説
「対照分析仮説」とは、母語の干渉が学習上の大きな問題であり、学習者の母語と目標言語との違いが大きいほど学習が困難であるとしています。
その答えになる理由


下線部は「対照分析仮説」の内容そのままですね。
4が正解です。
問3 誤り
解説 言語間の誤り(interlingual error)
「言語間の誤り」とは、第一言語と第二言語との差異から生じる誤り(母語の影響を受けた誤り)のことです。
解説 言語内の誤り(intralingual error)
「言語内の誤り」とは、第一言語との違いからではなく、第二言語の学習の不完全さから生じる誤りのことです。
過剰一般化(過剰般化)
第二言語の規則を過剰に適用して生じる誤りのことです。
簡略化
言語規則を単純化させることにより生じる誤りのことです。
などが該当します。
解説 全体的な誤り(global error)
「全体的な誤り(グローバル・エラー)」とは、コミュニケーション上で大きな支障を与える誤りのことです。
解説 局部的な誤り(local error)
「局部的な誤り(ローカル・エラー)」とは、コミュニケーション上で影響が少ない誤りのことです。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は「言語間の誤り」ではなく、「言語内の誤り」の内容です。
2は「言語内の誤り」ではなく、「言語間の誤り」の内容です。
3は何も問題ありません。これが正解です。
4は「局部的な誤り」ではなく、「訓練上の転移」の内容です。
下線部のように、教師の指導が不十分であることが原因で生じます。
問4 誤用分析研究
その答えになる理由


誤用分析自体は、発展途上の学習者の言語能力を知る有効なデータであるものの、表現されたデータのみに着目するところにネックがあります。
学習者が「回避」のような苦手な表現を避けるストラテジーを使用すると現象として出てこないため、分析に必要な誤用の数が限られてくることが指摘されています。
4が正解です。
問5 自然習得順序仮説
解説 モニターモデル
関連する用語も合わせて整理していきましょう。
「モニターモデル」とは、クラッシェンが提唱した
● 自然習得順序仮説
● 習得・学習仮説
● モニター仮説
● インプット仮説
● 情意フィルター仮説
などの第二言語習得理論全体のことです。
教授法ではナチュラル・アプローチとして具現化されています。
解説 自然習得順序仮説
「自然習得順序仮説」とは、言語を習得するにあたり、教える順序は関係なく、習得する自然な順序があるとする仮説のことです。
解説 習得・学習仮説
「習得・学習仮説」とは、幼児が母語を身に着ける際の「習得」と、学校などで意識的に身に着ける「学習」があるとし、「学習」で得た知識は「習得」の知識にはつながらないとする仮説のことです。
解説 モニター仮説
「モニター仮説」とは、「学習」は「習得」にはならないが、発話の際に修正・チェックをする「モニター」として働くとする仮説のことです。
解説 インプット仮説
「インプット仮説」とは、学習者が言語を身に着ける際に「理解可能なインプット(i+1)」を通して進むという仮説のことです。
「i」はその時点での学習者の言語能力を、「+1」は少し高いレベルを指しています。
未習の語彙であっても文脈などから推測できる範囲のインプットを与えることで、言語習得が進むとされています。
解説 情意フィルター仮説
「情意フィルター仮説」とは、学習者の動機の低迷や不安などがフィルターとなり、その「情意フィルター」が高くなることで言語習得が進まなくなるとする仮説のことです。
その答えになる理由


2が「自然習得順序仮説」の内容そのままですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら