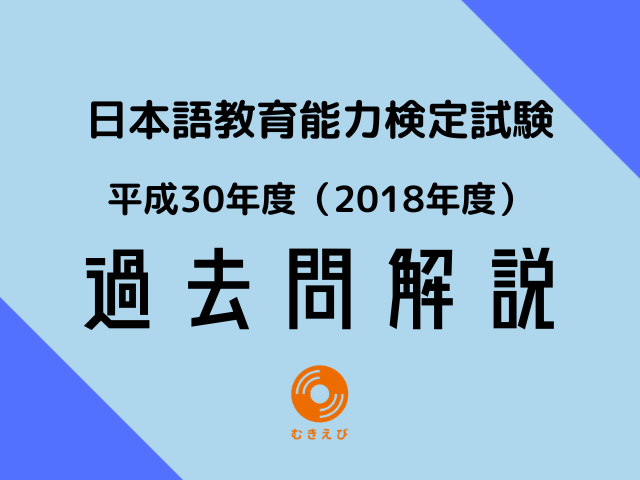平成30年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題2
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


(1)
その答えになる理由


「きこう」→「きっこう」と不要な促音が入ることで、拍の長さが変わってしまっています。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「ひま」→「いま」は、子音が脱落したことによる誤用です。
「にし」→「にっし」は、不要な促音が入ることで、拍の長さが変わる誤用です。
「とこう」→「とうこう」は、不要な長音が入ることで、拍の長さが変わる誤用です。
「きょう」→「きよう」は、「ょ」を単独で読むことで、拍の長さが変わる誤用です。
1のみ、拍の長さの誤用ではありません。
(2)
その答えになる理由


意向形にする際に、ルールを取り違えていることへの誤用です。
一段動詞「食べる」を意向形にするには「語幹+よう」ですが、五段動詞の活用を適用させてしまっています。
このように、あるルールを別のものにまで適用させてしまう誤用を「過剰般化」と言います。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「信じろう」 一段動詞「信じる」に五段動詞の活用を適用させた誤用です。
「植えろう」 一段動詞「植える」に五段動詞の活用を適用させた誤用です。
「考えろう」 一段動詞「考える」に五段動詞の活用を適用させた誤用です。
「出来ろう」 「出来るだろう」の「だ」が欠落したとによる誤用です。
4のみ、活用形の誤用ではありません。
これが正解です。
(3)
その答えになる理由


不要な「という」が挿入されている誤用です。
「という」を削って、文章が成り立つか見ていきましょう。
2のみ、「という」を削ると文章が成立しません。
これが正解です。
(4)
その答えになる理由


頻度に用いる「たいてい」と数量や割合に用いる「だいたい」を取り違えた誤用です。
「たいてい」→「だいたい」に変えて、文章が成立するか見ていきましょう。
3のみ、「たいてい」→「だいたい」ではなく「たいてい」→「たまに」の修正が必要になります。
これが正解です。
(5)
その答えになる理由


「行く前」のうしろの「に」が欠落してしまったことによる誤用です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
2のみ、「に」の欠落ではなく、「収まる前」→「収まるまで」の誤用ですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら