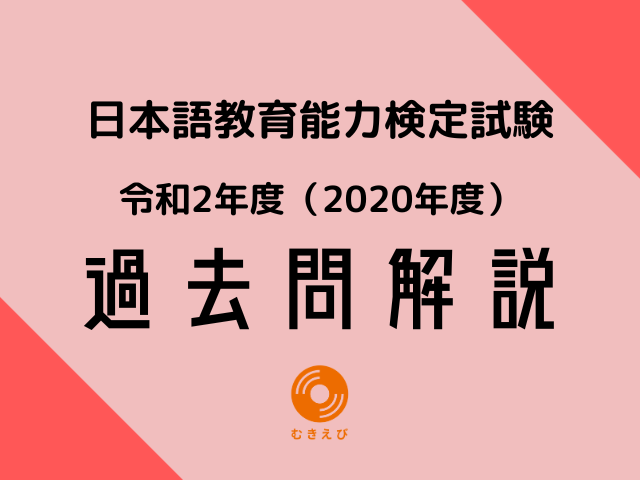令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題4
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 文法訳読法
解説 文法訳読法
多くの場合、授業中は学習者の母語を媒介語として使用します。
また、リスニングやスピーキングよりも、文法や語彙知識を問う練習問題の方が重視されます。
解説 多読
- 簡単な内容の本から始める
- わからないところは、辞書を引かずに飛ばして読む
などの注意点があります。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
文法訳読法では、その言語で書かれた文献を読むことができるようになることがゴールです。
いきなり最上級難度のものを…というわけではありませんが、易しいものから順に文型を積み上げていくわけではありません。
1は、間違いです。
2は、文法訳読法ではなく、「多読」をするメリットを説明しています。
3は、何も問題ありません。
これが正解です。
4は、前半は合っていますが、後半が間違いです。
文法訳読法において、単語や文法規則の暗記により向上するとされているのは、口頭コミュニケーション能力ではなく、読解能力ですね。
問2 直接法・帰納
解説 直接法・間接法
日本語教育の現場であれば、
英語が母語の学習者に、日本語で日本語の授業を行う
などが該当します。
日本語教育の現場であれば、
英語が母語の学習者に、英語で日本語の授業を行うこと
などが該当します。
解説 帰納・演繹
その答えになる理由


選択肢を1つずつみていきましょう。
1は、目標言語で学習していることから、直接法の教え方です。
また、個別事例から文法規則を導き出しているので、帰納的にアプローチしていますね。
直接法・帰納的アプローチの内容です。
2は、媒介語で学習していることから、間接法の教え方です。
また、文法規則を個別事例に当てはめているので、演繹的にアプローチしていますね。
間接法・演繹的アプローチの内容です。
3は、目標言語で学習していることから、直接法の教え方です。
また、文法規則を個別事例に当てはめているので、演繹的にアプローチしていますね。
直接法・演繹的アプローチの内容です。
4は、媒介語で学習していることから、間接法の教え方です。
また、個別事例から文法規則を導き出しているので、帰納的にアプローチしていますね。
間接法・帰納的アプローチの内容です。
問3 コミュニカティブ・アプローチ
解説 コミュニカティブ・アプローチ
言語形式や構造・正しい発音を重視した「オーディオリンガル・メソッド」への批判から唱えられた手法であり、2つの言語観が基盤になっています。
1つ目は、ハリデーが唱えた「機能言語学」です。
これは、言葉の意味と機能を重視しています。
2つ目は、ハイムズが唱えた「社会言語学」です。
これは、言語能力とは文法知識だけでなく実際の使用方法に関するものも含まれ、その総体が伝達能力だとしています。
実際の教育の場面では、「言語の機能を理解し、場面・文脈を把握して、話し手の考えを聞き手に伝えるために適切な表現を使う能力を育成すること」に重点が置かれています。
その答えになる理由


「文脈における言語の機能や意味を重視」が、まさにコミュニカティブ・アプローチの内容ですね。
1が正解です。
2は、コミュニカティブ・アプローチによって批判された「オーディオリンガル・メソッド」の説明になっています。
3は、問2で出てきた「直接法」の内容です。
4も、コミュニカティブ・アプローチによって批判された「オーディオリンガル・メソッド」の説明になっています。
実際のコミュニケーションの場面では、誰かに訂正してもらうのではなく、自身で誤りに気づけなければなりません。
そのため、コミュニカティブ・アプローチでは、自己訂正の方が重視されています。
問4 ナチュラル・アプローチ
解説 ナチュラル・アプローチ
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
「構造シラバス」とは、目標言語を文法や文型・語彙の面から分析し、基礎的なものから複雑なものへ、積み上げ式に配置したもののことです。
「構造主義言語学」の考え方に基づいており、言語形式を重視した教授法のときに用いられるシラバスなので、ナチュラル・アプローチでは重視されない内容ですね。
1は、間違いです。
2は、何も問題ありません。
これが正解です。
ナチュラル・アプローチでは、聴解を重視しているため、初期段階から学習者に積極的な発話を促すことはありません。
3は、間違いです。
ナチュラル・アプローチ、は幼児の言語習得過程がベースのため、中級以上よりも初級レベルの授業デザインに用いると効果的です。
4は、間違いです。
問5 タスク中心の教授法
解説 タスク中心の教授法
タスクを達成するための行動の中で、学習者が目標言語を積極的に使うことにより自然なコミュニケーション能力を身につけることを促していきます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、何も問題ありません。
これが正解です。
2のような教師の指示によって実際に動作を行わされる教授法は、「TPR(全身反応教授法)」です。
母語の習得過程をベースにして、スピーキングよりも先にリスニングを鍛え、今日y氏の指示に対して動作を使って応答する活動を行います。
3のような枠割を与えて読み合わせをさせるのは、「シナリオプレイ」です。
似ているのは「ロールプレイ」ですが、ロールプレイの場合は役割だけ与えて、具体的に話す内容の指示や読み合わせなどは行いません。
タスク中心の教授法では、インタビューをするというタスクを行うことで「ことができますか」という表現を身につけさせます。
4は、順序が逆ですね。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら