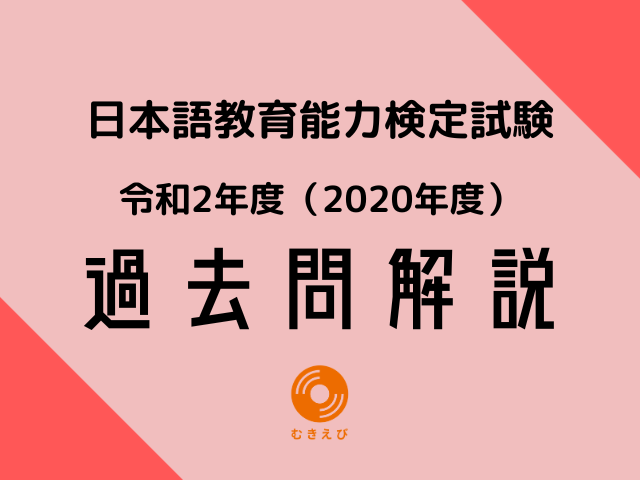令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題5
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 新出語の導入
その答えになる理由


初級学習者に対してでであることがポイントですね。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
使われる場面が限定される表現から始めると、その場面分だけパターンを覚えてもらう必要があります。
初級学習者に対してだとハードルが高くなるため、汎用的な語から取り入れていくのが好ましいですね。
1が正解です。
日本語教育では、定型表現や決まり文句を一語ずつ分解して導入するのではなく、表現としてそのまま覚えてもらうことの方が多くあります。
2は、間違いです。
日本語教育に限らず、文脈や実際に使用される場面とセットで覚えた方が長期記憶に残りやすくなりますね。
3は、間違いです。
中級以上では、形や意味に類似性のあるものをセットで教えることはありますが、初級では学習者が混乱しないように、できる限りシンプルに伝えていった方が良いですね。
4は、間違いです。
問2 目的と方法
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
目的:記憶に残りやすくする
方法:学習する語を示して自分の体験談を書かせる
学習する語と自分の体験談が紐づくことで、長期記憶に残りやすくなりますね。
1は、目的と方法が一致しています。
目的:学習した語を理解しているかどうか確認する
方法:短文のリピートをさせる
学習した語を理解していなくても、暗記できていれば短文のリピートが可能です。
2は、目的と方法が一致していません。
これが正解です。
目的:どのような文脈で使われるか学ばせる
方法:学習する語を含む文の一部を与え、文全体を完成させる
一部から全体を完成させることで、文脈を意識した学習が可能になりますね。
3は、目的と方法が一致しています。
目的:学習する語と母語の対応語との意味や用法の違いに気づかせる
方法:学習者の母語の文を日本語に翻訳させる
学習者の母語を日本語に翻訳することで、細かな意味の違いや使い方を意識しやすくなります。
4は、目的と方法が一致しています。
問3 階層的関係
解説 階層的関係
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、
販売する ⇔ 購入する
のように、反対の意味の組み合わせですね。
これは、対義語の例です。
2は、
賛成 = 同意
のように、同じ意味の組み合わせですね。
これは、同意語の例です。
3は、
動物
∟ 鳥
のような親・子の関係ですね。
これが、階層的関係の例です。
4は、
木
∟ 杉
∟ 松
のよう兄弟の関係ですね。
これは、同位語の例です。
問4 対義語
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、例が適切ではありません。
正しい(形容詞) ⇔ 間違い(名詞)
などであれば、対になる語の品詞が同一でないものの例なのですが、
ぼけ(名詞) ⇔ つっこみ(名詞)
は、どちらも名詞ですね。
2は、例・内容ともに問題ありません。
値段が高い ⇔ 値段が安い
背が高い ⇔ 背が低い
のように、「高い」は内容によって対義語が異なり、一対一の対立になっていません。
3は、対義語ではなく、同位語の説明になっています。
木
∟ 桜
∟ 梅
「桜」「梅」は、「木」という上位語をもつ兄弟関係にありますね。
4は、後半が違います。
語種とは、語を出どころから分類したもので、
- 和語 … 日本古来の語
- 漢語 … 中国から伝来した語
- 外来語 … 中国以外から伝来した語
であり、「不急」「火急」は、いずれも漢語で語種が同じです。
問5 付随的学習
解説 意図的学習
解説 付随的学習
その答えになる理由


4が正解です。
先に「漢字クラスで習う」という意図的学習があり、それを社内広告で見るという偶然による付随的学習で補完しています。
そのほかは、意図的学習と付随的学習の順番が逆ですね。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら