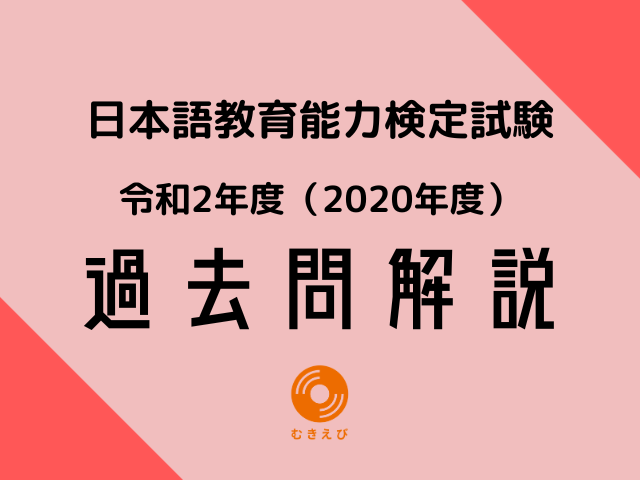令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題6
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 談話能力
解説 カナル&スウェインによるコミュニケーション能力(伝達能力)の分類
カナル&スウェインは、コミュニケーション能力(伝達能力)の下位分類として、以下の4つを挙げています。
解説 社会言語能力
解説 文法能力
解説 ストラテジー能力
解説 談話能力
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
コミュニケーションを円滑に進めるために表情・体の動きなどの非言語活動を活用できるようにすることで高められるのは、ストラテジー能力ですね。
1は、間違いです。
会話の相手や場面に合わせた表現を選ぶことができるようになることで高められるのは、社会言語能力ですね。
2は、間違いです。
学習者自身に発音の不自然な点を見つけさせることで、発音の正確さを高められるようにするのは、文法能力ですね。
3は、間違いです。
会話の中での相づちを意識することで、発話の順番の取り方などをできるようにするのは、談話能力ですね。
4が正解です。
問2 コミュニケーション・ストラテジー
解説 コミュニケーション・ストラテジー
解説 回避
解説 言い換え
解説 母語使用
解説 援助要求
その答えになる理由


コミュニケーション・ストラテジーは、
- 相手の話しが内容を上手く聞き取れなかった・理解できなかった
- 自分が話した内容を聞き取ってもらえなかった・理解してもらえなかった
などのコミュニケーション上の問題をクリアするためにとる方法のことです。
選択肢を見てみると…
コミュニケーション上の問題が起きていて、やり取りが上手くいくように工夫しているのは、2だけですね。
これが正解です。
問3 書く活動におけるコミュニケーション能力の養成を意識した活動
その答えになる理由


「コミュニケーション能力の養成を意識した活動」なので、相手が必要ですね。
今回は、「書く活動においても」とあるので、読み手に考えを正しく伝えようとしているかがポイントです。
選択肢を見てみると…
4だけ、書くだけで伝えていません。
これが正解です。
問4 プロフィシエンシー
解説 プロフィシエンシー
日本語教育における「プロフィシエンシー」では、「実際の場面において、どれくらい母語話者のような言語活動ができるか」が問われます。
問1であったカカナル&スウェインによるコミュニケーション能力(伝達能力)も、「プロフィシエンシー」で問われる指標の1つです。
その答えになる理由


3が「プロフィシエンシー」の内容そのままですね。
これが正解です。
問5 語用論的転移
解説 語用論的転移
母語をそのまま訳すことによって、目標言語においては不適切な表現になってしまうことも「語用論的転移」に含まれます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、「できなければ→できないとすると」のように、伝える内容が文法的に間違っていますね。
これは、母語の影響を受けた不適切な言語使用ではありません。
2は、「もらう→いただく」「驚愕しました→驚きました」のように、文法的には間違いではないものの、不適切な言葉選びになっていますね。
不適切な言語使用ですが、母語の影響を受けたものではありません。
3は、「行きません→約束があるので…申し訳ございません」などの方が良さそうですね。
文法的な誤りではなく、直接的な表現を好む母語の影響によるものだと思われます。
これが正解です。
4は、コミュニケーション・ストラテジーにおける「母語使用」の例ですね。
わからない部分を母語に置き換えることで、内容を伝えようとしています。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら