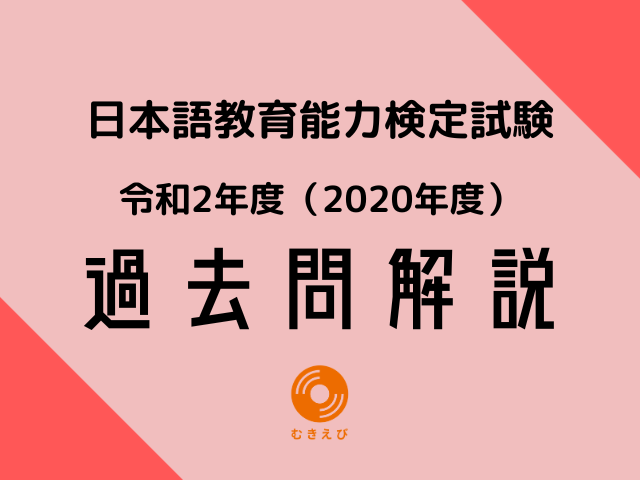令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題7
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 逆行
解説 逆行
母語の影響よりも、緊張したときや不安が高まったときに起きやすいとされています。
その答えになる理由


4のような「~できていたが…」が逆行の例です。
1と2は、学習者の母語の影響が出てしまった例です。
また、母語習得過程において幼児語や短い文が出てくることはありますが、第二言語習得過程において同様の現象が出ることはありません。
問2 文法的な正確さに関わる誤用
その答えになる理由


文法的に誤りがあるものを探してみましょう。
△ 新しい薬が風邪を治しました。
は、
○ (私は)新しい薬で風邪が治りました。
のように、「私」を主語にした方が良いですね。
ただし、これは「日本語では、こちらの方が自然」という内容であって、文法的な誤りがあるわけではありません。
1は、間違いです。
△ 私はどこにいますか?
は、
○ ここはどこですか?
○ ●●にはどう行けばよいですか?
などの方が良いですね。
ただし、これも「日本語では、こちらの方が自然」という内容であって、文法的な誤りがあるわけではありません。
2は、間違いです。
× テストを受けているうちに
は、
○ テストを受けているときに
にしなければなりません。
これは「日本語では、こちらの方が自然」という内容ではなく、文法的に間違っています。
3が正解です。
△ 誰かが私のパソコンを盗みました。
は、
○ (私は)誰かにパソコンを盗まれました。
のように、「私」を主語にした受身文の方が良いですね。
ただし、これも「日本語では、こちらの方が自然」という内容であって、文法的な誤りがあるわけではありません。
4は、間違いです。
問3 誤形成
解説 誤形成
「誤形成」とは、「したがって」を「たしがって」にするなどの形態的な誤りのことです。
誤用に関しては日本語教育能力試験の問題集等に記載が少なく、知識に不安がある方も少なくないかと思います。
実際に現場に立つようになったら、『日本語誤用辞典』が大活躍します。
今回は、誤用の分類に絞って確認していきましょう。
日本語誤用辞典では、学習者の誤用を以下のように分類しています。
| 脱落 | 当該項目を使用しなければいけないのに使用していない誤用。その項目がないと非文法的になる場合と、非文法的ではないが、適切ではないという場合がある。 |
| 付加 | 脱落とは逆に、当該項目を使用してはいけないところに使用している誤用 |
| 誤形成 | 「したがって」を「たしがって」にするなどの形態的な誤り |
| 混同 | 助詞「は」と「が」、接続詞「そして」と「それで」などのように、当該項目を他の項目と混同していることによる誤用 |
| 位置 | 当該項目の文中での位置がおかしい誤用 |
| その他 | 以上の五つに属さないが、当該項目と密接に関係すると判断される誤用 |
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
× 目上の人に対して
○ 目上の人を
格助詞・複合格助詞の中で、別の項目と間違えていますね。
1の誤用は、混同です。
× 高かっても
○ 高くても
イ形容詞「高い」の活用が形態的に間違っていますね。
2の誤用は、誤形成です。
× 熱38度がある
○ 熱が38度ある
格助詞「が」が置かれている場所が違いますね。
3の誤用は、位置です。
× 席から出た
○ 席を立った
格助詞の中で「から」と「を」を・動詞の中で「出る」と「立つ」を間違えていますね。
4の誤用は、混同です。
問4 母語の影響
その答えになる理由


全然わかりません。。
発話したい単語の子音が母語にはないために、脱落や付加が起こっていることによるものだと思うのですが、それぞれの外国語の知識がないと難しいですね。
一定レベル以上の知識がある方であれば、消去法も可能ですが、わからなければサッと次にいきましょう。
4が正解です。
問5 付加のストラテジー
解説 付加のストラテジー
きれい
↓
きれいじゃない
のように、「じゃない」を否定の表現と見なして
必要だ
↓
○ 必要じゃない
—
大切だ
↓
○ 大切じゃない
—
ある
↓
× あるじゃない
—
美しい
↓
× 美しいじゃない
のように、必要だと考えるところにそのまま付加することなどが例として挙げられます。
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
× あるじゃない
○ ない
ナ形容詞文・名詞文のときの「じゃない」をそのままくっつけることで、否定文を作ろうとしていますね。
1は、付加のストラテジーの例です。
× あの人
○ その人
指示詞が間違っていますね。
2は、付加のストラテジーの例ではありません。
× 家の前に話をしました。
○ 家の前で話しをしました。
格助詞が間違っていますね。
3は、付加のストラテジーの例ではありません。
× 考えれません
○ 考えられません。
「ら」が脱落して、ら抜き言葉になっていますね。
4は、付加のストラテジーの例ではありません。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら