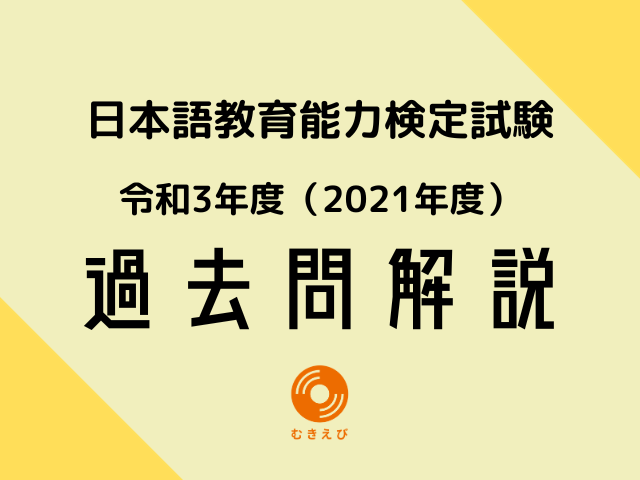令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題3D
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


(16)等位・並列節
解説 単文・複文
【単文】
昨日雨が降った。
【複文】
昨日雨が降ったので、外出しなかった。
解説 主節・従属節
昨日雨が降ったので、外出しなかった。
であれば、主節が「外出しなかった」・従属節が「昨日雨が降ったので」です。
従属節は、主節に対して果たす役割によって、
- 補足節
- 名詞修飾節
- 副詞節
- 等位・並列節
の4つに分類することができます。
【補足節】
私は、カフェに行くのが好きだ。
【名詞修飾節】
カフェで飲むコーヒーが好きだ。
【副詞節】
カフェに着いたとき、母から電話がかかってきた。
【等位・並列節】
私はカフェに行き、妹はスーパーに行った。
解説 等位・並列節
彼は大学に進学し、私は家業を継いだ。
その答えになる理由


選択肢が
- 補足節
- 名詞修飾節
- 副詞節
- 等位・並列節
のどれに当たるかを見ていきましょう。
1の従属節「掃除もするし」は、主節と対等な関係にありますね。
これは、等位・並列節にあたります。
2は、主節「テレビを見た」を従属節「ソファーに座って」が修飾していますね。
これは、副詞節にあたります。
3は、主節「びっくりした」を従属節「息が詰まるくらい」が修飾していますね。
これは、副詞節にあたります。
4は、主節「取っていいですよ」を従属節「好きなだけ」が修飾していますね。
これは、副詞節にあたります。
1が正解です。
(17)疑問節をガ格に取る述語
解説 疑問節
明日、誰がパーティーにくるかわからない。
彼が山田さんかどうか自信がない。
疑問節が補語となる文の主節には、
- 思考
- 知覚
- 評価
などを表す述語が現れます。
その答えになる理由


対象の用法がある格助詞は、「が」と「を」です。
推しの武道館デビューがうれしい。
推しの誕生日を忘れていた。
格助詞「が」を「ガ格」・格助詞「を」を「ヲ格」と呼ぶので、上の例文であれば、
- イ形容詞「うれしい」は、対象をガ格に取る
- 動詞「忘れる」は、対象をヲ格に取る
と表現されることがあります。
設問の「疑問節をガ格に取る述語」というのは、
きちんと覚えたかどうかが大切だ。
のように、
- ナ形容詞「大切だ」は、疑問節をガ格に取る
と表現できるもののことです。
選択肢になっているナ形容詞を述語にした文を作ってみましょう。
○ 本質的な解き方ができているかが重要だ。
1の「重要だ」は、疑問節をガ格に取る述語として適当です。
○ この学習ペースで良いのかが問題だ。
2の「問題だ」は、疑問節をガ格に取る述語として適当です。
× この学習ペースで良いのかが不満だ。
3の「不満だ」は、疑問節をガ格に取る述語として不適当です。
○ 本質的な解き方ができているかが心配だ。
4の「心配だ」は、疑問節をガ格に取る述語として適当です。
(18) 内の関係
解説 内の関係
勉強する姉
は、「姉」という名詞を詳しく説明する名詞修飾節です。
内の関係にあるので、修飾される名詞「姉」を主語とした
○ 姉が勉強する
が成立します。
姉が勉強する科目
も、「科目」という名詞を詳しく説明する名詞修飾節です。
修飾される名詞「科目」を主語にしようとしてみても
× 科目が姉が勉強する
のように、内容が成立しないですね。
このような関係を「外の関係」といいます。
その答えになる理由


修飾される名詞を主語にした文に変換してみましょう。
1 × おつりがお菓子を買った
2 × 事前が駅前の宝石店に泥棒が入った
3 × アルバイトが子どもに算数を教える
4 ○ 噂が最近大学で広まっている
4は「内の関係」・1~3は「外の関係」ですね。
4が正解です。
(19)条件節
解説 条件節
条件節には、
- 順接条件節
- 原因・理由節
- 逆接条件節
の3つに分類することができます。
【順接条件節】
薬を飲めば、熱が下がるだろう。
【原因・理由節】
薬を飲んだから、熱が下がった。
【逆接条件節】
薬を飲んでも、熱が下がらなかった。
その答えになる理由


条件節の中の「順接条件節」につく接続助詞が問題になっています。
「主節に命令などの行為要求のモダリティが使えない」とあるので、主節を命令形式にした例文を考えてみましょう。
○ やる気がなければ、出ていきなさい。
状態性である述語「ない」を用いて、接続助詞「ば」を用いた条件文が成立していますね。
1の内容は、制約にあたりません。
× 不審物を見かけると、車掌まで知らせてください。
接続助詞「と」を用いた条件節の場合、主節を命令形式にした文が成立しないですね。
2の内容は、制約にあたります。
○ 不審物を見つけたら、車掌まで知らせてください。
接続助詞「たら」を用いた条件文が成立していますね。
3は、制約にあたりません。
○ やる気がないなら、出ていきなさい。
接続助詞「なら」を用いた条件文が成立していますね。
4は、制約にあたりません。
2が正解です。
(20)最も従属度の低い従属節
その答えになる理由


「最も従属度の低い…」と言われると身構えてしまいそうですが、解き方はシンプルです。
主節と従属節の結びつき度合いを見るときは、まず主節・従属節の主語が同じかを確認します。
2・3は、主節と従属節の主語が同じです。
従属節だけ抜き出すと、誰の動作なのかわからないですね。
両者の結びつきが強いので、従属節の従属度が高いと言えます。
1・4は、主節と従属節の主語が違います。
述語だけ抜き出しても、誰の動作かわかりますね。
両者の結びつきが弱いので、従属節の従属度が低いと言えます。
次に、従属節が単独で成立するかを見ていきましょう。
1は、主節・従属節がそれぞれ単独で文が成立します。
一方、4の従属節は、主節の原因・理由になっていますね。
そのため、意味の関係上、単独にすることができません。
最も従属度の低い従属節をもつのは、1です。
上の解き方が正攻法なのですが、従属節の種類と特徴がわかっていれば、パっと正解にたどり着くこともできます。
1 等位・並列節
2 副詞節 – 時間節
3 副詞節 – 様態節
4 副詞節 – 条件節 – 原因・理由節
副詞節は、主節の内容を修飾する働きをするため、従属度が高いです。
等位・並列節は、主節と対等な関係のため、従属度が低いです。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら