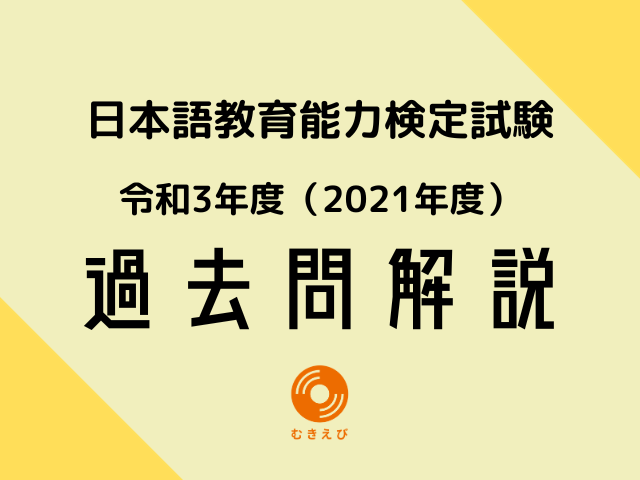令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題4
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 トップダウン処理に焦点を当てた活動
解説 トップダウン処理
前後の文脈から語の意味を類推する
聴解の際の背景の音から、場面を想像したりする
などが該当します。
解説 ボトムアップ処理
その答えになる理由


トップダウン処理では、既に持っている知識を活用して、わからない内容の意味を予測しながら理解を進めていきます。
反対に、文字・音・単語の意味などの細かい部分から理解を進めていくのが「ボトムアップ処理」です。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
定型表現のような細かい部分から理解を進めていくのは、ボトムアップ処理ですね。
1は、トップダウン処理に焦点を当てた活動ではありません。
「どのコースに行きたいか」といった大枠から入り、既に持っている知識を活用して具体的に決めていくのは、トップダウン処理ですね。
2は、トップダウン処理に焦点を当てた活動として適当です。
1つ1つの漢字のような細かい部分から理解を進めていくのは、ボトムアップ処理ですね。
3は、トップダウン処理に焦点を当てた活動ではありません。
語の意味のような細かい部分から理解を進めていくのは、ボトムアップ処理ですね。
4は、トップダウン処理に焦点を当てた活動ではありません。
問2 多読
解説 多読
- たくさん読めるように、興味がある簡単な内容の本から始める
- たくさん読めるように、わからないところは、辞書を引かずに飛ばして読む
などの注意点があります。
その答えになる理由


1が「多読」の内容そのままですね。
これが正解です。
悩むとしたら2ですが、「自分のレベルに合うかどうかよりも」が違います。
たくさん読めなければ多読ではないので、簡単な内容から始めて、自分のレベルに合ったものを選ぶことが大切です。
問3 再話
解説 再話
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
再話の目的は、学習者が理解したことを自分の言葉で説明することで、知識の定着を図ることです。
人により再生できることに違いはありますが、グループ活動・個人活動のどちらでも有効な手段だと言えます。
1は間違いです。
再話の目的は、学習者が理解したことを自分の言葉で説明することで、知識の定着を図ることです。
口頭だけでなく、感想文などで実施することもあります。
2は間違いです。
再話の目的は、学習者が理解したことを自分の言葉で説明することで、知識の定着を図ることです。
段落間の関係性といった意味部分も理解できていないと、再話が成立しないですね。
3は間違いです。
4は何も問題ありません。
これが正解です。
問4 読解テストを作る際の留意点
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
授業で扱った文章をそのまま工夫することなく出題してしまうと、直前の記憶で解けてしまって、読解テストとしては不適切ですね。
1は間違いです。
問題同士の結びつきが強いと「この問題から先はすべて不正解…」という学習者が出てきてしまいます。
各問題が独立していた方が良いですね。
2は間違いです。
3は何も問題ありません。
これが正解です。
質問文の意味が読み取れなくては、読解の文章が理解できたのかがわからないですね。
4は間違いです。
問5 クローズテスト
解説 クローズテスト
初代の内閣総理大臣は、( )です。
その答えになる理由


4が「クローズテスト」の内容そのままですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら