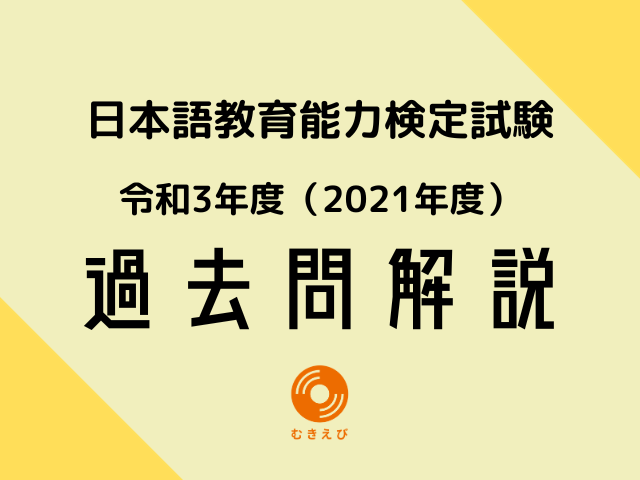令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅰ 問題6
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
著:公益財団法人日本国際教育支援協会, 編集:公益財団法人日本国際教育支援協会
¥1,540 (2025/06/30 04:59時点 | Amazon調べ)
目次
前の問題はこちら
あわせて読みたい




【令和3年度 日本語教育能力検定試験 過去問】試験Ⅰ 問題5の解説!
令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における 試験Ⅰ 問題5の解説です。お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。 前の問題はこちら https://japanes...
問1 インプット強化
その答えになる理由


1と2は、インプットではなく、アウトプットの内容なので間違いです。
3と4は、教師側のアウトプットを工夫することで、学習者側のインプットを補助しています。
どちらもインプットの内容なのですが、4の前半が違いますね。
学習者が理解可能な内容だけにしてしまうと、その場でのインプットできる量は増えますが、インプット能力の強化にはつながりません。
3が正解です。
問2 最近接発達領域(ZPD)
解説 最近接発達領域(ZPD)
その答えになる理由


1が「最近接発達領域(ZPD)」の内容そのままですね。
これが正解です。
ヴィゴツキーは、最近接発達領域(ZPD)以外にも
- 外言 … 相手に何かを伝えるコミュニケーションのための言語
- 内言 … 自分の頭の中で、思考を組み立てるための言語
- スキャホールディング …「できない」から「できる」に至る上での支援・手助け
がキーワードです。
これらの概念を使って、子どもの言語発達を分析しています。
問3 「プロジェクト型学習」で設定するテーマ
解説 プロジェクト型学習(プロジェクト・ワーク)
コミュニカティブ・アプローチの考え方が基礎になっており、読む・書く・聞く・話すの4技能を総合的に伸ばして、コミュニケーション能力を高める効果があります。
その答えになる理由


4が明らかに間違いですね。
やる前から答えがわかるテーマだと、学習者間での活発なコミュニケーションが生まれにくくなり、プロジェクト型学習の目的が果たせなくなります。
問4 KJ法
解説 KJ法
その答えになる理由


2が「KJ法」の説明そのままですね。
これが正解です。
問5 ジグソー法
解説 ジグソー法(ジグソー・リーディング)
その答えになる理由


1が「ジグソー法(ジグソー・リーディング)」の説明そのままですね。
これが正解です。
次の問題はこちら
あわせて読みたい




【令和3年度 日本語教育能力検定試験 過去問】試験Ⅰ 問題7の解説!
令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における 試験Ⅰ 問題7の解説です。お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。 前の問題はこちら https://japanes...
過去問解説の一覧はこちら
あわせて読みたい




日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
過去問に掲載されているのは解答のみです。「解答だけ見ても、しっくりとこない…」「きちんと正答・誤答の理由を確認したい」という方は、ぜひご活用ください。 まずは...