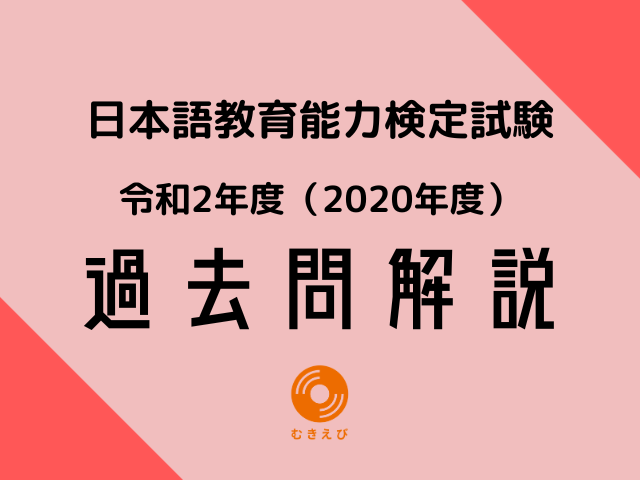令和2年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題9
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 異文化間葛藤
その答えになる理由


それっぽい言葉が出てきたときは、物怖じせず意味を類推してみましょう。
異文化と何の間か?を考えると、「異文化⇔自文化」であると想定できます。
また「葛藤」とは、心の中にそれぞれ違った方向・相反する方向の考えがあって、その選択に迷いが生じている状態」のことですね。
そのため、「異文化間葛藤」とは、「異文化と自文化の間に相反する考えがあって、その選択に迷いが生じている状態」であると言えます。
3がドンピシャで正解です。
ほかの選択肢を見てみると…
1・2は、「同一化」「同一の感情」が違います。
葛藤は、選択に迷いが出ている段階であり、これらは葛藤を乗り越えたあとに出てくる内容です。
4は、「自我の統合」が違います。
今回聞かれているのは、「異文化 ⇔ 自文化」の内容です。
問2 直接・双方向方略
その答えになる理由


「直接・双方向方略」という用語を知っている必要はありません。
心理学の用語なので、大半の受験生は知らないはずです。
- 直接 ⇔ 間接
- 双方向 ⇔ 一方向
が想定できれば、
- 直接・双方向
- 直接・一方向
- 間接・双方向
- 間接・一方向
という4つに分けられることも類推できます。
- 葛藤を解消するために、相手に対して、どのようにアプローチをとるか?
- 相手の欲求にどれだけ丁寧に配慮をするか?
がポイントです。
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、相手に対して、直接的にアプローチしています。
また、一方的に伝えており、相手の欲求への配慮が小さい内容になっていますね。
これは、直接・一方向方略です。
2は、相手に対して、間接的にアプローチしています。
また、一方的に離れており、相手の欲求への配慮が小さい内容になっていますね。
これは、間接・一方向方略です。
3は、相手に対して、間接的にアプローチしています。
また、状況を相手に伝えており、相手の欲求への配慮が大きい内容になっていますね。
これは、間接・双方向方略です。
4は、相手に対して、直接的にアプローチしています。
また、両者が守るルールを設定しており、相手の欲求への配慮が大きい内容になっていますね。
これは、直接・双方向方略です。
問3 ジョハリの窓
解説 ジョハリの窓
自己開示の程度について分析するために、
- 自分自身が知っているか?
- 他人が知っているか?
の視点により、4つの窓に当てはめて考えます。
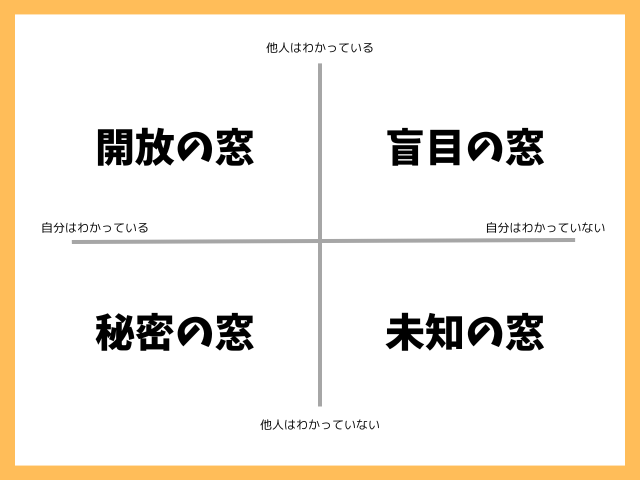
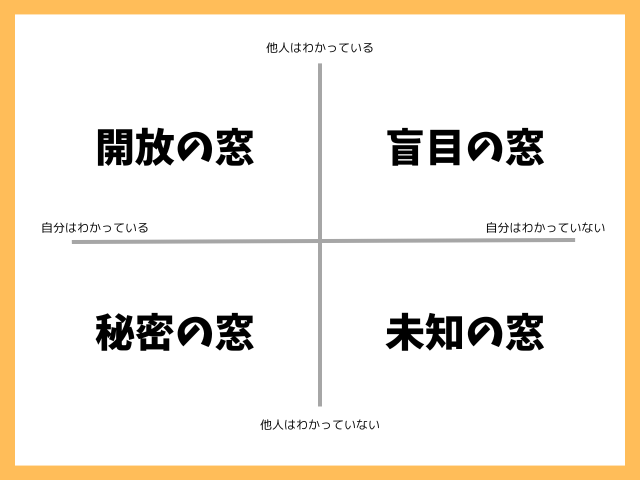
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
他者の意見を聞こうとせず、頑固者になる傾向があるのは、「秘密の窓」が大きい人ですね。
1は、間違いです。
「盲目の窓」が大きい人は、自分が自身について知らないことが多いため、他者の自分に対する反応への感受性が低い傾向にあります。
2が正解です。
周囲は知っているが、本人が全く気づいていない部分は、「盲目の窓」ですね。
3は、間違いです。
自分も周りの人も気づいていない、可能性を秘めた部分は、「未知の窓」ですね。
4は間違いです。
問4 偏見
解説 ステレオタイプ 偏見 差別
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
他者に対する無意識的な否定感情は、「偏見」の内容ですね。
1は、適当な内容です。
自集団の立場を優位にするということは、相対的に他集団を劣位にするということであり、これも「偏見」の内容ですね。
2は、適当な内容です。
感情をもっているだけ・考えているだけであれば「偏見」ですが、排除行動までいくと「差別」になってしまいます。
3は、偏見に対する記述として不適当です。
他者を否定的に捉える考え方は、「偏見」の内容ですね。
4は、適当な内容です。
問5 再カテゴリー化
解説 カテゴリー
その答えになる理由


「集団間の再カテゴリー化を促す活動」とは、
- すでにカテゴリー化されている集団同士を
- ごちゃまぜにして、再度カテゴリー化する活動
であると推測できます。
1が当てはまりそうですね。
これが正解です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら