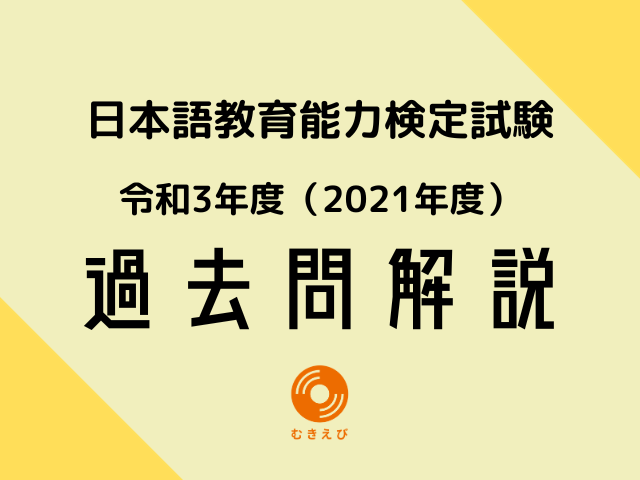令和3年度 日本語教育能力検定試験の試験問題における
試験Ⅲ 問題9
の解説です。
お手元に、問題冊子をご用意の上でご確認ください。
前の問題はこちら


問1 2019(令和元)年度外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果
その答えになる理由


出典元はこちら
P1より、2019年度に日本の大学(大学院)等を卒業(修了)した留学生62,411人のうち、75.6%にあたる47,179人が進学・就職のために日本国内に留まっています。
4が正解です。
問2 内集団バイアス
解説 バイアス
解説 内集団バイアス
その答えになる理由


3が「内集団バイアス」の内容そのままですね。
これが正解です。
悩むとすれば4ですが、「公正だと信じること」の部分が違います。
実際に公正かどうかに関係なく、ある集団の方が良いと考えるのが「バイアス」の働きです。
問3 接触仮説
解説 接触仮説
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
教師と生徒の立場は、指導する側・指導される側なので、対等ではないですね。
1は、接触仮説の内容として適切ではありません。
職員と外国人住民の立場は、支援する側・支援される側なので、対等ではないですね。
2は、接触仮説の内容として適切ではありません。
大学公認サークル内での留学生と日本人学生の立場は、いずれもサークルに所属する学生であり、対等ですね。
3は、接触仮説の内容として適切です。
日本人と留学生の立場は、招待する側・招待される側なので、対等ではないですね。
4は、接触仮説の内容として適切ではありません。
問4 異文化トレーニング
解説 バファバファ
解説 バーンガ
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
異文化環境でのマナーやルールを学ぶこと自体は異文化トレーニングですが、講演会で説明するだけでは、トレーニングになっていません。
1は、異文化トレーニングの例として不適当です。
単に異文化場面のロールプレイをするだけで終わらず、どう感じたかを話し合うことで、自身の中のギャップを言語化することにつながります。
2は、異文化トレーニングの例として適当です。
異文化トレーニングは、4のようなゲーム形式のほか、実際に経験した場面を例に行うこともあります。
より実践的になり、具体的な内容に取り組みやすくなりますね。
3は、異文化トレーニングの例として適当です。
異文化シミュレーションゲームに参加することで、経験したことがない異文化にも触れることができます。
ゲーム形式なので、学習者全員が参加しやすいのも良いですね。
4は、異文化トレーニングの例として適当です。
問5 ファシリテーターの関わり方
解説 ファシリテーター
その答えになる理由


選択肢を1つずつ見ていきましょう。
1は、前半部分が違います。
どんなグループワークでも、目標を設定しないことはありません。
2は、何も問題ありません。
これが正解です。
3は、後半部分が違います。
学習者の発言を促進させて、そこから一定のまとめをアウトプットさせるのがファシリテーターの役割です。
4は、後半部分が違います。
参加者が同じであっても、学習者の発言のハードルを下げるためにアイスブレイクは有効です。
次の問題はこちら


過去問解説の一覧はこちら